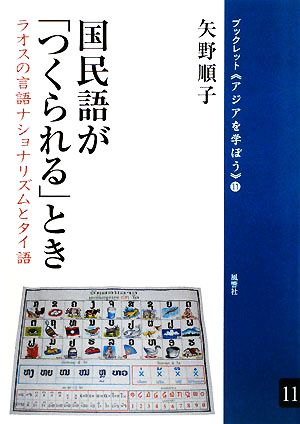
- 中古
- 書籍
- 書籍
国民語が「つくられる」とき ラオスの言語ナショナリズムとタイ語 ブックレット アジアを学ぼう11
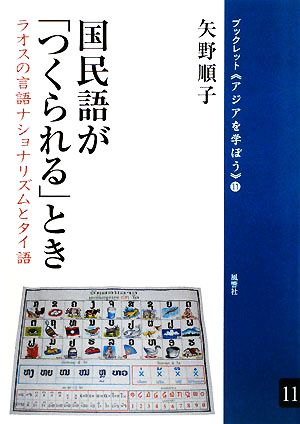
定価 ¥880
¥550 定価より330円(37%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 風響社 |
| 発売年月日 | 2008/11/10 |
| JAN | 9784894897380 |
- 書籍
- 書籍
国民語が「つくられる」とき
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
国民語が「つくられる」とき
¥550
在庫なし
商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
開発と言語の関係は非常に興味深いテーマである。宣教師の布教活動や植民地支配まで遡ることのできる「開発」の歴史を見ると、公用語・国民語を作り出すことは、文明開化・独立の象徴であると同時に、権威者が支配を行う土台でもある。本書は、ラオスの「国民語」はなぜ作られたのかを、フランス植民地...
開発と言語の関係は非常に興味深いテーマである。宣教師の布教活動や植民地支配まで遡ることのできる「開発」の歴史を見ると、公用語・国民語を作り出すことは、文明開化・独立の象徴であると同時に、権威者が支配を行う土台でもある。本書は、ラオスの「国民語」はなぜ作られたのかを、フランス植民地時代から1975年までの歴史をひもといたものである。 1893年、フランスとシャム(タイ)の権力者の交渉によって人びとが長い時間スパンの移動で形成された生活空間が切り分けられ、「ラオス」という国が誕生した(p13)。言葉のつながりは土地ほどきれいに分けられないものの、ラオスの権力者は自らの境界線を守るためにラーオ語の優越性やタイ語との差異化を求めていた。ラオスの国民語はどのようにつくられたかについて、「語源型」(言語機能の健全性重視)「音韻型」(伝統・根源性重視)と「ローマ字表記」(普及可能性重視)という3つのルート(p38)があり、その背後には異なるバックグラウンドを持つ知識人が存在していた。植民地支配や流亡などといった複雑な経験の持ち主が「純粋な国語」の創出に巻き込まれた姿が窺える。本書は短いものの、民族・アイデンティティ・国家・言語の複雑な様相を呈している。同じテーマは、その後に『国民語の形成と国家建設―内戦期ラオスの言語ナショナリズム』(2013)に発展された。 本書の最後に作者は、ラオスの人びとがラーオ語を守る意志がある限りラーオ語はなくならないという明るい展望を示した。しかし、ラオスで国民語を作ろうとする意志はタイによる侵食への抵抗によって活性化されたとはいえ、今日のラーオ語を維持しているのはどんな意志であろうか。私はラオスに初めて行ったのは今年の8月で、ラオスのテレビは(ほぼ?)タイ語の番組を放送していることに覚えた驚きはまだ記憶に新しい。そこから、言語の使用とアイデンティティの確保は必ずしも直接に結ばれているわけではなく、学校教育やメディアに関する諸制度の確立によって、言語が「脱(話者)意志」で維持されることは、現代における国民語の特徴なのではないかとも思うようになった。ラオスの国民語の事例を踏まえて自分自身の研究(中国の開発)をみた時に、「開発を抵抗するための開発」や、意志の産物と解釈された「脱意志の変化」に目を向ける必要性を改めて感じた。 (東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程 汪牧耘)
Posted by 
タイ語とラオス語(ラオ語)はとても似ていると聞いて興味を持って読んでみました。 言語というのはどうしても政治や戦争、他国の支配などから自由でいることは難しく、また現代においてはテレビや映画、人の行き来の影響も大きいということがわかりました。ラオス語を大切に守ろうとしている人も多い...
タイ語とラオス語(ラオ語)はとても似ていると聞いて興味を持って読んでみました。 言語というのはどうしても政治や戦争、他国の支配などから自由でいることは難しく、また現代においてはテレビや映画、人の行き来の影響も大きいということがわかりました。ラオス語を大切に守ろうとしている人も多いと知って、言語について改めて興味が増しました。
Posted by 
[ 内容 ] 近似する言語を持つ隣国タイ。 その強大な政治・文化の磁場にさらされ続けるラオスにとって、言語の独自性は独立の証しである。 国民性を創り、守り育てる現場からレポート。 [ 目次 ] 1 「ラオス」の誕生―メコン川に引かれた国境線(ラーンサーン王国―繁栄と没落;国境線...
[ 内容 ] 近似する言語を持つ隣国タイ。 その強大な政治・文化の磁場にさらされ続けるラオスにとって、言語の独自性は独立の証しである。 国民性を創り、守り育てる現場からレポート。 [ 目次 ] 1 「ラオス」の誕生―メコン川に引かれた国境線(ラーンサーン王国―繁栄と没落;国境線と言語の「境界」―分断されたラーオ人たち;「失地回復」と大タイ主義;ラオス刷新運動―ラーオニャイ(大ラオス) ラオス内戦「二〇年戦争」―分裂するラーオ語) 2 ラーオ語を「つくる」―正書法をめぐって(ラーオ語正書法とタイ語正書法;ラーオ語は「遅れた言語」か?;ラーオ語正書法をめぐって―タイ語との「境界」設定;「国民語」、「国民の文学」;王国政府とパテーと・ラーオへ) 3 ラーオ語の「歴史」―「ラーオ語族Sakun Phasa Lao」の形成(ラーオ語、ラーオ族の「起源」―「ラーオ語族」;ラーオ語の「歴史」―「没落」と「復興」;タイ人は「ラーオ系民族」か?;) 4 ラーオ語か、タイ語か―言語ナショナリズムの昂揚(新しい娯楽とタイ語;「パーサー・パー・シィア」;アカデミーへの批判) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by 

