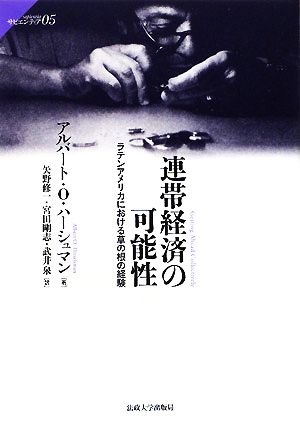
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-11
連帯経済の可能性 ラテンアメリカにおける草の根の経験 サピエンティア05
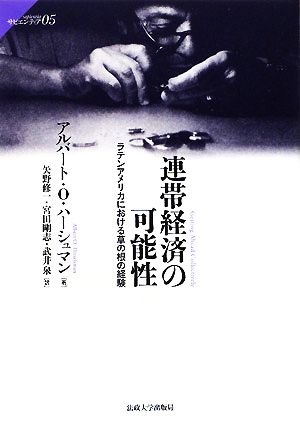
定価 ¥2,420
1,650円 定価より770円(31%)おトク
獲得ポイント15P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 法政大学出版局 |
| 発売年月日 | 2008/12/22 |
| JAN | 9784588603051 |
- 書籍
- 書籍
連帯経済の可能性
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
連帯経済の可能性
¥1,650
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.3
4件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 小さき人びとの挑戦! 共生と連帯をめざして新自由主義的グローバリゼーションに異議申し立てをおこなう、小さなプロジェクトへのまなざし。 [ 目次 ] 序論 第1章 逆のシークエンス―前提条件と結果の逆転 第2章 その他の注目すべきシークエンス 第3章 協調行動がなぜ生まれたか1―外部からの攻撃に対抗して 第4章 協調行動がなぜ生まれたか2―過去の活動経験から 第5章 協同組合の無形の便益と費用 第6章 実践的社会活動に関わる組織 第7章 結局、どういうことなのか [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by 
この本はもちろん連帯経済の本ですが、要するに、人々の協調行動(連帯)がどのようにして生み出され、社会的な問題に繋がって行くのかということを、さまざまな事例から考えている本です。 分かりやすい事例から、人々の協調行動の過程と効果について、さまざまな考え方を提示しています。驚くべきは...
この本はもちろん連帯経済の本ですが、要するに、人々の協調行動(連帯)がどのようにして生み出され、社会的な問題に繋がって行くのかということを、さまざまな事例から考えている本です。 分かりやすい事例から、人々の協調行動の過程と効果について、さまざまな考え方を提示しています。驚くべきは、1984年(2008年に和訳)に書かれたこの本で書かれている協調行動についての解釈が、今なお色あせていないということです。 - 以下、ひとりごと - たとえば、「人々が住宅の所有権を持つことで、はじめて街の環境が改善しうる」という、一見当たり前の考え方に対して、「住宅の所有権を所有するための行動が、街の環境を改善している(=所有権を獲得していないことが改善に繋がっている)」という考えを、ある事例から導き出しています。 私が本書から読み取った重要な指摘は2つあります。1つ目は、私的動機(自分の生活に関わること)が、協調行動を通して社会的運動(社会に関わること)へと繋がって行くというプロセス。また、協調行動が個々人の生活に影響を与えるというプロセス。つまり、私的行動から協調するだけではなくて、協調に参加することが、個々人をそのあとの社会的運動のプロセスまでつなげてゆく可能性があるということ。 2つ目は、協同組合には「非金銭的な便益・費用(損失)」が存在するということ。たしかに協同組合も事業である以上は経営合理化は欠かせない。ですが、協同組合によってもたらされる連帯や協調行動は、金銭的な尺度だけでは計れないということです。 国連が2012年を「国際協同組合年」として定めたように、今日の協同組合の意義は、このような協調の過程、効果にあるのでしょう。その点で、数々の事例からそのことを示す本書は面白いです。
Posted by 
学術書とかじゃなくて、筆者がラテンアメリカ各国を見てまわった旅行記的な感じでした。 もちろんただの旅行記じゃなくて、連帯経済の可能性について述べてる本なんですが。 世界社会フォーラムで掲げられた連帯経済と関係があるのかただ単に連帯している経済なのかわからないけど、草の根で新...
学術書とかじゃなくて、筆者がラテンアメリカ各国を見てまわった旅行記的な感じでした。 もちろんただの旅行記じゃなくて、連帯経済の可能性について述べてる本なんですが。 世界社会フォーラムで掲げられた連帯経済と関係があるのかただ単に連帯している経済なのかわからないけど、草の根で新しい小さな経済システム作ろうと共同で頑張っている人たちの姿、とても頼もしく感じた。 この本でとりあげられていた草の根活動は外部から入ってきた人がある地域に対してプロジェクトをおこなってるとかじゃなくて、例えば自由貿易協定などの影響をもろに受けた農民たち等が自ら立ち上がって行動している。そこに、海外特にヨーロッパ諸国のNGOからの資金援助があるっていう感じ。この形が一番望ましいんやと思う。外部の人間がゴールをたてたってあかん。 昨日レビュー書いたシューマッハーの本にも、途上国の人間に対する教育で農業とかの教育が大事って書いてあったんやけど、それがまさに実践されているのがあって素晴らしいと思った。 もちろん「それって農業に縛り付けることになるやん」という反論は可能やけど(それはフェアトレードにしたって同じ)、人口の多い途上国では農業に関わる人間が多くなるのは変えられないと思うし、農業で生きていけないのならばそのシステムが悪いと思う。一次産品のことを考えるとき、どうしても国内でも不等価交換が起こっている気がしてならん… 持続可能な農法のノウハウと流通システム(小さい)を改善することでまだまだ向上すると思う。これは先進国にもいえること。
Posted by 



