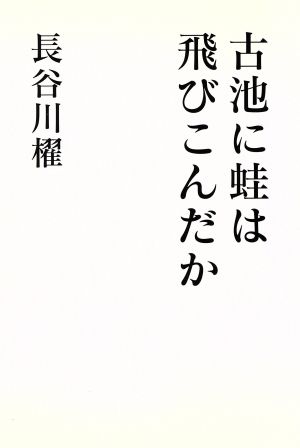
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1220-05-00
古池に蛙は飛びこんだか
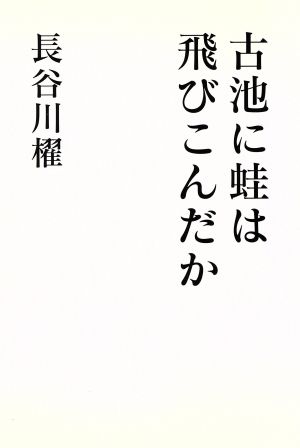
定価 ¥2,200
220円 定価より1,980円(90%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 花神社 |
| 発売年月日 | 2005/06/01 |
| JAN | 9784760218073 |
- 書籍
- 書籍
古池に蛙は飛びこんだか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
古池に蛙は飛びこんだか
¥220
在庫なし
商品レビュー
4.7
3件のお客様レビュー
まるで推理小説を読んでいるようでした。 俳句には疎いわたしですが、松尾芭蕉がその時代を飛びぬけた俳句を作ったということはわかりました。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「古池や蛙飛び込む水の音」・・・この句は蕉風開眼の句とされています。 蛙が池に飛び込んだだけで何が面白いのか? その謎を解くために一冊丸ごとこの句の説明に費やしています。一級のミステリー本でもあります。 従来和歌の世界においては、蛙は鳴くものであって、飛びこむものではなかった。「鳴く蛙」を「飛び込む蛙」へ置き換えただけでも凄く斬新なのですが、さらに以下のような情況で、この句が創られています。 この句は蛙の飛び込む音を聞きながら、芭蕉庵で催された「蛙の句あわせ」に出された句であり、中下の「蛙飛び込む水の音」が先に出来て、上をどうしようかと議論になったそうです。そこで其角が「山吹や」と言ったのに対して、芭蕉はこれを採用せず、また「水」と「古池」の重なりにも関わらず「古池や」と置いた。 其角のいう「山吹」は文学的な根拠があり、和歌ではこれまでには蛙というか「河蛙(カジカ)」というと「山吹」と取り合わせてきた。 「山吹や 蛙飛び込む 水の音」等々 既にこの段階で、「山吹」でも「古池」でも、蛙が飛び込んだ「水」とは別の次元のものを取り合わせている。 言いかえると、この古池は芭蕉の想像上の池なのです。 芭蕉は「古池」と「蛙が飛び込んだ水」は別々のものであると思っていたからこそ、「古池」と「水」の重複など気にせずに「古池や」と置くことが出来た。 これは、何を意味しているというと、「古池や」は観念というか空想の世界であり、「蛙飛び込む 水の音」は現実の目の前の出来事である。 まさに空想と現実が混在している句となっているのが、この句の凄さだというのです。 芭蕉は和歌のように「かはづなくゐでの山吹」とも歌わないが、其角のように「山吹や 蛙飛び込む 水の音」としようとも思わない。因襲にとらわれるのでもなく、因襲を待向こうから批判するのでもない。そのどちらも超越した不思議な新しい空間に「古池や」という言葉はある。 以上拙い説明なので、十分説明出来たか自信がありませんが・・・ 因みにこの解釈からすると、「古池」に蛙は飛び込んでいないことになりますね。異次元の世界は越えられません。 この本ではこの句の切字の「や」の働きについて、また結構な分量を割いています。
Posted by 
「古池や蛙飛こむ水のおと」。 俳句に詳しくない人でも一度くらいは耳にしたことがある句だろう。作者はもちろん松尾芭蕉。俳句の代名詞みたいなものだ。それほど有名なのだから、きっと名句なんだろうと、誰もしっかり中身について考えたことがない。いや、考える前に、名句にちがいないという先入観...
「古池や蛙飛こむ水のおと」。 俳句に詳しくない人でも一度くらいは耳にしたことがある句だろう。作者はもちろん松尾芭蕉。俳句の代名詞みたいなものだ。それほど有名なのだから、きっと名句なんだろうと、誰もしっかり中身について考えたことがない。いや、考える前に、名句にちがいないという先入観があって、思考停止に陥ってしまうのだ。 「荒海や佐渡によこたふ天河」、「閑さや岩にしみ入蝉の声」のように、その詠みぶりから誰にも名句だと分かる句が芭蕉にはいくつもある。それなのに、なぜ芭蕉といえば「古池」の句が持ち出されるのか。「古池に蛙が飛びこんで水の音がした」というような句のどこがそんなにいいのか。この疑問はかなり古くから囁かれていたようだ。それだけに深読みをした解釈などもあったようだが、明治になり、正岡子規が表面に表れた意味しかないと喝破してこの方、先のような解釈が自明とされてきた。 その「古池」の句を再吟味して、この句は果たして古池に飛びこむ蛙を詠んだのか、ということを考えたのが著者の長谷川櫂である。自身俳人である著者は芭蕉ともあろうものが限られた十七音の中に「古池」と置きながら、もう一度「水の音」と繰り返すだろうか、という疑問を抱いた。調べていくと、この句、中下である「蛙飛こむ水の音」が先にできている。 中下に合う上五を考えているうちに弟子の其角は「山吹や」という上五を思いついた。和歌の世界では蛙の声を詠むとき山吹を取り合わせるのが定法だからだ。ところが、芭蕉はそれを採らず「古池や」とした。蛙といえば鳴き声を詠むものとされていたのに、飛びこんだ時の水音に着眼している芭蕉である。俳句という新しい革袋を作り上げようとしている芭蕉が、そこに古い酒を注ぐようなまねをするはずがない。結論を言うなら、蛙は古池に飛びこんでなどいない。蛙と古池は同じ位相にないからだ。著者の解説を次に引く。 「蛙飛こむ水のおと」は庵の外から聞こえてくる現実の音であるが「古池」は芭蕉の心に浮かんだどこにも存在しない古池である。どこにもない心の中の古池に現(うつつ)の蛙が飛びこむわけにはいかないだろう。 古池が先にあったのではなく、蛙の飛びこむ水音を聞いている芭蕉の心の中に、物寂びた古池のイメージが湧き起こってきたのだ。現実の情景に喚起され、作者の心の中に非現実の世界がまざまざと現出する。たった十七音の小宇宙の中で異なる二つの位相が出会う。蕉門俳句の新風を告げた句こそ「古池」の句であった。 そうと分かれば、これまで現実の情景を詠んだと考えられていた芭蕉の句が、次々と読みかえられてゆく。このあたりの展開のスリリングなことは、よくできたミステリで名探偵が謎解きをしている場面を読んでいるようなものだ。俳句には詳しくない読者でも面白いように分かる。 ものごとを自明のものとして見るのでなく、自分がおかしいと思ったことはとことん突きつめて考えてみる。そうすることで思っても見なかった事実が発見される。長谷川氏の見解が新しいものなのか、そうでもないのか門外漢には分かりかねる。ただ、ここには批評というものの持つ清新な思考の輝きが感じられることは確かだ。
Posted by 



