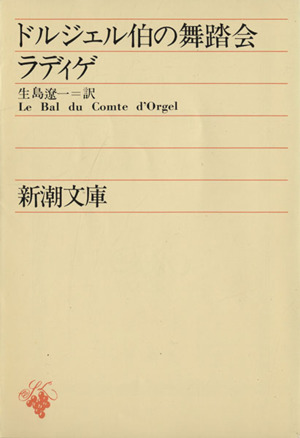
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
- 1225-16-08
ドルジェル伯の舞踏会 新潮文庫
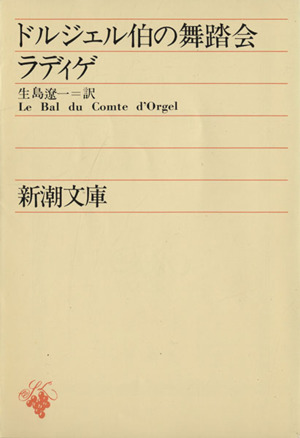
定価 ¥473
110円 定価より363円(76%)おトク
獲得ポイント1P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/22(土)~2/27(木)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社 |
| 発売年月日 | 1953/08/25 |
| JAN | 9784102094013 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/22(土)~2/27(木)
- 書籍
- 文庫
ドルジェル伯の舞踏会
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ドルジェル伯の舞踏会
¥110
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
13件のお客様レビュー
185P 初版発行: 1924年 レーモン・ラディゲ Raymond Radiguet 生年:1903年 没年:1923年 フランスの詩人・小説家。風刺画家を父として、パリ郊外に生まれる。幼少期は成績優秀な生徒だったが、長じて、文学に傾倒。14歳で『肉体の悪魔』のモデルといわ...
185P 初版発行: 1924年 レーモン・ラディゲ Raymond Radiguet 生年:1903年 没年:1923年 フランスの詩人・小説家。風刺画家を父として、パリ郊外に生まれる。幼少期は成績優秀な生徒だったが、長じて、文学に傾倒。14歳で『肉体の悪魔』のモデルといわれる年上の女性と恋愛関係となり、欠席が増えて退学処分となる。退学後、詩人のジャコブやコクトーと出会い、処女長編小説の本作で文壇デビュー。ベストセラーとなる。その後もコクトーと旅をしながら『ドルジェル伯の舞踏会』を執筆するが、1923年、腸チフスにより20歳の若さで死去。 ドルジェル伯の舞踏会 (光文社古典新訳文庫) by ラディゲ、渋谷 豊 マオはラ・ヴェルブリーで野生の 木蔦 のように育った。この娘の美しさと知性はすぐに開花したわけではないが、それだけに着実にはぐくまれていった。両親は彼女を愛していないわけではなかった。だが、彼らの愛し方はいたって消極的だったので、彼女が愛情に包まれていると感じるのはマリーと一緒にいるときだけだった。マリーというのはグリモワール家の人たちがまるで家財道具のように貸し借りし合っている年とった黒人の女性だ。彼女がマオに注ぐ愛情は、目下の者が主人に捧げるそれ、つまり、恋に最も近い愛情だった。 フランスではかつてカトリックが国教とされていたが、脱宗教化の結果、公立小学校から宗教色が除かれ、カトリックの教義などが教えられることはなくなった。ただし、子女に従来通りの宗教教育を受けさせたいと願う親には、私立小学校に通わせるか、あるいは学校に通わせずに親か家庭教師が教育するという選択肢が残されていた。作中では政教分離が行われたということと「ラ・ヴェルブリーの地で」マオを育てなければならないということとの因果関係が明瞭に示されてはいないが、ことによるとグリモワール家の人たちは熱心なカトリック教徒で、マオを公立小学校に通わせるなどもっての他と考え、自宅で教育することにしたのかもしれない。そう解釈するのであれば、「ラ・ヴェルブリーの地で」という言葉は「グリモワール家の屋敷で」という程の意味となる。 ところで、公然の秘密と言えば、コクトーとラディゲの同性愛もまた公然の秘密でした。じつはこれは確たる証拠のある話ではなく、真相は 藪 の中ですが、とはいえ状況証拠には事欠かず、やはり二人は同性愛で結ばれていたのだと考える研究者が今日では大勢を占めています。 ラディゲには年上の女性に惹かれる顕著な傾向があったようにも思えますが、実際は同世代の女性の若々しい魅力にもけっして無関心ではありませんでした。 「悪徳」を云々する作者の脳裏にあるのは、一八世紀の作家ラクロの『危険な関係』だったかもしれません。『危険な関係』(ちなみに本作には『危険な関係』への言及があります)は「悪徳」の化身のような男女が暗躍するめっぽう面白い恋愛小説ですが、ラディゲはあたかもそれに対抗するかのように、この世には「悪徳がはりめぐらせる策略」よりもさらに不思議なもの、面白いものがあるのではないかと問うのです。悪徳から遠く隔たった「純粋な魂」も、じつは 無意識のうちに 奸計を弄しているのではないか。当人が知らず知らずのうちに用いる詐術や偽計ほど興味深いものはないのではないか──こんなところが彼の見当です。それにしても、「無意識」という言葉で彼は何をイメージしていたのでしょう。 一九一三年 一〇歳 一〇月から始まる新年度は学校に通わず、父親のもとでラテン語、ギリシア語、英語を学ぶ。ボードレールやラファイエット夫人の作品に親しみ、数ページにわたって暗唱できるまでになったという。 ラディゲが 遺した雑多な文章の中に、恋愛小説にかんする短い省察が含まれています。そこで彼はスタンダールなどを名指ししながら、一九世紀フランスの恋愛小説に対する不満を漏らしています。「純粋さ」が足りない、というのです。不純物、すなわち〈恋愛以外のテーマ〉が混在しているじゃないか、という意味です。可能な限り純粋な恋愛小説を追求するとどうなるか。この雑然とした人生から恋愛のみを抽出し、恋する男女の心の動きの観察、分析に徹するとどうなるか。そんな科学の実験のような試みから生まれたのがこの『ドルジェル伯の舞踏会』です。その意味で本作は「純粋恋愛小説」とでも呼べるでしょうし(「純粋詩」と言うときと同じ意味での「純粋」です)、おそらくはその極北なのです。 すごいよな、こんな見方ができて、と。いい歳をして、二〇歳で死んだ若者に憧れているというのも滑稽な話ではありますが、どうやらこの憧憬の念が私をこの作品に繫ぎとめてきた要因であり、これからもそうであり続けるものと思われます。
Posted by 
巻頭のジャン・コクトーの追悼文によれば、本作品はレイモン・ラディゲが20歳でモノした彼の最高傑作ということで、ベッドで高熱に苦しみながらも校正刷りを読んでいたが、その後しばらくして亡くなったという。 文壇の批評では「冷たい心」を持っていたといい、コクトーによれば「硬い心」を持って...
巻頭のジャン・コクトーの追悼文によれば、本作品はレイモン・ラディゲが20歳でモノした彼の最高傑作ということで、ベッドで高熱に苦しみながらも校正刷りを読んでいたが、その後しばらくして亡くなったという。 文壇の批評では「冷たい心」を持っていたといい、コクトーによれば「硬い心」を持っていたといい、些細な接触には動じない人柄だったという。 確かにこのような心の機微を事細かに文章として表現する人は冷たくて硬い心が必要なのかもしれない。 この作品は個人の心の内面をこれまでもかというほどに描き晒すことに重点が置かれている心理小説で、物語の経緯とか登場人物間のかかわりの多くを捨象してまで内面の奥底を抽出することに力を入れている作品となっている。 訳の雰囲気にもよるのだろうが内面へのアプローチがある意味、明治の文豪たちの作品のような趣があり古き香りが漂ってくる感じであった。 あまりにも心理描写に力を入れすぎていてこんな風に思うことが本当にあるのかと感じる部分がところどころあるのと、また、ドルジェル伯爵夫人マオの女中や恋人フランソワの下宿先の身障者などいろいろ登場してくる人物の説明が最初にあったかと思えばその後スルー状態となる登場人物が何人もいたりして、これ以外にも多くの経緯が捨象されていてこれでもかと心理描写のだらだら感がひたすら続くので、若者が背伸びしたような繊細さと荒削りさが同居した作品のように感じられた。 特にフランソワの母親がマオの手紙を受け取った後の行動などは、えー!?本当にそんな風に考えるのかなという感じで違和感ありありだったかな。 また、マオがフランソワに惚れていくくだりなどはもう少し細やかな記述が欲しかったと思う。何せ最初マオは夫であるドルジェル伯爵に惚れていたのだから。 経緯の描写が削られているところが多々ある点については、フランソワの友人のポールとのかかわりが当初の出だしから考えるとあまりにも尻すぼみになったことや、ウィーンでドルジェル伯爵にいいよる美人のくだりをいっさい端折るなど、本当は物語を展開し心理に裏付けを持たせるために必要な部分で肉付けしたいところであるが、時間的制約もあり、あえて構想ノート的な部分も含めて作品化したのではないかと勘ぐりたくなる。 心理面に純化したといえばそれまでだが、小説というか小説家としては少々生き急ぎすぎたのではないだろうか。 この作品の一番の見どころは物語最後の仮面舞踏会を企画するくだりであるだろう。 突然にロシア亡命貴族のナルモフ公爵が登場して多少面食らったが、悲劇的なナルモフ公爵とノー天気なドルジェル伯爵、恋に悩む伯爵夫人のマオと開き直ったフランソワの4者の絡みと心理描写が面白く、究極のところラディゲはこの場面を描きたかったがためにこの物語を創作したのではと思ってしまう。 このあたりのラディゲの感性には若き才能が感じられたかな。 本書の裏には「最も淫らで最も貞潔な恋愛小説」とあったが、どこが「最も淫ら」なのかとんと分からなかった。 騙された・・・。
Posted by 
規定演技で技の出来栄えを競う、フィギュアスケートや体操競技などを観ているような印象。回転すべきところで回転し、跳躍すべきところで跳躍する、大層丁寧な演技を拝見しました、という感想。
Posted by 


