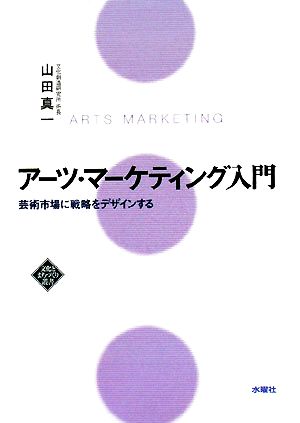
- 中古
- 書籍
- 書籍
アーツ・マーケティング入門 芸術市場に戦略をデザインする
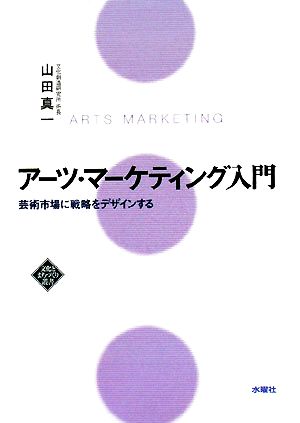
定価 ¥3,300
550円 定価より2,750円(83%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 水曜社 |
| 発売年月日 | 2008/06/28 |
| JAN | 9784880652139 |
- 書籍
- 書籍
アーツ・マーケティング入門
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
アーツ・マーケティング入門
¥550
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
個々のアート作品を観てその文脈を知ることも大好きだけど、それらのアート作品をいかに社会の価値にしていくかにも興味があります。 ということで読んだ本。 内容はびっくりするくらい「マーケティング」の本です。 マーケティングの手順が詳しく書いてあります。 具体的には「ビジョン→戦略...
個々のアート作品を観てその文脈を知ることも大好きだけど、それらのアート作品をいかに社会の価値にしていくかにも興味があります。 ということで読んだ本。 内容はびっくりするくらい「マーケティング」の本です。 マーケティングの手順が詳しく書いてあります。 具体的には「ビジョン→戦略→調査・分析→行動」の一連の流れ(PDCAサイクルとはちょっと違う?)や、それに付属するフレームワーク「マーケティングの4P」「環境分析の3C」などなど。 そしてこの本の最大の特徴かつ魅力は、そういったマーケティングのいわば基礎知識をアート市場に当てはめて詳しく分析しているところです。 こういった本は貴重。 ちなみに、この場合のアート市場は音楽が中心なのですが、美術でもある程度当てはめられると思います。 例えば普通の企業との違いに、利益拡大を目的にしていないところやそもそもアートという「商品」の特徴、専門性の必要性などを挙げています。 もちろんそれらが違えばあるべきアートマーケティングの姿も違う。 でも、いくら特殊とはいえ、やはり大事なのは 「顧客のニーズを満足させる」 「新たなニーズを生み出す」 ことのようです。 特に後者はこれから必要になってくることなのかなと思います。 アートマーケットの話を最近はよく聞きます。それだけ関心が向けられてきているということ。 また、ネットの活用によってマーケティングのやり方も変わると思う。 アートのマネジメントって、むつかしい。。。 だけど、やっぱり、私はアートのファンを増やしたい、アート好きの仲間を増やしたいと思う。
Posted by 
日本の「舞台芸術事業」をマーケティングの枠組みで捉えてみようとするときに何が課題か?はよく分かる。 ただ、「アーツ・マーケティング」をやろうとしたときに具体的に何をやればいいか?は他の本を読んだ方がいいと思う。 例えば「コトラー ソーシャル・マーケティング 貧困に克つ7つの視...
日本の「舞台芸術事業」をマーケティングの枠組みで捉えてみようとするときに何が課題か?はよく分かる。 ただ、「アーツ・マーケティング」をやろうとしたときに具体的に何をやればいいか?は他の本を読んだ方がいいと思う。 例えば「コトラー ソーシャル・マーケティング 貧困に克つ7つの視点と10の戦略的取り組み」http://d.hatena.ne.jp/quliqulickle/20100421/1271867564とか。 「課題解決!マーケティング・リサーチ入門」http://booklog.jp/asin/4478014035とか。 基本的には「芸術の売り方――劇場を満員にするマーケティング」http://d.hatena.ne.jp/quliqulickle/20100627/1277608768やコトラーのマーケティング基本本のベースに、日本の舞台芸術を乗せてみただけの感じ。 まあ、そうですよね。個々の課題や目標が何か分からないとマーケティングの戦略なんて立てようがないですから。 それでも、私が前の仕事をしていた2006年ごろにこういった本があれば私の仕事も違っていたかもしれない。 2008年6月に書かれたものを2年半後に読んでみて、2年半の間に私が得た知識で感じたこと。レベルの大小を気にせず。 1)「地方」の公共ホールにとって、マーケティングのとっかかりが、いきなりセグメント調査やターゲティングのための1次データのリサーチってハードル高い気がする。 そもそも近隣人口併せても数十万人。 キャパ3000人のホールで年間トータル300回公演しても90万席。 「市場を捉える」っていう意味でいくと、そこに来る可能性のある人は誰?というのを、まずは行政区をとっぱらったゼロベースでざっくり把握して、その上で、実際の来場者とのギャップを見る。 頻度なのか間口なのか。 そのギャップから解決すべき課題とか目標とかを探ってからの方がよさそうな気がする。 本書では、リサーチの目的がセグメントのターゲティングオンリーになってるんだけど、そのための基礎調査が先でしょ、と。 セグメント化は大事だし、いずれ課題解決のために必要だけど、ひとつのプロダクトの開発に何億円も投資して何億個も作って売ろうとしている「企業」の手法を教科書的に細かいとこからまねようとしてもリソースが足りないと思う。 2)プロダクト=製品?商品?大きく違うと思う。 「コトラーは製品と書いているが、最近の主要なマーケティング本では商品と書いているので商品にする」的なことが書いてあるんだけど、これって大きな違いだと思う。 製品は原料を仕入れ、加工したりして付加価値を付けたもの。 商品は仕入れられた完成品。 舞台芸術で言えば、製品=プロデュースもの、商品=買い公演みたいなもの。 そして、製品を作るためにはR&Dが必要なんだよな、と思い至る。 演劇で言えば文芸部なのかな。 ロジャーズの普及理論とかも含めて、リサーチの手順とか、ちょっと考えて実践してみたいなあ。
Posted by 



