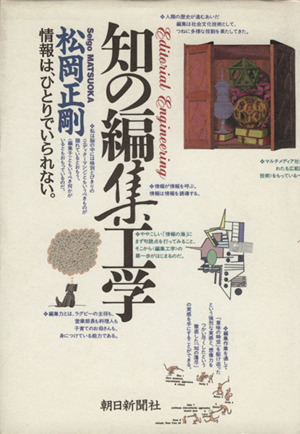
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-02-03
知の編集工学
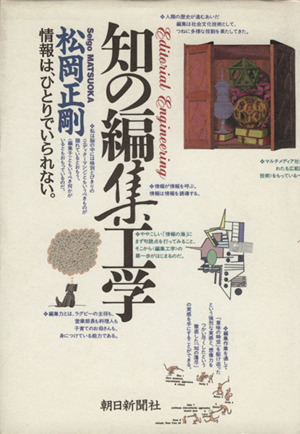
定価 ¥2,420
990円 定価より1,430円(59%)おトク
獲得ポイント9P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞出版 |
| 発売年月日 | 1996/07/24 |
| JAN | 9784022569882 |
- 書籍
- 書籍
知の編集工学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
知の編集工学
¥990
在庫なし
商品レビュー
3.7
8件のお客様レビュー
世の中における営為を「編集」という言葉で捉えてみたという本で、考え方として面白かった。その思考に従えば、他者との会話や読書さえも「共同編集」という考え方になり、認知の一部を組み替えたり、構成を考える事で再認知する作業である。実際、我々の認知や理解というものは、作文や動画を作り上げ...
世の中における営為を「編集」という言葉で捉えてみたという本で、考え方として面白かった。その思考に従えば、他者との会話や読書さえも「共同編集」という考え方になり、認知の一部を組み替えたり、構成を考える事で再認知する作業である。実際、我々の認知や理解というものは、作文や動画を作り上げる作業のように、強い主張や印象に残るものを優先的に組み上げていくものだ。 そのことは、対象物に対し自らも構図に含めた上で、メタに捉えて形容した表現とも言える。日々の生活は人生を編集しているとか、建築物を建てるのは地球を編集していると言えるとか、料理を作るのは健康を編集していると言えるとか、言い方次第。言い方次第だが、これはつまり、段階的な編集者(=支配者)の設定という立ち位置を自覚させるには良い考えであり、編集とは神の所業、勝者の所業とも言えそうだ。ゆえに、歴史は勝者によって語られるし、会社の編集権をもつのは社長、家庭の編集権をもっていたのは強大な母親の存在だった。エディターは細分化した神の模倣者である。 感情や意識をもつ人間がエンコード(記号化)とデコード(脱記号化)をはたしているモデル。送り手の人間が発言したい情報内容を脳の中でまとめ、次にこれを口などの感覚器官でエンコードし、これを発話メッセージなどとして相手に渡す(伝える)と、受け手の人間がそのメッセージを耳などの感覚器官をつかってデコードして理解するというもの。しかし、そのデコードされた他者の頭の中の世界は、送り手には分からないので、それぞれが編集権を持っているという事だ。我々は自らの肉体と認知に対して、神を模倣している。 この編集をするためのOSが宗教や義務教育、歴史認識などの国家観だという気がする。また、種として本能的に備わった正義感、モノミス理論のような共通項目だろうか。 せいごうさんの編集論は他の本で知っていたので残念ながら目新しさは無いが、やはり面白い物の見方だと思う。
Posted by 
言葉は記号である。 名刺の肩書は、自分の見出し・タイトルである。 「地(ground)-背景」と「図(figure)」の分解 脳の中では情報はハイパーリンク状態。 編集は、「情報の海」に突き刺さる句読点 「分節化」が編集の第一歩。 エディティングは、関係発見的な行為(メ...
言葉は記号である。 名刺の肩書は、自分の見出し・タイトルである。 「地(ground)-背景」と「図(figure)」の分解 脳の中では情報はハイパーリンク状態。 編集は、「情報の海」に突き刺さる句読点 「分節化」が編集の第一歩。 エディティングは、関係発見的な行為(メタファー・ アナロジー)
Posted by 
「情報は情報を呼ぶ」→連想ゲーム的 ニューロコンピューター 人間には、 ・論理的に試作を進めていく「逐次直列型の情報処理」 ・色々な情報をそれとなく頭の片隅において、論拠ははっきりしないけれど全体を総合してしまう「直感的で並列な情報処理」 ニューロコンピューターは後者の能...
「情報は情報を呼ぶ」→連想ゲーム的 ニューロコンピューター 人間には、 ・論理的に試作を進めていく「逐次直列型の情報処理」 ・色々な情報をそれとなく頭の片隅において、論拠ははっきりしないけれど全体を総合してしまう「直感的で並列な情報処理」 ニューロコンピューターは後者の能力をコンピューターにもたせようとした。 しかし失敗した。 そもそも、2つだけに分けようとしたことに無理があった。 また、人間の学習能力は実は対話型で、かつ遊び的である。 私たちが学習にあたって、その学習の相手になってくれる”もうひとりの私”を用意しているのである。幼児にとっては母親、大学においては先生、あるいは、それを凌駕した自分の未来像などである。
Posted by 



