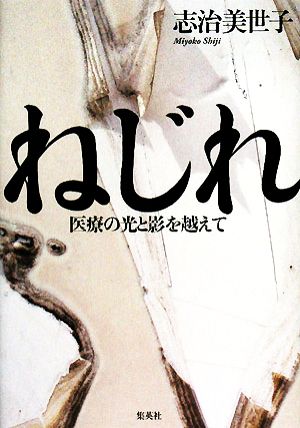
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1214-01-06
ねじれ 医療の光と影を越えて
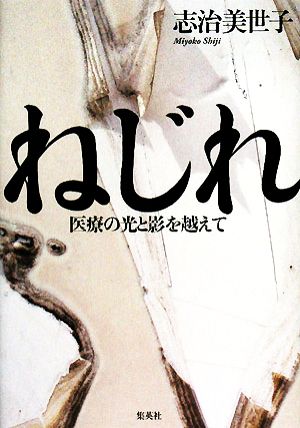
定価 ¥1,760
220円 定価より1,540円(87%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 集英社 |
| 発売年月日 | 2008/05/06 |
| JAN | 9784087813937 |
- 書籍
- 書籍
ねじれ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ねじれ
¥220
在庫なし
商品レビュー
2.7
3件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
著者と飲み屋で遭遇することがあるのだが,なんだかなーという人なので,どんな本を書いているのか興味があって図書館から借りてみた。 医療関係のノンフィクションは難しい。なぜなら中立的な判断が難しいからである。裁判であれば,どうしても一方の立場になってしまう。医療過誤を訴えた方が正しいとされることが多いが,本当にそうなのかは難しい。 この本も中立的とはいえない。真実はどこにあるかは分からないから,なんとも言えないが。飲み屋でくだを巻く著者にしてはちゃんとした本かもしれないが,随所に鼻に付く表現がある。 開高健ノンフィクション賞に値する理由は不明。 2013/02/03図書館から借用;直ちに読み始めて,風邪で休んでいた02/05の午前中に読了
Posted by 
訴訟事例を中心に、医療問題について書いたノンフィクション。開高健ノンフィクション賞受賞。現状では、カルテの改ざんなどの犯罪、ある程度の確率で起こりうる事故、医療ミスなどの過誤が全て司法の場に持ち込まれている。著者はこれを「結果こそ大事だと考える患者側と過程が大切で結果には責任が持...
訴訟事例を中心に、医療問題について書いたノンフィクション。開高健ノンフィクション賞受賞。現状では、カルテの改ざんなどの犯罪、ある程度の確率で起こりうる事故、医療ミスなどの過誤が全て司法の場に持ち込まれている。著者はこれを「結果こそ大事だと考える患者側と過程が大切で結果には責任が持てないと考える医療者」という考え方の違いだと言うが、ちょっと紋切り型にすぎるように感じた。問題はむしろ、これらの事態が発生した際に、話し合いで合意ができなければ司法の場に持ち込むしかないということで、これにはやはり無過失補償制度などシステム面での整備が必要だと思う。「勝訴によっても救われることのない被害者」という表現はその通りで、命が失われてしまうと裁判で勝っても空しいだけだし、医療サイド・患者サイドともに現在のシステムは不十分なものだと思う。
Posted by 
たまにやたらと感傷的な描写が入ること以外は、まぁいいじゃないかと思う。 3つの事件(医療過誤?、過労死自殺?、診断ミス?)を切り口として、日本の医療問題の現状を描いている。 3件の関係者(被害者?)のうち、患者側サイドで取り上げられていた2者がそれぞれ報道関係者と病院関係...
たまにやたらと感傷的な描写が入ること以外は、まぁいいじゃないかと思う。 3つの事件(医療過誤?、過労死自殺?、診断ミス?)を切り口として、日本の医療問題の現状を描いている。 3件の関係者(被害者?)のうち、患者側サイドで取り上げられていた2者がそれぞれ報道関係者と病院関係者ということだったので、世に対して自らの経験を語ることに対する葛藤は多少少なかったのかもしれない。 興味深いなと思ったのは第三章で、無過失保障、ADR(裁判外紛争処理)、解剖等の制度的な側面に関して、医師の意見と現状が記されていて大変参考になった。 僕自身の結論としては、人間の道徳心に頼って医師と患者の「歩み寄り」を成し遂げるのは難しいのではないかということだろうか。 例えば書中では裁判に提出される鑑定意見書(不審死などの事象に対して所見を述べるもの)の日本医療界における位置づけの軽さが指摘されている。簡単に言うと、いくら書いてもまったく得をしないのだ(まじめに書いて論文並みのクォリティを達成しても誰も評価してくれない、おまけに患者サイドに立って書くと「象牙の塔」からはじき出される)。これに対してドイツでは、裁判等に提出される鑑定書が、執筆した医師の評価基準の1つとして確立されているとのこと。 インセンティブをカネと名誉に分類するなら、この二つを傷つけず、時に増加させる(ミスの発見・報告・改善を社会的に奨励する)ような制度を構築することによって、著者が言う「ねじれ」を乗り越えての歩み寄りが可能になるのかもしれない。 なんかもやっとした感想だな・・・。医療というフィールドの特殊性(人の命を扱う)、専門性(閉鎖的かつ難しい)にとらわれてしまって、つい医療のフィールドだけで議論してしまいがちだけど、もっと多様な分野の制度設計・政策立案の専門家や一般の人々の意見を柔軟に取り入れていく必要があるな〜と感じた。 追記:全然関係ないことだけど、普段病院にいくと医師や看護婦がやたらと冷たいな〜と感じることがある。実際こう感じた人は少なからずいると思う。しかし彼らの立場に立ってみれば、僕はその日来院する多くの患者のうちの一人に過ぎないわけであり、全ての患者に対して満額のホスピタリティをそそげるわけではないということもまた事実である。それだけ。
Posted by 



