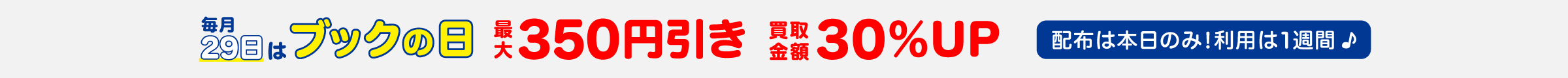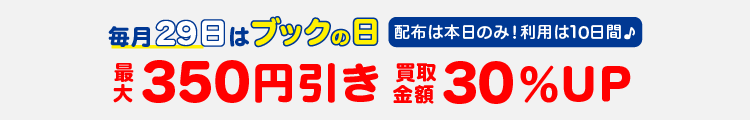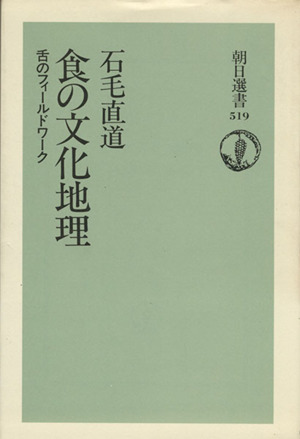
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-07-00
食の文化地理 舌のフィールドワーク 朝日選書519
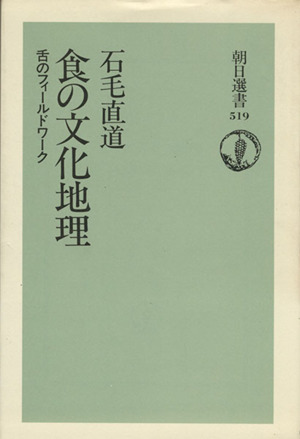
定価 ¥1,650
385円 定価より1,265円(76%)おトク
獲得ポイント3P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞出版 |
| 発売年月日 | 1995/01/11 |
| JAN | 9784022596192 |
- 書籍
- 書籍
食の文化地理
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
食の文化地理
¥385
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
東アジア、東南アジアが中心だが、各地の食文化について詳しく、穀醤・魚醤やナレズシなどの分布地図が掲載されているなど、食文化の広がりやその背景を考える上でもおもしろい。 ・根栽作物は、紀元前の時代にインドネシアからアフリカに伝搬した。 ・魚醤は、小魚・アミなどでつくった塩辛の上澄...
東アジア、東南アジアが中心だが、各地の食文化について詳しく、穀醤・魚醤やナレズシなどの分布地図が掲載されているなど、食文化の広がりやその背景を考える上でもおもしろい。 ・根栽作物は、紀元前の時代にインドネシアからアフリカに伝搬した。 ・魚醤は、小魚・アミなどでつくった塩辛の上澄み液を集めたもの。日本のしょっつるも同様の調味料。 ・朝鮮半島のテンジャンは味噌玉だけで作ったもので、八丁味噌などの豆味噌と同じ製法。発酵した大豆の液体部分を集めたものがカンジャンで、たまり醤油と同じ。 ・華北では、新石器時代にアワ・キビを主食としていたが、漢代以降にコムギの粉食(饅頭・麺条)が始まった。唐代に西方から水車製粉の技術が導入され、粉が大量に生産されるようになった。米は、大運河で華北に輸送されてきた。食肉とされたのはブタ、ニワトリ、アヒルで、牛・馬は役畜とされた。 ・東南アジアでは、スパイスやハーブをすりつぶすなどするために小型の石臼または石皿と石杵を用いる。農業は、根栽作物の後に雑穀類と陸稲を経て水稲へと変化した。現在は、在来のタロイモ、ヤムイモなどよりも、新大陸起源のトウモロコシ、キャッサバ、サツマイモの方が重要になっている。 ・マレー半島のマレー人の多くは、12世紀以降にスマトラのミナンカバウから移住してきた。中国人は1830〜1930年の間に移民してきた。インド人はイギリス統治下の1900年頃にゴムのプランテーション労働者として連れてこられた。 ・モルッカ諸島は、西洋で珍重された四大スパイスのうち、チョウジとニクズクの産地で、香料諸島と呼ばれた。 ・ナレズシは淡水魚を腐らせることなく保存する方法として開発され、メコン川流域から各地に伝搬した可能性が強い。現在の分布は東南アジア、台湾、日本、朝鮮半島北部だが、かつては中国にも存在していた。日本では15世紀頃から、1〜2週間漬け込んだだけで魚が生に近く、飯も一緒に食べることができる「生なれ」で食べるようになった。さらに、乳酸発酵の代わりに酢を加えるようになり、18世紀末からは生の魚を用いる握りずしが現れた。現在は、琵琶湖周辺の鮒ずし、和歌山のサンマのなれずし、岐阜のアユのなれずしが残っている。 ・北インドで米と野菜、豆、肉などを油でいためたプラオが、トルコのピラウ、ヨーロッパのピラフになり、イベリア半島にはアラブ人によって持ち込まれてパエーリャとなった。 ・青野菜をほとんど食べない民族は多く、野菜を何種類も畑で栽培するのは文明社会でのこと。 ・ヨーロッパで茶を飲む習慣が定着したのはイギリスとオランダで、両国の東インド会社が中国からの輸入を独占し、インドやスリランカ、ジャワでプランテーション経営を始めたため。 ・甘みはエネルギー源、酸味は代謝を促進する有機酸、塩味はミネラル、苦味は体に有害な物質、うま味はタンパク質やアミノ酸の存在を示す信号として働いている。出汁は、肉食をタブーとしてきた日本の食生活で、おいしく食べる方法として発達した。コンブのうま味成分はグルタミン酸、カツオブシはイノシン酸、シイタケはグアニル酸。東アジアの穀醤はグルタミン酸のうま味を持つと推定される。
Posted by 
食とは、保守的なもの。だから、地域と民族に守り続けられる。 主食という言葉が、世界共通のものでなく、 ヨーロッパには、主食がない。 パンは、食事を構成する食品の一つ。 スプーン、フォーク、ナイフを使うようになったのは、 17世紀くらいと言われる。 アジアでは、主食と副食がある。お...
食とは、保守的なもの。だから、地域と民族に守り続けられる。 主食という言葉が、世界共通のものでなく、 ヨーロッパには、主食がない。 パンは、食事を構成する食品の一つ。 スプーン、フォーク、ナイフを使うようになったのは、 17世紀くらいと言われる。 アジアでは、主食と副食がある。おもに、米が主食である。 箸と匙 中国ではレンゲ。 箸とスプーン 韓国。スプーンでご飯も食べる。 日本は、腕が発達したため、箸だけとなった。 インドから西は、調味されたご飯がたべられる。 中国は、火を使う料理が基本で、道具も少ない。 火を多様に使う。油脂をよく使う。高熱で料理する。 宋の時代に、コークスが、利用されるようになった。鉄鍋の普及。 日本の食が、仏教の普及により、肉食を禁じていた。 コメを主食として、オカズは、コメをたくさん食べるための促進剤だった という分析が、面白い。 調理をしないのが料理として優れている。そのことが、生食文化を生み出した。 そして、旨味を見出した日本の科学の進歩。 魚醤に、グルタミン酸ナトリウムが多いというのが、理解できる。 地球的な視点で、食を大づかみにつかむという作業は必要だね。
Posted by