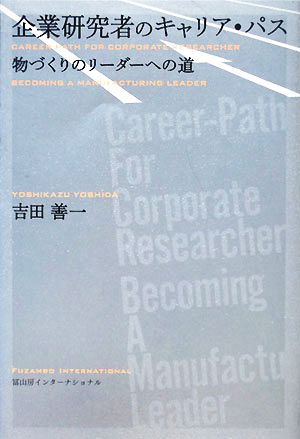
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-02-38
企業研究者のキャリア・パス 物づくりのリーダーへの道
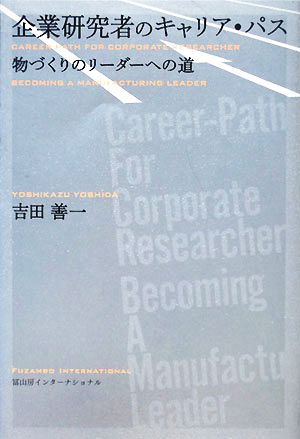
定価 ¥1,650
550円 定価より1,100円(66%)おトク
獲得ポイント5P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 冨山房インターナショナル |
| 発売年月日 | 2008/03/29 |
| JAN | 9784902385557 |
- 書籍
- 書籍
企業研究者のキャリア・パス
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
企業研究者のキャリア・パス
¥550
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
企業研究者のキャリア・パス ・独創力が求められる企業研究者は、原価意識や売れる物づくりといった経済合理主義で測定できるような工学だけではなく、数学や物理学といった理学的な素養が十分みについていないと、優れた成果を上げることはできない ・最初は、その分野に関しては研究所内のトップに...
企業研究者のキャリア・パス ・独創力が求められる企業研究者は、原価意識や売れる物づくりといった経済合理主義で測定できるような工学だけではなく、数学や物理学といった理学的な素養が十分みについていないと、優れた成果を上げることはできない ・最初は、その分野に関しては研究所内のトップになることを目指す。「何々に関しては彼に聞け」と言われるようになることである。次に、全社内でトップに、そして国内でトップに、最終的には世界でトップになることを目指して努力する ・研究者が最初に世の中に認められるのは、研究者自身ではなく、手がけた開発品の価値である。いくら一生懸命仕事をしても、自分のテクノロジーが日の目を見ないのでは、研究者としての存在価値はない ・開かれた大学の議論が進むなかで、企業研究者は従来タブーとされていた特定の企業の利益となる目的を絞った研究を、大学と共同で行える可能性が出てきている ・現場への説明によりフィードバックを得る際には、「こんな技術があります」ではなく、「こんな活用/応用が可能です」を示す ・「顧客満足」「お客様第一主義」が優先されるのは研究所も他の企業組織と同じ ・管理職を目指す研究者は、「常に余裕を持ち、周囲の人をうまく使う」ことが必要 ・装置の性能を1桁上げることを目標とすれば、飛躍的な発想、常識を破る構想が必要となる ・知行合一:行って行わざるは未だ知らざるなり。知と行は同等であり、行動がないと知識もなかったことになる ・今後、企業が研究開発で生き残るためには、社内での競合はもちろん、同業他者との競合もマイナスになるだろう ・企業研究者の心得 1.研究目標、自己実現目標を明確にする(1年、5年) 2.自分の設定した目標に対して、現状、他社動向、将来予測を徹底的に調べる 3.研究が企業利益に直接結びつく道を明らかにする 4.自分の目標と会社の企業の目標が一致することを確認したら、上司に説明して意見を求める 5.関連部門の仕事に少し入り込むぐらいの気持ちで仕事をする 6.研究目標の設定、現状分析、将来予測、協力者探しなどには人的ネットワークが威力を発揮するので、常にネットワークのメンテナンスを心がける 7.現場の意見はこちらから出向いて聞くようにする ・研究テーマヒアリングに臨む際のチェックリスト 1.何をしようとしているのか 2.その技術の現状はどうなっているのか 3.研究の独自性はどこにあって、なぜ成功すると思うのか 4.成功したら何ができるようになり、誰が喜ぶのか 5.お客様は誰で、どのような利益を受けるのか 6.リスクは何か 7.どれだけの時間とコストがかかるのか 8.中間的および最終的な評価方法をどのようにするか
Posted by 
期待して読んで、期待通り面白かった。 企業研究者は必読。企業研究者を目指す学生も必読。 まあ、ある程度ベテランの人にとっちゃあ当たり前のことばかりかもしれないが。 吉田 善一 1957年、兵庫県明石市に生まれる。筑波大学物理工学科卒業。京都大学電子工学教室研究員。松下電器産業(...
期待して読んで、期待通り面白かった。 企業研究者は必読。企業研究者を目指す学生も必読。 まあ、ある程度ベテランの人にとっちゃあ当たり前のことばかりかもしれないが。 吉田 善一 1957年、兵庫県明石市に生まれる。筑波大学物理工学科卒業。京都大学電子工学教室研究員。松下電器産業(株)を経て、1995年より、山梨大学機械システム工学科助教授。2000年より、東洋大学機械工学科教授。工学博士。専門は、プラズマ、レーザー、イオンビーム 退官講演かあ。 人物評価は入社1〜3年で決まる。 企業の基礎研究は「新規事業分野の創出」 日本の大学は評価は低いが、企業は一流。 ニーズの創出:自分たちのコンセプトを世の中に浸透させて行く 「The Squeaky wheel gets the grease」きしむ車輪は油を注してもらえる 企業に入ったらエリート意識は捨てる 「創造力」「活力」「気魄(きはく)」 電話魔 研究テーマの多くは境界領域から生まれる 最初の会議には上司に出席してもらう 「マイセレンディピティ(掘り出し物)」年2〜3テーマ 謙虚になれ、成果はアピール 議事録をとる癖をつける 事業部は技術情報に飢えており、真剣に聞いてくれる 外販、アメリカなら起業してしまう ふと思いついたことをどんどん特許に 科学者として生まれたからには、地球に爪痕くらい残したい 中堅になると、企業人間になってしまう。創造は企業人間からは生まれない。 知識を減らしてでも気迫が大事 学歴と研究能力は比例しない。むしろ反比例するくらい。 研究所で大事なのは「テーマ選定」「人材育成」「基本特許」 老いると評論家になってしまう。若い人も注意。 特許の失敗は調査不足が原因 頭が切れるフリをしていないか 特定の分野や学会にこだわっていないか 科学史に帰れ、を忘れていないか 日経サイエンス1992 8月号 IBMの研究者
Posted by 



