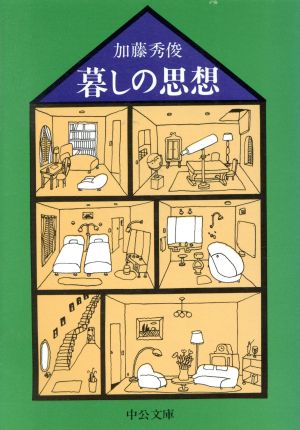
- 中古
- 書籍
- 文庫
暮しの思想 中公文庫
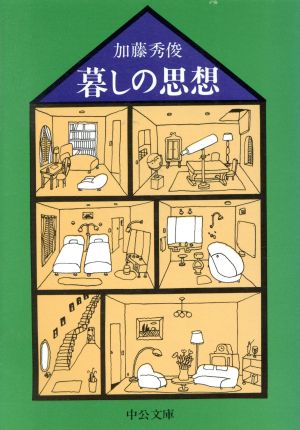
定価 ¥502
220円 定価より282円(56%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 1976/08/10 |
| JAN | 9784122003590 |
- 書籍
- 文庫
暮しの思想
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
暮しの思想
¥220
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
何度も読み返したい本。いまは、もっと読み返したい。読んで欲しい。 最近、シェアだのパブリックだのの本を読んでいたところ、本著の一番始めにある「趣味と人生」が思い出された。 リスペクトという言葉を思い出したからです。
Posted by 
40年を経て復刊、社会観察がおもしろい名著である。15本のエッセーが載っているが、主に英米圏と日本の比較であり、柳田民俗学から強く影響をうけている。「風呂」には温泉の話があるが、日本では娯楽にいくとはいいにくが、温泉にいって一旦、湯船につかれば、いろいろな娯楽が許されることを指摘...
40年を経て復刊、社会観察がおもしろい名著である。15本のエッセーが載っているが、主に英米圏と日本の比較であり、柳田民俗学から強く影響をうけている。「風呂」には温泉の話があるが、日本では娯楽にいくとはいいにくが、温泉にいって一旦、湯船につかれば、いろいろな娯楽が許されることを指摘している。宝塚歌劇団は宝塚温泉の娯楽として始まったらしい。温泉の流行には室町時代の「功徳風呂」などの寺社の温泉経営があったよう。「茶」では仕事中に「茶」を飲んでも許されることを指摘し(考えてみれば不思議)、茶は人間関係の結束に使われており、「茶の間」がその場所であったことをいう。「生活のなかの火」では、hibachiが英語になっていること、「面白い」が火を囲んで談笑をしているとき、顔が白くうつることから来た言葉であるという説があることを指摘している。「家具」では、西洋では家具は「動くもの」という意味があるが、日本の部屋はもともと何もないのが常態であり、いろいろなモノを吸いこんで成立しているとし、明治20年代くらいまではタタミも引っ越しでもっていくのが普通だったと指摘している。タタミは家具であった。「日記」では、藤原時代の私日記からはじめ、現代の私小説まで、日本における日記の流行を指摘していて面白い。「人とうつわ」では世の中を「いれもの」の連続であると面白い見方を披露し、西洋人は日本人とちがって「鏡」を恥ずかしがらずに見られる指摘している文も面白い。昔の女性は手鏡をふせてしまっておくしつけをうけたようだ。
Posted by 

