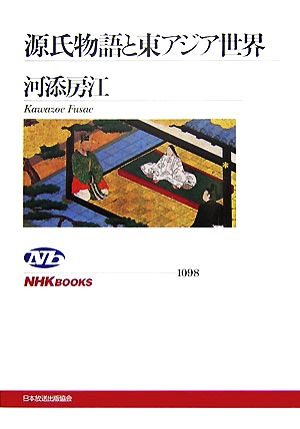
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1220-02-01
源氏物語と東アジア世界 NHKブックス1098
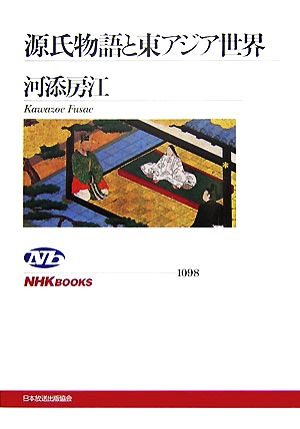
定価 ¥1,276
550円 定価より726円(56%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本放送出版協会 |
| 発売年月日 | 2007/11/28 |
| JAN | 9784140910986 |
- 書籍
- 書籍
源氏物語と東アジア世界
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
源氏物語と東アジア世界
¥550
在庫なし
商品レビュー
4.5
3件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2010年刊。表題は源氏物語云々だが、正確ではない。本書は源氏物語を素材に、国風文化が唐土や高麗等の東アジア文化の影響下にあったことを示しつつ、他方、近代日本が生み出した概念、つまり。遣唐使廃止が国風文化の発生の要因となったとの見解に一定の歯止めをかけようとするものである。高麗人の人相見だけでなく、源氏物語の文物に唐物・輸入物が描かれている(例えば、末摘花の羽織や、柏木が女三の宮を垣間見する時に登場する唐猫等。他にも多数)点、その由来が、遣唐使廃止後も残存した北宋等との東アジア交易にあった指摘は興味深い。 ある表現・描写(特に柏木と女三の宮、彼らを結ぶ唐猫は著名すぎる)でも、見方・解釈如何によって、全く別の意味を見出すことができる好例であり、その著者の着眼は素晴らしい。著者は東京学芸大学教授兼一橋大学大学院連携教授。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 「あなかしこ、このわたりに若紫やさぶらふ」と『紫式部日記』に記されて千年。 以来、日本固有の美意識の源流として称揚されてきた『源氏物語』だが、果たして、本当に和の文学の極致と言えるのか。 七歳で異国人である高麗人と出会い、その予言を起点に権力への道を歩みはじめた光源氏の物語を、東アジア世界からの“モノ・ヒト・情報”を手がかりに捉え直す。 『源氏物語』を古代東アジア世界に屹立するヒーローの物語として読み直す、気鋭の野心的試み。 [ 目次 ] いま、なぜ『源氏物語』と東アジア世界なのか 「いづれの御時にか」の時代設定 鴻臚館の光る君 異人・高麗人の予言 「光る君」伝承の起源へ 紫式部の対外意識 黄金と唐物 転位する唐物 表象としての唐物 唐物による六条院世界の再生 光源氏世界の終焉 光源氏没後の世界と唐物 「国風文化」の再検討 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by 
「源氏物語」に見られる人と物の交流を通して、作者や作者を取り巻く社会の価値観を見出そうとする。おもしろい。外来文化の緩やかな受容は、島には常に必要なものであったのだ。大陸の政治的変動にも敏感にならざるをえない、それが日本なのである。平安時代の国風文化を代表するといわれる作品だが、...
「源氏物語」に見られる人と物の交流を通して、作者や作者を取り巻く社会の価値観を見出そうとする。おもしろい。外来文化の緩やかな受容は、島には常に必要なものであったのだ。大陸の政治的変動にも敏感にならざるをえない、それが日本なのである。平安時代の国風文化を代表するといわれる作品だが、国風文化というカテゴライズはこれを読むと「作られたもの」で、どんどん揺らいでいく。
Posted by 



