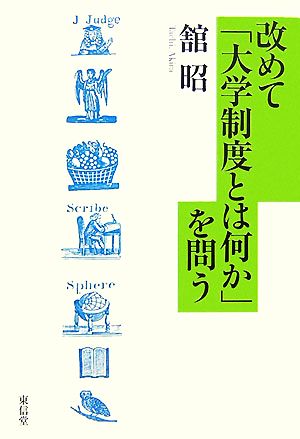
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1218-01-01
改めて「大学制度とは何か」を問う
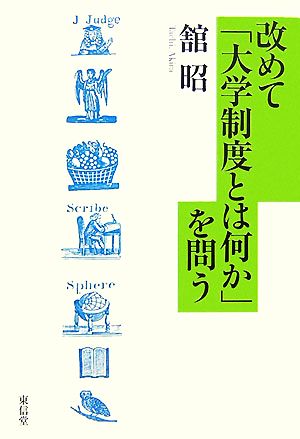
定価 ¥1,100
935円 定価より165円(15%)おトク
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東信堂/東信堂 |
| 発売年月日 | 2007/07/30 |
| JAN | 9784887137585 |
- 書籍
- 書籍
改めて「大学制度とは何か」を問う
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
改めて「大学制度とは何か」を問う
¥935
在庫なし
商品レビュー
4.3
4件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
大学改革が盛んだった2007年に購入。久し振りに読み直してみた。 ☐英語圏の「degree」は、日本では「学位」と訳されるが、両者の意義や機能には大きな隔たりがある。例えば、Merriam-Webster Dictionary によると、Degree は ”a title conferred on students by a college, university, or professional school on completion of a program of study” と定義しており、学習課程を修了したことにより授与される称号としている。しかし、日本の場合特に人文・社会科学系では課程修了と学位(博士)が結びつかず、博士=碩学泰斗のイメージが強い。この隔たりが、博士号とDoctoral Degree を違う意義のものにしている。しかしグローバルな評価においては、博士号はDoctoral Degree として評価され、日本の大学の教育研究環境や成果が低く評価される傾向をもたらしている。 ☐日本の大学では、大学と大学院を区別し対置してきたことも混乱の一因となっている。本来 Graduate School は紛れもなくUniversity の一部である。アメリカの大学では一連のカリキュラムをGraduate Level(卒後課程)とUndergraduate Level(卒前課程)で分けることができる。学生に提供されるプログラムは一連のもので、学士課程・修士課程・博士課程とレベルに応じて区分(一部供用)され、あくまでもそれを同一の教員団(Faculty)がDepartment毎に担当するのである。日本と違って、学部と大学院の課程は一連の体系的なカリキュラムのレベルによる区分に過ぎない。Graduate School(大学院)というものがあったとしても、それは卒後課程の統括組織で、共通の学生支援を主業務とするだけである。 ☐Credit制は、学生の学習量を証明するもので、これにより①履修科目の選択制や②他大学の単位互換や大学外での相当学習の認定なども可能となった。問題はこの正しい理解と運用がないこと。セメスター制度の場合1単位が(標準的な1週間の労働時間)45時間のWorkload を意味しており、この時間数の保障のためにCAP制(履修単位制限。計算上は学期15-18単位が上限となる)があるということ。さらに、講義科目であれば1時間につき原則2時間の予習復習を前提としており、予習復習指示のためにシラバスがある(日本ではシラバスと銘打っていても、内容はコースガイドの場合が殆ど)という理解である。自主学習が不徹底な日本の大学の単位数は、世界的にみても信用度が低い。そもそも、講義形式の場合、講義時間の2倍の準備によって、インターラクティブな授業が可能になるのだが、日本ではこのような自主学習が定着していないことが、教育の質という点での問題を生じている。
Posted by 
学位、大学院、教員組織、教育研究組織、単位制度、学生、認証評価制度についての解釈が詳しく解説されている。
Posted by 
2013.6.29再読記録 「大学改革実行プラン」の「改革集中実行期」の今、改めて『改めて「大学制度とは何か」を問う』を読んでみた。 学位、大学院、教員組織などなど、原点に立ち返るべき課題は多いが、喫緊の課題は単位制(舘先生のいう履修証明制)だと思う。 「一単位は学生が標準...
2013.6.29再読記録 「大学改革実行プラン」の「改革集中実行期」の今、改めて『改めて「大学制度とは何か」を問う』を読んでみた。 学位、大学院、教員組織などなど、原点に立ち返るべき課題は多いが、喫緊の課題は単位制(舘先生のいう履修証明制)だと思う。 「一単位は学生が標準的に一週間分の時間を費やして修得が可能な学習量(p71)」 改革の出発点はここだろうなぁ。
Posted by 



