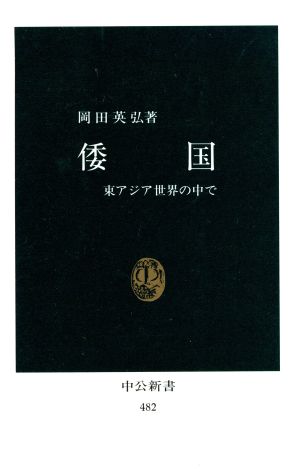
- 中古
- 書籍
- 新書
倭国
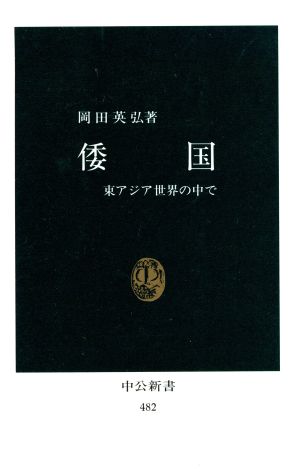
定価 ¥748
220円 定価より528円(70%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社/中央公論新社 |
| 発売年月日 | 1977/10/22 |
| JAN | 9784121004826 |
- 書籍
- 新書
倭国
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
倭国
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.8
6件のお客様レビュー
後漢末期の184年に農民の反乱である、黄巾の乱が起こる。そこに鬼道の起源があるという。政府軍に押さえ込まれた者達のなかから秘密結社をもつ農民が商人になったのかその華僑が倭国にもやって来たのだとのこと。卑弥呼の鬼道と同じでなかったとしても近いものを感じたので、味方となり力を貸したと...
後漢末期の184年に農民の反乱である、黄巾の乱が起こる。そこに鬼道の起源があるという。政府軍に押さえ込まれた者達のなかから秘密結社をもつ農民が商人になったのかその華僑が倭国にもやって来たのだとのこと。卑弥呼の鬼道と同じでなかったとしても近いものを感じたので、味方となり力を貸したとする。つまりそれまでの倭国の王は、後漢派であったわけだからということだろう。
Posted by 
著者は、歴史理論はヘロドトスによるヨーロッパ史と、司馬遷による中国史の二つしかないと見做す。 そして、その二つの異なる原理の止揚を目指す。 その止揚の成果として、ヨーロッパ史と中国史の結節点となるモンゴル帝国に着目、世界史の始まりをモンゴル帝国に求めたのが、著者の到達点だ。 本書...
著者は、歴史理論はヘロドトスによるヨーロッパ史と、司馬遷による中国史の二つしかないと見做す。 そして、その二つの異なる原理の止揚を目指す。 その止揚の成果として、ヨーロッパ史と中国史の結節点となるモンゴル帝国に着目、世界史の始まりをモンゴル帝国に求めたのが、著者の到達点だ。 本書は、その到達点に至る道程のなかて、倭国の位置付けに照準したものだ。 本書が書かれたのは1977年、二つの歴史観を止揚した「世界史の誕生」をものしたのが、1992年のことだ。 歴史観は、ヨーロッパ史と中国史しか存在しないと見做す著者にとって「日本史」などというものは存在しない。 では、日本はどのように捉えたらよいのか? 日本は中国の東、東アジアに属している。 当時、倭国と呼ばれた日本は、中国史、東アジア史の中で見ていかない限り、理解できない。 つまり、日本の歴史は中国史(東アジア史)の一部として捉えるべきだということだ。 日本に自国のアイデンティティ形成に力あった(強いた)のは、外圧だった。 戦争も含めた交易の中で、倭国の形成が、なされていったのだ。 中国に巨大帝国唐が生まれ、続いて三国が争い、そこに日本も地歩を築いていた朝鮮半島は、ライバル新羅によって統一される。 日本と言う意識、日本語という統一言語は、こうした中国史(東アジア史)のダイナミズムの渦中にあって、危機の意識が生み出したものだったのだ。 日本と言うアイデンティティを作り出す上で力あったのが「華僑」であったと言う指摘が、面白い。 日本における「華僑」とは、日本史の内なる中国史を生きる者のことだ。 そして、日本史は中国史の一部でしかないことを否応なしに思い知らせた者たちだ。 色々なルートから日本列島に渡ってきた複数の民族の中で、歴史を作ってきた国からの「華僑」が、日本の政治のリーダーとなり、中国史に倣った歴史を作ろうとしたのも頷ける。 日本が倭国と言われた時代を、中国史=東アジア史の中で、小さな事件の積み重ねによってかろうじて国が維持されていく奇跡=奇跡を描く。
Posted by 
和食を食べに料亭にいったのに、"シェフ"の本日のお薦めだからと「本場韓国の参鶏湯つき特製中華Aコース」を出されたような気分にさせられる本。 あるいは、本日の日替わり和食Bランチですと言って出された料理をみたら、つやつやコシヒカリが塩辛いビビンバの具で埋もれ、お...
和食を食べに料亭にいったのに、"シェフ"の本日のお薦めだからと「本場韓国の参鶏湯つき特製中華Aコース」を出されたような気分にさせられる本。 あるいは、本日の日替わり和食Bランチですと言って出された料理をみたら、つやつやコシヒカリが塩辛いビビンバの具で埋もれ、お香々かと思ったらこれまた塩っぱいザーサイで、旬の野菜の煮物は鷹の爪で真っ赤に煮込まれ、お吸い物の蓋を開けたらサンラータンだった、というような気分にさせられる本。 (我ながら秀逸な比喩だと思う) とにかく、頁を捲っても捲っても倭国が出なくて、三国志と朝鮮半島史が延々続く。そして後半入ってしばらくしてやっと日本人が出て来たかと思ったらすでに誰でも知っている天皇の名前が並ぶ。たとえるなら、唯一の日本料理だと思えたものがカレーライスで和食とは言い難い、というような気分。料理自体は不味くはないが、和食の口で店に入って中華と韓国料理を食わされるのだから、心のモヤモヤが半端ない。 それとp.10に、「江」と「竜」が古くは同じ発音だったみたいなことが書いてあるが、上古音をネットで調べた限りでは全く似てすらいない。上古音までいかなくても、普通話でjiangとlong、到底同じ発音の派生系とは考えられない。 ----- 『古事記』は『日本書紀』をもとに創作されたというのは有名な話。『日本書紀』では日本が初めから統一国家だったという筋書きだが、そんなこと信じる人はまづいない。東日本はいまのアイヌの人たちの祖先が居住する地で、その分布範囲は越国から福島の線くらいまでに及んだと何かで読んだことがある。九州は隼人と呼ばれた人たちが生活していた。 中国の文献などをみていくと、初めは河内のあたりに存在した局地的な氏族国家にすぎず、『日本書紀』が編纂された継体天皇の時代においても、継体天皇の出身地である敦賀 (福井県) ですら大和系以外の部族氏族がゴロゴロいたらしい。なんなら大和といわれる氏族ももとは大和にはいなかったとか。 中国の国内の混乱などで前線の位置は前後したものの、漢の時代頃から朝鮮半島が中国の一部となりはじめ、中国内地から朝鮮半島に移り住んだ人が現地人化し、その人たちがやがて海を渡って日本にやってきた。中国人はやはりいつの時代も中国人で、商魂たくましいというか、都市的というか。日本列島に来ると、中国からの物資を朝鮮経由で日本に流し、日本からは資源や特産を中国に流す、それによって儲けを出していたらしい。中国が安泰なら、朝鮮が安泰なら、即ち日本の発展も安泰。そんな中で起きたのが白村江の戦いであり、それに負けた日本は中国・朝鮮からの支援を得られなくなったことで、発展への道が閉ざされてしまった。 このままでは国家は滅亡へ向かってしまう。そこで焦った大和人は、日本を諸部族や諸民族の集合体ではなく、国家として再構築し、国際情勢に対応できるようにした。そこで腕をふるったのはやはり朝鮮経由で入ってきた華僑であり、その華僑のもとで「日本語」も再構築されたという。文法は韓国語などと同じながら語彙は全く似ていない日本語、それを創り出したのは日本にのこった華僑で、華僑は中国語の語彙を現地の言葉に当てはめていったために、語彙的には韓国語とは完全に離別してしまった。現存する和歌の中で詠人を特定できる最古のものを漁ってみると、その大半は帰化人、つまり渡来人らしく、それがまさに日本語の「生みの親」が誰であるかを語っているのだとか。 この日本語誕生秘話については確かに刺激的でおもしろかったが、信じたい信じたくないは置いておいて、断定するにはまだ早いかなとも思う。 というわけで、最後の数ページと最初の数ページ以外は、完全に期待した和食ではなかったが、結局のところ、和食も実は華僑が作ったっていうオチなのか。お後がよろしいようで。
Posted by 



