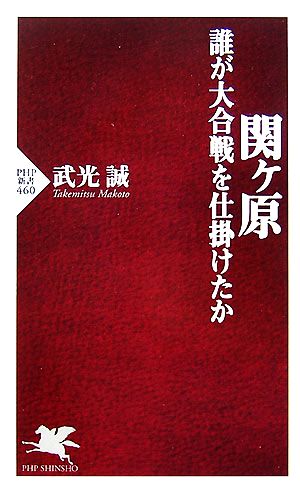
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-26-01
関ヶ原 誰が大合戦を仕掛けたか PHP新書
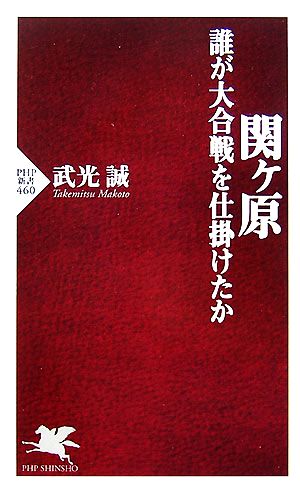
定価 ¥770
110円 定価より660円(85%)おトク
獲得ポイント1P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | PHP研究所/PHP研究所 |
| 発売年月日 | 2007/05/30 |
| JAN | 9784569659381 |
- 書籍
- 新書
関ヶ原
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
関ヶ原
¥110
在庫なし
商品レビュー
2.3
7件のお客様レビュー
日本の戦国時代において、敵味方に分かれてガップリ四つで組んだ最後の戦いであると私が思っている有名な、関ヶ原の合戦は、とても興味があり、今まで多くの本を読んできました。 関ヶ原の合戦を解説したもの、それを題材にした物語、どれもこれも楽しい読書タイムを過ごせたのを覚えています。 ...
日本の戦国時代において、敵味方に分かれてガップリ四つで組んだ最後の戦いであると私が思っている有名な、関ヶ原の合戦は、とても興味があり、今まで多くの本を読んできました。 関ヶ原の合戦を解説したもの、それを題材にした物語、どれもこれも楽しい読書タイムを過ごせたのを覚えています。 私の個人的な印象かもしれませんが、この5年間位にかけて、いままで定説とされてきた常識(私が高校の日本史の授業でならったもの)と比べてかなり変わってきたことを感じます。 この本の特徴は、関ヶ原の合戦に参加した大名の一人ひとりについて、関ヶ原の合戦に参加するにあたり、どのような状況にあったのかを解説しています。私が嬉しかったのは、小早川秀秋の裏切りに呼応した4武将(赤座、小川、朽木、脇坂)が小早川氏に追随することになった理由が私なりに理解できたことです。 今後も、私が「あれ?」と思っていたことが徐々に明らかになっていくことを願っています。 以下は気になったポイントです。 ・合戦が起きた旧暦9月15日は新暦換算で10月21日、合戦をしかけた人物を理解するには、1)豊臣から徳川政権にいたるまでの経済の在り方、2)主要人物の立場を知ること、がポイント(p17) ・秀吉のとった重要な政策として、1)検地、2)刀狩、3)海賊取締り令、があるが、前者2つは、荘園制のもとで活躍した、地主・荘官などの小領主、そしてその下の地侍層を否定するもの(p35) ・家康は藤原惺窩の弟子である林羅山を御用学者にして、日本化した朱子学を幕府の官学とした(p100) ・光秀と深い関わりのもつ人物として、小早川秀秋の筆頭家老である、稲葉正成と、大名:脇坂安治である、脇坂は光秀の近臣で後に秀吉に仕えた。朽木と小川も光秀の部下(p110) ・慶長の役で総大将の小早川秀秋は、稲葉正成のすすめで加藤・浅野軍を助けたが、これを石田三成は勝手にプサンを離れたことを責めた結果、領地を削られて12万石になったので石田三成に恨みを持った(p129) ・吉川広家も、蔚山の戦いで手柄を立てたが、恵瓊が抜け駆けしたとして、非難して三成が同調した。これに毛利家が同調したので、毛利家と吉川家は疎遠になった、このときに取り成したのは家康(p135) ・小早川秀秋の裏切り直後に、東軍に走って、西軍の平塚為広らの部隊を壊滅させた、脇坂は、西軍崩壊のきっかけをつくった(p136) ・家康が合戦まで、加増に用いた領地はいずれも、豊臣家の直轄領、秀吉が晩年に行った露骨な拡大策に反発するものが多かったので、これを受け入れる者も多かった。特に中小大名は期待の目を持った(p149) ・家康は農村にまで都市の豊かな暮らしを広めていくために、租税を七公三民から、四公六民にした。さらに村三役(庄屋、組頭、百姓代)からなる村役人の手による農村自治を重んじた(p194) ・関ヶ原の合戦は、1)上杉景勝、2)毛利輝元、の二つの反徳川の行動によって起きた(p198) 2015年7月12日作成
Posted by 
豊臣政権は格差社会だった。庶民と新富裕層、安定と発展交錯する思惑を読み解く。2007年の刊。 序 章 関ヶ原合戦の意義 第一章 豊臣政権の行き詰まり 第二章 西軍の大名の立場 第三章 東軍の大名の立場 第四章 迷える大名の立場 第五章 関ヶ原へのみち ...
豊臣政権は格差社会だった。庶民と新富裕層、安定と発展交錯する思惑を読み解く。2007年の刊。 序 章 関ヶ原合戦の意義 第一章 豊臣政権の行き詰まり 第二章 西軍の大名の立場 第三章 東軍の大名の立場 第四章 迷える大名の立場 第五章 関ヶ原へのみち 第六章 関ヶ原の勝敗の分かれ目 終 章 新たな時代の訪れ 長らく積ん読状態だった本。いまどき珍しく、巻末にも文中にも参考文献というものが載っていない。新書とはいえ歴史分野の本としては如何なものか。史料の引用も明記されていないのには驚く。なぜそうなるのか根拠不明の論理展開にはついていけない。 著者の石田三成の評価は著しく低い。まるで江戸時代のようである。 p15家康よりはるかに小粒な人物で、秀吉に気に入られた能吏、一国の政治を考える政治家ではない。重要な戦いの指揮官をつとめた経験も無い。 p55三成は政治家でも、経済通でもない、ただの能吏である。 p63三成は小田原遠征にあたって、館林城と忍城攻めを命ぜられた。ところが、三成は二つの城攻めを続けざまに失敗したのだ。 p64三成は諸大名に嫌われ、孤立したなかで、関ヶ原を迎えることになる。 等々、著しく偏った見方をしている。 豊臣秀吉及び秀吉政権についても、見方が偏っている。 p19秀吉は、一部の上流武士や豪商だけの利益を図る政策をとり無意味な朝鮮出兵をおこなった。そのため、政権の末期に日本は、再び戦国時代のような動乱の世に戻る危機を迎えていた。 p40七公三民の重税 p42秀吉は暴挙と呼ぶべき、理由なき大名追放をくり返した。 p45秀吉は、国の将来を考える長期的な視野から政策を立案する人間ではなかった。秀吉の政策の多くは、織田政権の方向をうけついだものにすぎない。 p45この時代の民衆の生活を向上させるための新たな経済政策が考え出されたとは言い難い。 p46晩年の秀吉は、国政を能吏に委ねて贅沢三昧の日々を楽しんでいた。 その他にも、疑問な点や誤字等が多々ある。 p38質素な衣服をつけた者は、大名や豪商のあつまりの場で軽蔑された。 p50毛利家と上杉家は、互いに連絡なしに勝手な動きをとった。 p59三成は、蒲生真令や、蒲生氏郷を高録で招いた(誤字か) p67毛利輝元は12歳で元就の養子となった p73家康と気が合わない上杉景勝は、会津に帰国した p94家康は正直で愚直な武士 p102桶狭間で討たれなければ、義元は近いうちに京都を征服していた p116福島正則は、家康が嫌いであった p139(西軍大名の心情として)家康は国内を安定させて庶民を富ませる新たな秩序をつくろうとしている。この秩序をつくるためには、大名たちは内政のわずらわしいことにあたらねばならず、日常生活でも、質素を求められ、あれこれの我慢を強いられる。 p145(秀吉死後)糾問使の事件によって、利家の評判は地に堕ちた。 p150直江兼続は会津政権を作ろうとした。 疑問な点 七公三民の重税とあるが、秀吉政権だけの問題なのだろうか。 家康は民衆の生活を向上させるための新たな経済政策を行ったのだろうか。 そもそも、この当時、為政者たちに、そのような意識があったのだろうか。 本書は、小説に近い内容としか思えない。 山本博文氏は、著書のなかで「学問というものは、検証する必要があるから、出所を明示されてないと、いくら史料に書かれていることでも、その史料そのものの検討が出来ないから史実とは認定できない。これは実に残念なところである。」と言っている。これは実にもっともな事である。
Posted by 
近代以前の歴史については、いわゆる歴史物という読み物以外の資料が少ないことが多いと聞く。本書の関が原も後世の読み物によるものが多く。同時代の原資料は少ないのだろう。しかし、一冊の本として上梓した以上はそれなりの説得力のある資料や論考を示さなければ、歴史を語るべきではないと思うが...
近代以前の歴史については、いわゆる歴史物という読み物以外の資料が少ないことが多いと聞く。本書の関が原も後世の読み物によるものが多く。同時代の原資料は少ないのだろう。しかし、一冊の本として上梓した以上はそれなりの説得力のある資料や論考を示さなければ、歴史を語るべきではないと思うが、本書はその点で不十分ではないかと感じた。 本書では「豊臣秀吉の政治は苛性であった」と決め付け、「関が原決戦で徳川家康が敗れていたら、支配層は庶民を踏みつけて贅沢をむさぼり続けていただろう」と結論付ける。十分な資料も豊富な論証もなくして結論のみを突然だされても、読者としては、戸惑うのみである。 本書は、まともな歴史書としてはあまり価値を見出せないと思った。せっかく新書として上梓したのであるから、もう少しきちんと資料を調べて欲しかった。
Posted by 



