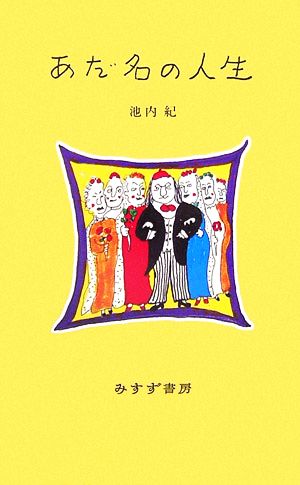
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1220-04-00
あだ名の人生
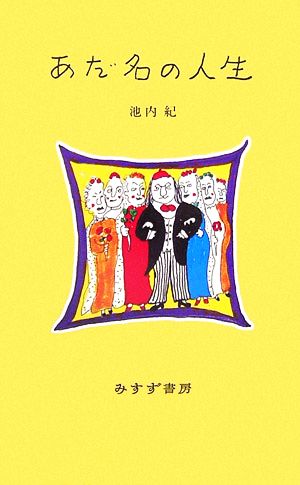
定価 ¥2,860
770円 定価より2,090円(73%)おトク
獲得ポイント7P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | みすず書房/みすず書房 |
| 発売年月日 | 2006/12/04 |
| JAN | 9784622072690 |
- 書籍
- 書籍
あだ名の人生
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
あだ名の人生
¥770
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3
2件のお客様レビュー
面白いあだ名をつけられた有名人を紹介していく一冊かと思ったら、全くの間違えでした。有名人からあまり知られていないけど、内容を追っていくとその人の残した業績はすごく有名!という人々へつけられたあだ名、通称、呼び名。有名無名24人の人生は、やはり凡人とは一味違うのね、という印象でした...
面白いあだ名をつけられた有名人を紹介していく一冊かと思ったら、全くの間違えでした。有名人からあまり知られていないけど、内容を追っていくとその人の残した業績はすごく有名!という人々へつけられたあだ名、通称、呼び名。有名無名24人の人生は、やはり凡人とは一味違うのね、という印象でした。
Posted by 
昨日、めずらしく本を返したら、予約本もきてなかったのでカードに空きができ、しばらく図書館をうろつく。奥の棚にいろいろ面陳されてる本の中から、『あだ名の人生』をとってみた。ぱらぱらっと中をみると、巻末の広告ページに「大人の本棚」の本が並んでいて、あ、これは「大人の本棚」の一冊かと思...
昨日、めずらしく本を返したら、予約本もきてなかったのでカードに空きができ、しばらく図書館をうろつく。奥の棚にいろいろ面陳されてる本の中から、『あだ名の人生』をとってみた。ぱらぱらっと中をみると、巻末の広告ページに「大人の本棚」の本が並んでいて、あ、これは「大人の本棚」の一冊かと思って借りてきてみた。 「大人の本棚」には、吉屋信子の『私の見た人』や『父の果/未知の月日』が入ってるのをチェックしているが、未読。いつだったか途中まで読んで返却期限がきてしまった野呂邦暢の『夕暮の緑の光』もこのシリーズ。 巻頭の「たばこ和尚」があまりのらなくて、うしろのほうをぴらぴらっと読んでみたら、「最後の文士」高見順がどうのこうのが出てきて、高見順はどっちかというと小説家かアと、いまさらとんまなことを思う(私のなかでは高見順は『死の淵より』の印象が強烈すぎて、詩人というハコに入っている)。 その後ろ、「大いなる野次馬」大宅壮一の頁を読んで、へぇ「クチコミ」というのは大宅の造った新語なのかと知り、そこが本の最後で、このあだ名列伝を前へ前へとさかのぼって読む。「あだ名、通称、身代わりのようにしてつけられた呼び名」を切り口に、無名も有名もとりまぜて24人の肖像が書かれている。 「狂歌師鶴彦」とよばれた大倉喜八郎は、あまたあるオークラの元祖のような人である。関西なら、関西大倉(通称カンクラ)とか。 ▼日本最初の私立美術館「大倉集古館」の公開にあたり、「集古館規定」を歌で伝えた。 品物に さはるべからず タバコをも 喫(の)むことなかれ 心ある人 (p.132) 「さはるべからず」かあ、と思って読む。広瀬さんの『触る門には…』を読んだ身には、「見る」を主とした美術館の今にいたる源流のように思える。 「妖怪博士」とよばれた井上円了は、東洋大学の祖となる哲学館をつくった人。 ▼井上円了には教壇の教師だけではもの足りなかったようで、四十代の半ばになって哲学館は人にゆだね、当時、江古田とよばれていた東京の郊外に土地を買った。(p.112) 「当時、江古田と」とは、今の江古田とは違うところなのか?(江古田も「えこだ」とよぶ地と、「えごた」とよぶ地があるそうだというのは、『江古田ちゃん』で知った話) 「ランプ亡国論」を説いてまわり、それが代名詞となった佐田介石には「栽培経済論」がある。その栽培のゆえんとは「富は栽(ウ)エザレバ育タズ、培(バイ)セザレバ繁(シゲ)ラズ」(p.93)のテーゼをふまえてのことという。 ▼では「経済」とは何か。 「四方ノ人民ノ間(アイ)ダニ金貨物品を滞リナク往来セシメ、融通ノ道ヲ開クコト」なり。(p.93、途中の「を」はヲの誤りのような気もするが、本文での引用がこうなっている) 「噺の元祖」、または「落語の元祖」「中興の祖」といわれたのは、中村英祝(ひでのり)で元は大工の棟梁、通り名は和泉屋和助。 ▼おりしも四十歳。江戸の人には「初老」であって、身を引くのにふさわしい齢ごろとされていた。やがて和泉屋和助に代わって、烏亭焉馬(うていえんば)の名があらわれる。(p.48) 同居人の里に「初老」という風習があり、私の知らないものだったが、江戸でも「初老」!当時は隠居の年頃だったのかと思って読む。 読みはじめると、どれも、小さな地域史だったり、小さな芸能史だったり、なかなかにおもしろいのだった。表紙も挿画も、著者の池内紀の手になる小さな絵で、これがまた味がある。 そして、読み終わってよくよく本をあらためると、どうもこれは「大人の本棚」シリーズではないのだった。まあ、それはいい。おもしろかった。
Posted by 



