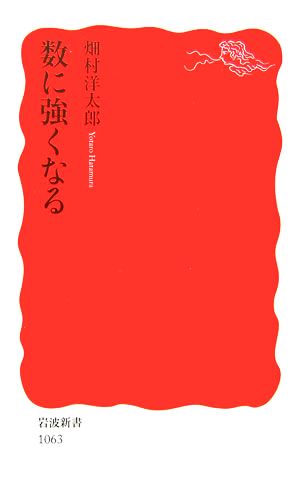
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-24-03
数に強くなる 岩波新書
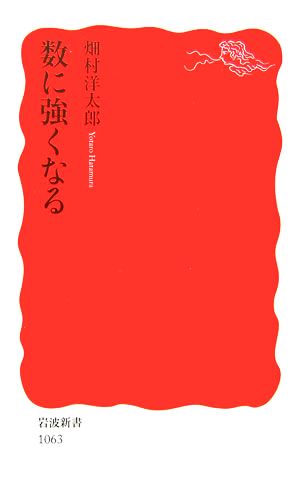
定価 ¥836
110円 定価より726円(86%)おトク
獲得ポイント1P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/25(火)~3/2(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店/岩波書店 |
| 発売年月日 | 2007/02/22 |
| JAN | 9784004310631 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/25(火)~3/2(日)
- 書籍
- 新書
数に強くなる
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
数に強くなる
¥110
在庫あり
商品レビュー
3.6
71件のお客様レビュー
タイトルの「数」は「かず」と読む。「すう」や「数字」とは考え方が異なると筆者は定義している。本書では数式めいたものはなく、全体像を数で把握する考え方を説いている。 細かな数字にとらわれるのではなく、物事の本質を理解して考えようという啓蒙的な内容を、筆者の経験や生活の中のエピソー...
タイトルの「数」は「かず」と読む。「すう」や「数字」とは考え方が異なると筆者は定義している。本書では数式めいたものはなく、全体像を数で把握する考え方を説いている。 細かな数字にとらわれるのではなく、物事の本質を理解して考えようという啓蒙的な内容を、筆者の経験や生活の中のエピソードなども交えて分かりやすく解説している。 しかしジェンダー論的な観点や使用ツールなどの話題にいささか古さを感じた。2007年に書かれた本で筆者は1941年生まれと後追いで確認して、妙に納得してしまった。
Posted by 
836 畑村 洋太郎 1941年東京生まれ。東京大学工学部機械工学科修士課程修了。東京大学大学院工学系研究科教授、工学院大学グローバルエンジニアリング学部特別専任教授 を歴任。東京大学名誉教授。工学博士。専門は失敗学、創造的設計論、知能化加工学、ナノ・マイクロ加工学。2001年...
836 畑村 洋太郎 1941年東京生まれ。東京大学工学部機械工学科修士課程修了。東京大学大学院工学系研究科教授、工学院大学グローバルエンジニアリング学部特別専任教授 を歴任。東京大学名誉教授。工学博士。専門は失敗学、創造的設計論、知能化加工学、ナノ・マイクロ加工学。2001年より畑村創造工学研究所を主 宰。’02年にNPO法人「失敗学会」を、’07年に「危険学プロジェクト」を立ち上げる 筆者の考えはこうである。「もう数なんて見るのもイヤ!」と 人がなるのは、「数は厳密なものだ」「数は正しくなくてはいけ ない」と思い込まされるからである。これが、人が数ギライにな る、最大にして根源的な理由である。こういう思い込みが人を圧 迫し、強迫観念にも近い恐れを抱かせるのである。 文科系の人は、情緒が必要ないところまで情緒でやろ うとすることがあるので困る。数は理科系の人間だけの専売特 許で、数学が得意な人だけが考えていればいいもの、白分には 関係ないものと思い込んでいる。しかし、そうではないのであ る。ただし、理科系の人もよく自分のことを顧みた方がいい。 理科系というところは、数や構造にばかり関心があって、情緒 は煩わしくて考えたくないという人間が逃げ込んでいる駆け込 み寺である。情緒で行かなくてはいけないことも、時にはある のである。 しかし、「全体の傾向を見る」ということは、とてもよくやっ ている。そして、この「全体の傾向を見る」という動作には、本 人が意識しているかしていないかは別にして、じつは微分的な発 想が含まれているのである。 一方、「全体の量がどのくらいになるか」ということもよく見 ている。こういう動作は、じつは積分的な概念である。横軸に時 間をとって、トータルでお金はどれだけ貯まっていくか、という 発想は積分そのものである。 欧来の人たちは、数をかぞ えるときには「千(tousand)」を基準にしている。たとえば、105000という数を見たときには、「千が105個ある数だ」と認識する。そこ で、数を表記するときは、千ごと(3ケタごと)にカンマで区切って、105,000と書く習慣になっている。 「自己評価は2割増しの法則」というものがある。これは別の言い方をすると、「他 人の評価は正しい」ということである。 たとえば、勤続年数が大体20年を過ぎた会社員で考えてみよう。このくらいの中堅 社員になると、経験をたくさん積み、自信も付いて、「俺は会社にとって大事な仕事 をしているぞ」と思うようになるものである。
Posted by 
「数に強くなりたい」、多くの社会人が身につけたいと思うスキルの1つだと思います。要は訓練なんだと思います。日頃から、自分の頭で色んな数をこねくり回すことが大切であると本書では述べられています。かなり脳に負荷のかかる、しんどい作業ですが、結局自分の頭で考えないかぎり、数に強くなりま...
「数に強くなりたい」、多くの社会人が身につけたいと思うスキルの1つだと思います。要は訓練なんだと思います。日頃から、自分の頭で色んな数をこねくり回すことが大切であると本書では述べられています。かなり脳に負荷のかかる、しんどい作業ですが、結局自分の頭で考えないかぎり、数に強くなりませんし、思考力は身につかないんだと思います。最近流行りのロジカルシンキング本を何冊読んだところで、わかった気になるだけで、論理的思考力は身につかないんですよね。ということで、脳みそに汗をかきましょう!
Posted by 


