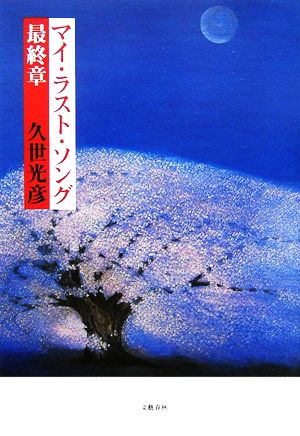
- 中古
- 書籍
- 書籍
マイ・ラスト・ソング 最終章
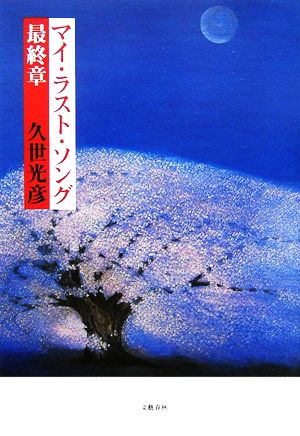
定価 ¥1,980
990円 定価より990円(50%)おトク
獲得ポイント9P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋/文藝春秋 |
| 発売年月日 | 2006/08/05 |
| JAN | 9784163683508 |
- 書籍
- 書籍
マイ・ラスト・ソング 最終章
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
マイ・ラスト・ソング 最終章
¥990
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」などのテレビプロデューサーであり、また作家、エッセイストであった久世光彦(くぜてるひこ)氏の「マイ・ラスト・ソング 最終章」(2006.8)を再読しました。野坂昭如氏の「黒の舟唄」を聴いて、嫌な歌だと眉をひそめながら、なぜか胸に引っ掛かる。鈍い痛み...
「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」などのテレビプロデューサーであり、また作家、エッセイストであった久世光彦(くぜてるひこ)氏の「マイ・ラスト・ソング 最終章」(2006.8)を再読しました。野坂昭如氏の「黒の舟唄」を聴いて、嫌な歌だと眉をひそめながら、なぜか胸に引っ掛かる。鈍い痛み、深爪の痛みのようなもの。もう一度聴いてみる。野坂さんの暴力的な荒々しい呼吸音と信じられないくらいに優しい含羞(はじらい)が!<♪お前が十七おれ十九 忘れもしないこの河に ふたりの星のひとかけら ながして泣いた夜もある♪> 2006年3月2日、虚血性心不全、70歳で亡くなった久世光彦(くぜ てるひこ)氏「マイ・ラスト・ソング」、2006.8発行。近江俊郎の「黒いパイプ」(昭和21年)、昭和15年の「隣組」、北原白秋の「雨」、野坂昭如の「黒の舟歌」・・・、いい歌がいっぱい詰まった本です。~たとえば男はあほう鳥 たとえば女はわすれ貝~♪ ~雨が降ります 雨が降る~♪ ~君にもらったこのパイプ 昼の休みに窓辺によれば~♪
Posted by 
1992年「諸君!」4月号から連載が始まった「マイ・ラスト・ソング」は、2006年に亡くなるまでの14年間続いた久世光彦の長期連載シリーズである。 今回の「最終章」が出るまでには、「マイ・ラスト・ソング」、「みんな夢の中」、「月がとっても青いから」、「ダニー・ボーイ」と都合4冊が...
1992年「諸君!」4月号から連載が始まった「マイ・ラスト・ソング」は、2006年に亡くなるまでの14年間続いた久世光彦の長期連載シリーズである。 今回の「最終章」が出るまでには、「マイ・ラスト・ソング」、「みんな夢の中」、「月がとっても青いから」、「ダニー・ボーイ」と都合4冊が出版されており、これが5冊目の「マイ・ラスト・ソング」である。 「末期の刻(とき)に聴く歌を選ぶとすれば、どんな曲を選ぶだろう」という座興のような発想から生まれたシリーズではあったが、歌謡曲フリークの久世光彦にとっては、まことにふさわしいシリーズだったようで、これほど長期に渉る人気シリーズになったのである。 そしてこれだけの分量にまとまると、時代を捉えた見事な昭和史ともなっている。 「この連載が終わるのは、雑誌が廃刊になるときか俺が死ぬときだな」の言葉通り、2006年の死によって連載は終了したが、童謡や唱歌、洋楽から歌謡曲までの100を越える曲が選ばれている。 その一曲一曲に深い思い入れがこめられており、まるで上質の短編小説を読むような味わいがある。 またそれは時には単なる曲選びというだけではなく、あの時のあの人が歌った歌というような限定されたものも登場する。 たとえばそれは次のようなもの。 秋なら、四谷シモンである。そして四谷シモンなら「影を慕いて」である。 たった一度しか聴いたことがないのだが、この人の「影を慕いて」は絶品だった。凄絶というか、妖異というか、あるいは静かな狂乱というか、とにかく聴いているうちに死にたくなるのである。まだカラオケがいまほど盛んではない頃の話で、小さな地下のクラブでシモンはギター一本の伴奏で歌いはじめたのだが、それまでザワザワしていた店内が、誰がどう制したわけでもないのに、いつの間にか静まりかえって、見るとシモンが蒼い頬に薄ら笑いを浮かべて歌っていた。怖いくらいにいい歌というものは、いつもどこか投げやりなところがあるものだ。私は、シモンがあの世を覗いて帰ってきたのかと思った。 昔状況劇場の芝居で、四谷シモンの歌を聴いたことがある。 この文章を読みながら、その時の情景が目に浮かんできた。 そして「死にたいと思った」久世光彦の気持ちに、痛いほどの共感をおぼえた。 さらに次のようなものもある。 他の歌を歌わなかったわけではなかったが、上村一夫と言えば「港が見える丘」だった。この歌を歌うために飲みに行くのではないかと思うくらい歌いたがったし、みんなも聴きたがった。ギターのコードは間違いだらけだったけど、この歌だけは他人の伴奏を嫌がって自分で弾いたし、またそれが絵になっていた。弾き語りというのはこういうことなんだと、私は上村の「港が見える丘」を聴くたびに思ったものである。思い入れ十分に泣くのではない。まるで秘かな猥歌のように、ヘラヘラ笑いながら唄うのである。それは、戦後のあのころならどの町にもあった汚いドブ川の水が、品のないネオンの色を映してゆっくり流れて行くような「港が見える丘」だった。 こういう文章を読んでいると、けっして聴くことはできないその歌を、無性に聴いてみたい衝動に駆られる。 そして歌というものは、そのシチュエーションによって、さまざまな色彩を帯びるものなのだということを、あらためて思うのである。 久世光彦はこうした歌を聴きながらさめざめと涙を流す。 というよりも泣きたいために歌を聴くのではと思わせるほど、その感傷に溺れようとする。 そしてその感傷の波が、読んでいるこちら側の記憶を刺激して、ともに感傷に耽ることになる。 それはとても心地いい読書体験である。 いつまでもその感傷に浸っていたいと思わせる。 最初に単行本化されて以来、このシリーズを読み続けてきたが、これで終わりとなると親しい友人を失ったような寂しさがある。 そのひとつひとつを噛み締めながら読んだ。 そしてこのシリーズを読むときには必ず思うことだが、自分にとっての「マイ・ラスト・ソング」とはいったいどんな曲だろうということを、またあらためて考えてしまうのである。
Posted by 



