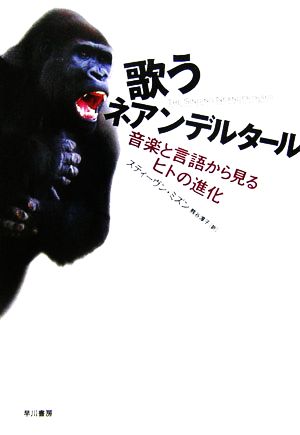
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-03-02
歌うネアンデルタール 音楽と言語から見るヒトの進化
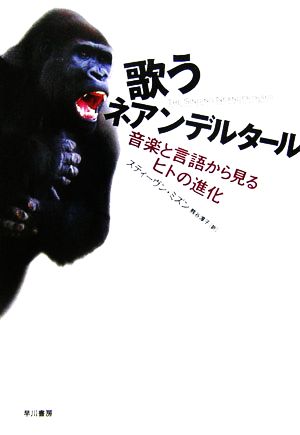
定価 ¥2,640
2,475円 定価より165円(6%)おトク
獲得ポイント22P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 早川書房/早川書房 |
| 発売年月日 | 2006/06/24 |
| JAN | 9784152087393 |
- 書籍
- 書籍
歌うネアンデルタール
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
歌うネアンデルタール
¥2,475
在庫なし
商品レビュー
3.7
9件のお客様レビュー
「クラシック音楽の歴史」で引用されていて、ヒトの進化に興味をもっているため読書開始。 音楽が、言語に先立って生まれたこと、それは現生人類のホモ・サピエンスより前の時代に生きたネアンデルタール人の時代から存在していたこと、赤ちゃんの言語獲得のプロセスがその進化の過程と符合することな...
「クラシック音楽の歴史」で引用されていて、ヒトの進化に興味をもっているため読書開始。 音楽が、言語に先立って生まれたこと、それは現生人類のホモ・サピエンスより前の時代に生きたネアンデルタール人の時代から存在していたこと、赤ちゃんの言語獲得のプロセスがその進化の過程と符合することなど、とても興味深かった 私達が音楽を愛すること、心地よく思うこと、音色・リズム・トーンによって喜怒哀楽を感じることは遺伝子レベルでプログラムされているのでは無いか。とても知的好奇心をそそられる内容だった。
Posted by 
音楽によって自分の感情を表現したり、他者の感情や行動を操作することができる。音楽と言語は、どちらも発声、動作、筆記によって表現でき、身振りや体の動きがある。しかし、言語の情報伝達は構成的で、音楽の意味は全体的である。また、言語は指示的でも操作的でもあるが、音楽は感情を誘導する操作...
音楽によって自分の感情を表現したり、他者の感情や行動を操作することができる。音楽と言語は、どちらも発声、動作、筆記によって表現でき、身振りや体の動きがある。しかし、言語の情報伝達は構成的で、音楽の意味は全体的である。また、言語は指示的でも操作的でもあるが、音楽は感情を誘導する操作的なものである。 著者は、音楽が言語進化の副産物と考えることも、音楽から言葉が派生したとも考えにくく、音楽と言語に共通の先駆体があったと考え、それをHmmmm(全体的、多様式的、操作的、音楽的)と表記している。 乳幼児への発話(IDS)は、メロディがメッセージになっており、韻律だけで話者の意図をくみ取ることができる。 乳児の音楽単語の識別は絶対音感への依存度が高く、成長するにつれて相対音階へ変わってゆく。メロディを絶対音感でしか識別できないと、声のピッチが異なる同じ単語を認識できないため。これを進化に置き換えると、サルは絶対音感を用いているかもしれない。 アフリカ類人猿の鳴き声の大まかな音響構造は似ており、すべてグラント(うなり声)、咆哮(ほえたける)、叫び、フートの変形である。これらがヒトの言語や音楽の先駆体になったと想像できる。 人類との類縁関係が遠い霊長類には、言語的で音楽的な発声をするものがある。ベルベットモンキーは決まった捕食者に対して決まった声を発する。ゲラダヒヒは人の会話にそっくりな音を社会相互作用に用いる。発声の始まりと終わりを示すためにリズムやメロディを変化させ、IDSと類似性がある。つがいによるデュエットは、テナガザルなどの一夫一婦制の霊長類で見られ、絆固めや縄張りの主張などの協力を行っていると思われる。サルとヒトは、それぞれの感情を表現するために同じようなピッチ変化を用いる。 類人猿が他の個体に知識を説明しないのは、自分の知識と他者の知識が異なることを認知できないためではないかとの説がある。 ホモ・エルガステルは、頭蓋の真下から脊髄が通じるようになった。脊髄と口の間にある喉頭の空間が狭くなったため、喉頭はのどの下方に位置するようになり、声道が長くなり、発声できる音の幅が広がった。用いる言語は、全体的な発話だった可能性が高い。 初期人類は、動物のコールや自然界の音をまねただろう。音共感では、「イ」が小さいもの、「ウ、オ、ア」は大きいものと結びつく。鳥の名前は機敏な動きを表す高周波の分節音からなり、魚の名前はゆっくりとした魚らしさを表す低周波の分節音からなる。 感情のこもった、音楽的に豊かなHmmmmの発声を共有することで、集団同一性を作り出し、協力行動を促進した。 音声言語に欠かせない複雑な運動制御に必要な神経の多さを反映する舌下神経管の大きさ、話し言葉のために呼吸を制御する神経が通る脊柱管の直径は、いずれもネアンデルタール人と現代人とで同等だった。しかし、意図的な加工品で、実用的な使い方以外の非象徴的な解釈ができないものが見つからないことから、象徴的な意味のある発話である言葉を使っていなかったと推測される。それぞれの動物に合わせた専用の武器をデザインすることがなかったことは、博物的知能と技術的知能をひとつの思考にまとめることができなかったためと考えられる。言葉を使わなかった代わりに、音楽能力を進化させていただろう。 脳内で言語の神経回路を発達させる遺伝子を含むFOXP2遺伝子は、類人猿とヒトではアミノ酸が2つだけ異なり、この変化は20万年前以降に起きた。 10万年前に近東に移住したスフールとカフゼーのサピエンスは、制作していた石器から考えると、Hmmmmに頼ったコミュニケーションを行っていた。5万年前を過ぎた頃に近東やヨーロッパに進出した現代人は、壁画、彫刻、埋葬人骨、石の人工物、骨器などの象徴的思考の証拠から、構成的言語を使用していたと考えられる。 構成的で指示的な言語が進化した後に、Hmmmmは感情の表出と集団同一性の確立のためだけの音楽というコミュニケーション手段となった。音楽は、超自然の存在とのコミュニケーションとして、宗教的な機能を持っていたと考えられる。 Hmmmmは他に、乳幼児への発話、身振り、擬音、音声模写、音共感、あいさつなどの定型表現として残っている。
Posted by 
何故ヒトは音楽を楽しむのか? 音楽を聴いたり作ったりすることによって、食物が得られたり子孫が生まれたりするわけでもないのに――。 そんな問いに答えてくれるのがこの本です。 結論から言うと、本書にはこのように書かれています。 “音楽は、言語が進化したあとの「Hmmmmm」の残骸...
何故ヒトは音楽を楽しむのか? 音楽を聴いたり作ったりすることによって、食物が得られたり子孫が生まれたりするわけでもないのに――。 そんな問いに答えてくれるのがこの本です。 結論から言うと、本書にはこのように書かれています。 “音楽は、言語が進化したあとの「Hmmmmm」の残骸から生まれた” “音楽作りは、言語のほうがはるにうまく情報を伝達できるおかげで、先駆体時代の本来の役割のひとつが不要になって生じた衝動が進化したものだ” 本書を未読の方からすれば、なんのことやらでしょう。「Hmmmmm」ってなんだ? 引用を含む解説をすると、「Hmmmmm」は著者が作った造語で、全体的、多様式的、操作的、音楽的、ミメシス(意図的ではあるが言語的ではない表象行為を意識的、自発的におこなう能力)的な特徴を持つ精巧なコミュニケーション体系を表わしています。 先駆体とは、ホモ・エルガステルやホモ・エレクトスといった我々の祖先のことです。 著者はまず、「構成的原型言語説」と「全体的原型言語説」というふたつの対立した説を提示しました。 「構成的原型言語説」とは、まず「俺」「熊」「殺した」などの単語が生まれて、それを恣意的に繋げることから言語が始まったという説です。 それに対して「全体的原型言語説」とは、構成的原型言語説とは逆に、先に長いフレーズが生まれ、それが“分節化”することで単語が生まれ、その後、それを組み合わせて言語が形作られていったという考え方です。たとえば「彼女にそれを渡せ」という意味の「テビマ」というフレーズと、「彼女とそれを分けろ」という意味の「クマピ」というフレーズがあった場合、そのふたつに共通する「マ」を「彼女」と定義する、というふうに単語が生成されるといった形で。 著者は、全体的原型言語説を支持して、実験心理学や考古学の研究結果を通して、理論を固めていきます。おおまかな流れとしては、 ①我々の先駆体(サルと共通の祖先)が「Hmmmmm」によるコミュニケーションを取り始める。 ②「Hmmmmm」から単語を抽出できる遺伝子を持った個体が生まれ、その単語を組み合わせた言語で、複雑な概念を伝達できるようになる。 ③言語を獲得したことによって、認知的流動性(個々の知能の考え方や知識の蓄えをひとつにまとめ、新しい思考――たとえば、人の心を持つライオンなどの空想的生物など――を生み出す能力)が生まれる。 ④情報交換の役割を言語に譲った「Hmmmmm」は、認知的流動性の持つ創造性(宗教や、複雑な楽器の誕生など)に後押しされながら音楽として発展していく。 本書の論旨は、おおよそこのように展開されます。多岐に渡る分野の事例を用いて、展開していくプロセスは非常に慎重でスリリングです。わりと分厚い本ですが、飽きずに読むことができました。 私が重要だと思うのは、いちど断絶されたように見える言語と音楽が「Hmmmmm」というひとつの根を持っているということです。定型詩の面白さは、おそらくここに起因しています。日本人が好きな七語調のリズムは、きっと劇的で普遍的な「Hmmmmm」としてかつても愛されていたのでしょう。 音楽――クラシック、ジャズ、ロック、ポップス、なんでも――を聴くとき、かつてその源流であった我々の先駆者の音楽や「Hmmmmm」に思いを馳せてみるのも良いかもしれません。
Posted by 



