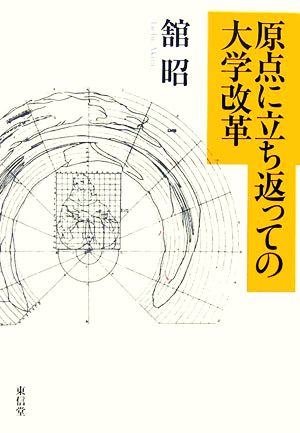
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1218-01-01
原点に立ち返っての大学改革
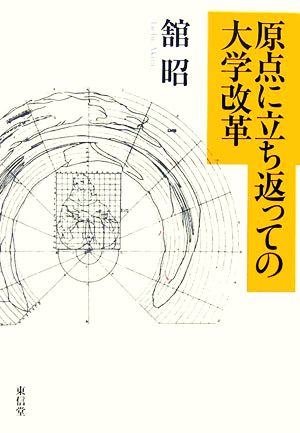
定価 ¥1,100
220円 定価より880円(80%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東信堂/東信堂 |
| 発売年月日 | 2006/07/15 |
| JAN | 9784887136861 |
- 書籍
- 書籍
原点に立ち返っての大学改革
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
原点に立ち返っての大学改革
¥220
在庫なし
商品レビュー
4.5
2件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
○リベラル・アーツと教養(culture)の混同 1990年代の大学設置基準の大綱化によりいわゆる教養課程が多くの大学で軽視され解体されたのを機に、皮肉にも「教養教育やリベラル・アーツは、大学教育の根幹」とも言われることが多くなった。しかし、リベラル・アーツと教養(culture)の混同がさらに教育改革を混乱させているというのが著者の主張である。 まず、混同の原因は、リベラル・アーツはディシプリン(学問的方法)を持った「専門」科目であることが認識されていない点にある。リベラル・アーツは、職業専門科目(Occupational and Technical Disciplines)と対置される科目群であって、中世の大学で学んだ言語系3学と数学系4科に、近代においては人文学、社会科学、自然科学の基礎学術が加わったものなのである(cf. カーネギー分類)。 とすれば、なぜリベラル・アーツ=教養(一般教育)という誤解が生じたのか。このことは本書には触れられていないが、自分なりに考えてみた。 アメリカでは20世紀に社会の変化とともに大学教育が拡大し、第二次世界大戦前後に大学教育改革が論じられるようになった。それまでの有名校の伝統的なリベラル・アーツを中心とした Liberal Education よりも,各世代の大部分の人々に対する一般(普通)教育(General Education)と表現される教育を、大学教育の中でも組織・実践しようとする理想が広がった。これはアメリカ中等教育の不十分さを大学で補うものでもあった。同時期に、専門性を高めるための大学院も拡大していることも重要である。 このようなGeneral Education の考え方は、第二次世界大戦後のアメリカにおける教育改革の中でバイブルとされた『自由社会における一般教育』-ハーバード委員会報告書』でも見ることができるが、この考え方が、GHQに設けられたCIEの指導を通して一般教育という訳語で日本にも移入され、同時に専門性を高めるために課程制大学院も移入されたのである。 当時のアメリカは、一部の中等教育の不振と学士課程終了後に大学院に進学するケースも多くあったためにGeneral Education はうまく機能した。しかし一方、中等教育が比較的よく機能した日本では、戦後も大学院への進学率が低迷した(ドイツの大学制度をモデルの柱としていた当時の日本の大学では専門科目は大学で学ぶものという意識が強かった)のでアメリカとは事情が異なったのだ。しかし、アメリカにおける、リベラル・アーツを学んでから大学院で専門科目を履修するという流れ(順序)が、専門科目を履修する前の学び(General Education)がリベラル・アーツであるとの誤解に繋がった可能性は十分考えられる(アメリカのリベラル・アーツカレッジでも、リベラル・アーツ専門科目を学ぶ前段階としてGeneral Education の履修は求められる)。 さらに、大衆化され浅いが広い分野を学ぶ形態のGeneral Education は、幅広い知識の意味を含む「教養課程」という訳語も時としてあてられてしまった。 しかし本来、教養はCulture(文化)の訳語であることから、寮生活などでの様々な人との交流と学生の自主的活動などによって養われる、「大学文化」から得られるものでもある。つまり、そもそもカリキュラム化(=定の範囲と順序で編成化)できるものではないということだ。 つまり、「教養」には共通認識できる明確な定義がなく、かつカリキュラムとしてなじまない。これをカリキュラムに組み込もうとする改革が混乱を招いている。リベラル・アーツの正しい認識と構成員間での共有が大学教育改革の原点となるのであろう。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「変化をしない大学は衰退する。変化しても原点を失う大学は衰退するか、大学であることをやめる(p1)」 先週末の有志勉強会@東京で、10年以上前に学内勉強会で課題本とした本書を紹介した。改めて読み返すと状況は何ら変わってない。というか、強制される改革で「大学であることをやめる」大学が増えてるんじゃないか。ちなみに上記学内勉強会は、認識不足で自然消滅したという苦い過去。
Posted by 



