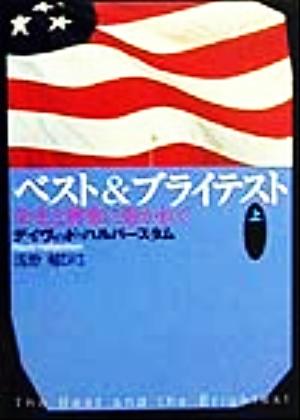
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-15-03
ベスト&ブライテスト(上) 栄光と興奮に憑かれて 朝日文庫
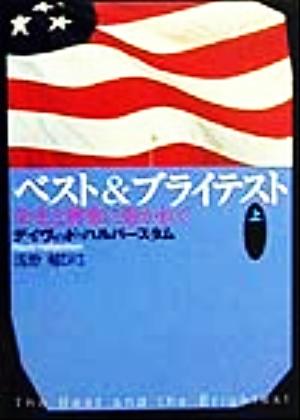
定価 ¥990
935円 定価より55円(5%)おトク
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | 内容:栄光と興奮に憑かれて |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞社 |
| 発売年月日 | 1999/07/01 |
| JAN | 9784022612618 |
- 書籍
- 文庫
ベスト&ブライテスト(上)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ベスト&ブライテスト(上)
¥935
在庫なし
商品レビュー
3.9
9件のお客様レビュー
なぜエリート人材が集まったアメリカが、ベトナム戦争の泥沼に引きずり困れてしまったのか? ・マーシャルプラン等の成功体験があった(p.21) ・頭がきれる者は揃っていたが、地方の保安官にでもなった経験がある者がいれば・・・(p.101-102) ・あまりに戦術的・機能的で、長期的...
なぜエリート人材が集まったアメリカが、ベトナム戦争の泥沼に引きずり困れてしまったのか? ・マーシャルプラン等の成功体験があった(p.21) ・頭がきれる者は揃っていたが、地方の保安官にでもなった経験がある者がいれば・・・(p.101-102) ・あまりに戦術的・機能的で、長期的展望に欠けた(バンディ、p.140-141) ・キューバ侵攻からの流れ(p.148) ・「ベトナムぐらいの問題」という見方(p.171)。アジアより欧州への関心(P.181)。アジア・ベトナムへの米の無関心(p.187) ・中国をめぐる挫折のためにベトナムに関与(p.222) ・傲慢不遜な自信過剰(p.261)。米が越を救えるというアメリカ万能主義(p.285) ・ディエンビエンフーは、フランスは越を罠に欠けようとしたが、大砲を実はもっていて仏を見下ろすことができた越に惨敗。これで仏国内の世論にはとどめを刺したが、別では仏兵を救出せよという圧力の高まり(p.288~289) ・主要な政策決定を行っている、という意識をもっていなかった。少々金をつぎ込めばいい、失敗しても失うものはほとんどあるまいというのが当時の態度。(p.311) ・南ベトナムの正当性、存立可能性を疑わず。(p.311,314) ・ベトナム戦争についてのテーラーの報告。フランス・インドシナ戦争やフィリピンの独立闘争が恰好の材料を提供していたのに、テーラーはベトナム戦争の類比を挑戦に求めた。(p.350) ・国防省の情勢報告の腐敗。(p.364) ・「新しい戦争」を論議しているのに「最もありきたりの将軍」を据えた。ケネディですらこのことに気づいていたが。(p.366)
Posted by 
『なぜ、優秀な人々があつまっても、泥沼の戦いを防ぐことができなかったのか?』 これが、デイヴィッド・ハルバースタムの名著「ベスト&ブライテスト」に一貫して流れる通奏低音である。 この本の中には、煌びやかな経歴を誇る俊英・秀才、そして策士が次々と現れてくる。そして彼らが様々な糸...
『なぜ、優秀な人々があつまっても、泥沼の戦いを防ぐことができなかったのか?』 これが、デイヴィッド・ハルバースタムの名著「ベスト&ブライテスト」に一貫して流れる通奏低音である。 この本の中には、煌びやかな経歴を誇る俊英・秀才、そして策士が次々と現れてくる。そして彼らが様々な糸で絡み合いながら、歴史は紡がれていく。 この本を読むたびに思うのは、すぐれた「編集力」を持てなかった組織の脆弱さである。 組織は、様々な人の集合体である事はいうまでもない。組織を効率的に稼動させるには、統制色の強い、ヒエラルキーを内包した組織体系の中でフローを構築する事になる。これはとても強固な仕組みで、日本でも、これだけ批判がありつつも、なかなか変質しない中央/地方政府組織を見れば明らかだ。 そういう中で「個の自発性」だとか「発想の転換」という事が叫ばれても、そもそもそれは、政府系組織にあるような官僚的組織には、そもそも相容れない、厳密に言えば「一部の人以外の大多数」には相容れない、のだ。 「一部の人」とはだれか?無論、役責者だ。 この「ベスト&ブライテスト」の中にも、多くの役責者が出てくる。いや、殆どがそういう人達の話だ。 「ごく一部の」役責者が「発想の転換」をするのに、果たして官僚的組織は適しているのか?というパラドキシカルな問題がここでは浮上してくる。 「編集」という概念は、ここで決定的な役割を果たすと私は思う。 無論、従来より「編集」という営為は官僚機構の中でも行なわれてきた、それもかなり効率的に。しかし、それは本当の編集ではなかったのではないだろうか? かつて「Web2.0」という言葉が巷間に広まったが、そのコアの考え方、根底には「利他」という考えがあるように思う。私が一時期深く関与した「業務用オープンソース」のビジネスモデルが、最も近しいように思う。 うまく結論めいたものを導き出せないのだが、そういう発想が仮に広まっていたとしても、「ベスト&ブライテスト」の中にある彼らが、アメリカをヴェトナム戦争から救う事は出来なかったような気がするのだ。
Posted by 
ケネディが、そしてのちにジョンソンも学ぶように、軍部はいったん敷居をまたがせると、一筋縄では言うことを聞く相手ではなかった。その後あらゆる時点で、軍部による見通しは誤りを犯したが、そのことで遠慮をするような軍部ではなかった。普通ならば、彼らは信用を失い、その圧力も減退していくもの...
ケネディが、そしてのちにジョンソンも学ぶように、軍部はいったん敷居をまたがせると、一筋縄では言うことを聞く相手ではなかった。その後あらゆる時点で、軍部による見通しは誤りを犯したが、そのことで遠慮をするような軍部ではなかった。普通ならば、彼らは信用を失い、その圧力も減退していくものと考えられるのだが、軍部については事は逆転であった。圧力はむしろ高まり、要員、兵器、攻撃目標すべてについて要求は増大していった。核兵器の使用に至らぬ限り、軍部のツケはすべて文官に回されるのである。
Posted by 



