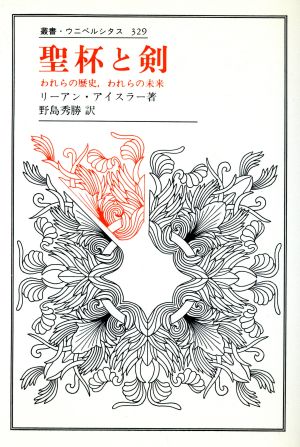
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1216-02-05
聖杯と剣 われらの歴史、われらの未来 叢書・ウニベルシタス329
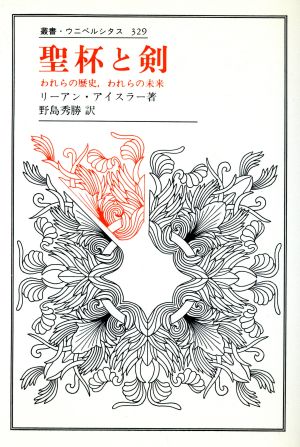
定価 ¥3,850
1,760円 定価より2,090円(54%)おトク
獲得ポイント16P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/15(木)~1/20(火)
店舗到着予定:1/15(木)~1/20(火)
店舗受取目安:1/15(木)~1/20(火)
店舗到着予定
1/15(木)~1/20

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/15(木)~1/20(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 法政大学出版局 |
| 発売年月日 | 1991/09/30 |
| JAN | 9784588003295 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
1/15(木)~1/20(火)
- 書籍
- 書籍
聖杯と剣
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
聖杯と剣
¥1,760
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
マトリズム(母性制)とパトリズム(父性制)がどのように分断され、しかし、にもかかわらず、神名やイコンや器物表現には、それらの分断以前のシンボリズムがどのように活発に“再生”されていたかを議論した。力作である。つまりは、われわれは何に支配されるかという問題を扱っている。 暴力が母...
マトリズム(母性制)とパトリズム(父性制)がどのように分断され、しかし、にもかかわらず、神名やイコンや器物表現には、それらの分断以前のシンボリズムがどのように活発に“再生”されていたかを議論した。力作である。つまりは、われわれは何に支配されるかという問題を扱っている。 暴力が母性制を覆い隠した的な話で、母権論をさらにフェミニズム的な視点で咀嚼して吐き出した感じの内容
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 男性支配のイデオロギーと制度としての歴史を徹底的に検証しなおし,〈支配者形態社会〉から〈協調形態社会〉への転換の可能性を追求して人類の未来への展望をひらく。 [ 目次 ] 《聖杯》と《剣》 失われた世界への旅―文明の始まり 過去からのメッセージ―《女神》の世界 本質的な差違―クレタ 混沌から暗い秩序へ―《聖杯》から《剣》へ 失われた時代の記憶―《女神》の遺産 逆立ちした現実 歴史のもう一つの半分 過去の形―女男結合制と歴史 縛めを解いて―未完の変容 進化の没落―支配者形態の未来 進化における大躍進―協調形態の未来に向けて [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by 
ティム・オブライエンの小説の冒頭を思い出した。 ~ 「私が男にいちばん参っちゃうところはね」とジャンは言った。「なにはともあれあいつらが、基本的にうぬぼれが強いってことよね。そういうところは好きだな。言ってることわかる?」 「わかるよ」とエイミーは言った。 「そういうところを抜...
ティム・オブライエンの小説の冒頭を思い出した。 ~ 「私が男にいちばん参っちゃうところはね」とジャンは言った。「なにはともあれあいつらが、基本的にうぬぼれが強いってことよね。そういうところは好きだな。言ってることわかる?」 「わかるよ」とエイミーは言った。 「そういうところを抜き去ったら、あとに何が残ると思う?」 「なんにも」 「そのとおり!」とジャンは言った。 「乾杯」とエイミーは言った。 「男たちに」とジャンは言った。 ~ どうして「俺は誰の力も借りずに生きていく・・・云々」だなんていう、トンチキな考え方を絞り出す脳みそはいつでも男性ホルモンに満たされているのだろうか。どうしてそれが魅力的に映るのか。ホントにそう思ってるのか、それともそうせざるを得ないのか。それとも、そうするべきなのか。 ~ 「どう転んだところで、私たちはあいつらにとことん殺されちゃうのよ。いつも同じ、花束に墓石。例外はない」 ~ どうして世の中はそのトンチキな方に味方するのか。さらに言えば、どうして「女の強さ」というやつを、男たちは必死に否定し貶めるのだろうか。このあらがえない何かは、もしかすると仕方のないことなのか。「生物学と政治はうまく折り合いがつかないのよ」「良いことだけに目を向けていれば人生は幸せさ」、そういうことなのか。小説のこの断片を取り上げるならば、アイスラーが解き明かそうとするのは、ここに見出されるカラクリである。 しかしアイスラーは警告する。「それは人間や社会の本性ではない」と。「このカラクリは歴史的な起源をもつものである」と。その根拠は、古代の歴史の中に、かつて「女性的な」価値観を基調とした協調的共同体文明の存在を示す証拠が語りかけるとおりである。 気をつけておかなければならないのは「女性的な」文明は、女性上位(女家長制)の文明とはイコールではない。アイスラーが「女性的」であるとするのは、「男性的」に人間関係を「支配する」という捉え方をするのではなく、人間関係を「協調に導く」という捉え方をするイデオロギーである。すなわち、自らを生み育てたものを尊敬・尊重するという価値観の上に立った文明である。 アイスラー曰く、この価値観こそが、物事の全体性をとらえるためにも、そして、自由な社会を作り上げる上でも、至急取り入れていかなければならないものなのだという。メジャーな社会学の流れで言えばこれは公共性の議論だということになろうが、おそらく彼女はあくまでも「女性的」に考えよということを強調するだろう。 結論に異論はない。が、一部、個人的に合点のいかないところが、その協調文明が崩れた原因を、男性的で好戦的な遊牧民の襲撃に求めたというところだ。遊牧民はどうして生まれ、なぜ男性的になったのだろう?そこは説明されていない。しかしそこにこそ、「男性化」の秘密が隠されているのではないか?そして、倫理的な問題になるが、氏が生命工学に対して楽観的な態度をとっているということだ。それは尊重すべき人間の「自然」を著しく犯すことにはならないか。 学術書ではあるが、ウェーバーのプロ倫のようにミステリーっぽく読めたりすれば、理想社会を語る章はSF(もちろんユートピア的でない)のようですらある。前に流行ったダ・ヴィンチ・コードと扱うテーマが同じであるが、この手の研究をベースにして書かれたものだろう。 単なるフェミニズムの本ではない。われわれの思考を相対化してくれる一冊。 先生から6月に借りてやっと読んだ。
Posted by 


