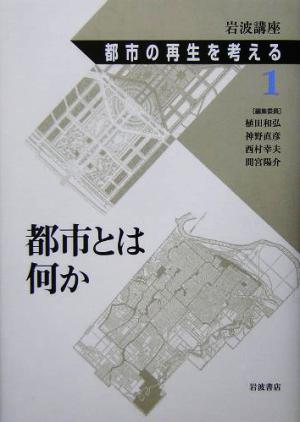
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1212-01-14
岩波講座 都市の再生を考える(第1巻) 都市とは何か
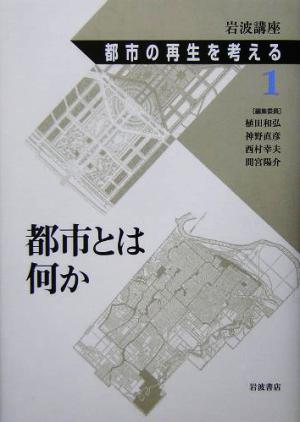
定価 ¥3,190
1,815円 定価より1,375円(43%)おトク
獲得ポイント16P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗到着予定:3/5(木)~3/10(火)

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
3/5(木)~3/10(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2005/03/28 |
| JAN | 9784000109734 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
3/5(木)~3/10(火)
- 書籍
- 書籍
岩波講座 都市の再生を考える(第1巻)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
岩波講座 都市の再生を考える(第1巻)
¥1,815
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
1件のお客様レビュー
古典的な都市論を下敷きにして、都市を農村という「ケ」に対する「ハレ」の場所と見る場合、都心回帰が進む昨今の東京首都圏は既存の都市論ではとらえ切れないような独特の様相を呈している。 バブル以降の地価下落と、その後の規制緩和政策により高容積が可能となった土地により、都心部においても...
古典的な都市論を下敷きにして、都市を農村という「ケ」に対する「ハレ」の場所と見る場合、都心回帰が進む昨今の東京首都圏は既存の都市論ではとらえ切れないような独特の様相を呈している。 バブル以降の地価下落と、その後の規制緩和政策により高容積が可能となった土地により、都心部においても、狭いながらも中流階級が住まいをもつことが出来るようになってきている。これは都市政策のグランドデザインを政策に落とし込んだ結果としてではなく、不良債権処理のための近視眼的な政策により、結果的にそうなったに過ぎない。 農村/都市という対立によって人々の生活様式を語ることができた時代においては、都市とは絶えず流入する人々が交流し接触する場として機能しており、その機能こそが都市の本質的な存在意義であった。都市デザインとしての優劣は別にして、交換行為や交流という活動が集積するという機能を維持ないし増大するために都市は発展してきた。これには経済性もさることながら、より文化面に近い部分においても都市は重要な機能を持っていたといえる。 この機能面の議論のほかに外形的な部分、つまり都市の見え方についても東京は特徴的である。 都市の乱雑な開発を抑制するためには、中央政府が都市開発に関する明確なグランドデザインをたて、民間による開発をコントロールする必要がある。しかし、強い規制や舵取りは都市の多様性を奪うこととなり、都市文化の貧困化をもたらす。 様々な書籍に書かれているように、日本の、特に首都圏の都市景観に開発がコントロールされた形跡を見つけるのは難しく、私益による勝手開発によって都市景観が形成されている。 混沌、モザイク、このような言葉で表現されている東京首都圏は、古典的な都市計画論から見ると、優れていない開発だと見える。 都市が持つ外部性、接触性という機能は、都市がハレの空間としてあった時には有効に機能し、その機能が求められていたと言える。しかし昨今の都心回帰の流れにより、都心部にも多くの住空間が作られている現在では、外部性という機能が危ぶまれている。 都市に住まう人は外部性を、治安の悪さと感じ、セキュリティーのニーズが高まってくる。ケの空間は部外者を排除する方向へと動き、これが都市の外部性をも排除することとなってしまう。 職場の近くに住みたい、この利便性への欲求により、都市のもっとも根幹的な機能は排除される。政府主導の都市計画を阻害してきたのは、人々の欲求の貫入なのかもしれない。
Posted by 


