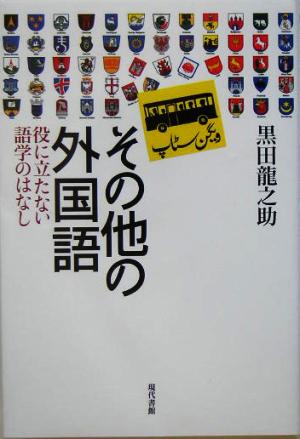
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1217-01-00
その他の外国語 役に立たない語学のはなし
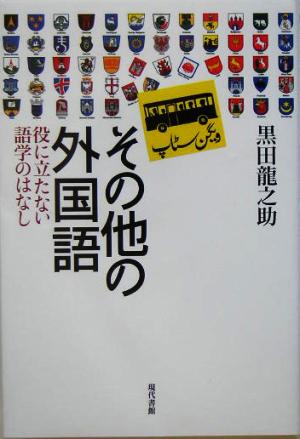
定価 ¥2,200
385円 定価より1,815円(82%)おトク
獲得ポイント3P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
3/23(日)~3/28(金)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 現代書館/ |
| 発売年月日 | 2005/03/20 |
| JAN | 9784768468920 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
3/23(日)~3/28(金)
- 書籍
- 書籍
その他の外国語
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
その他の外国語
¥385
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
12件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2005年のエッセイ。 「はじめに」の冒頭に、 「この本はわたしにとって、はじめてのエッセイ集である」 とある。なるほど、過去2冊読んだのが2018年上梓の著作だったのに比べると、いまいち振り切れていなかった。 それとなく、そののちに繋がる面白さは垣間見えるけど。 英語でも、ロシア語でもない、「その他の外国語」として、語学全般について広く浅くの軽妙な語り口は楽に読めてよい。 なかでも、「世界にはいろいろな英語があることを伝える」というのは、けだし慧眼。先日もNETFLIXの作品で「2人のローマ教皇」を鑑賞したが、教皇らの英語が片やドイツ訛り、片やアルゼンチン風スペイン語訛りと、聴くからに違う。 折しも今朝(2019年12月30日)のJ-WAVEのナビゲーターのサッシャが巧みな英語で、ドイツ訛り(これは母語か)、フランス訛、インド訛、イタリア訛と面白おかしく物まねしていた。まさに「世界にはいろいろな英語がある」だなと、本書の記述を思い出していた。 副題の通り、役に立たない話が多いが、役に立つことが全てではない。と、著者の本を読んでいるといつもそう思う(笑)
Posted by 
どんな内容かも分からずに買ってみたが、結果としては「最高」。語学、外国語を通じて人生もっと楽しんでも良いかも、と思えた。好奇心と思うがままに、自己流の方法論を築き上げて行けばそれでいいのかも。いつか自分も面白おかしくこのようなエッセイを書けるようになりたい。
Posted by 
ロシア語を専門とし、スラヴ言語の諸語も話す著者による、自身が公言する「初」エッセイ。 「この本はわたしにとって、はじめてのエッセイ集である、」 その一文で始まる。 この本の前には、『外国語の水曜日』が出版され、書評で、「著者の二冊目となるエッセイ…」とされる。 自身初の著...
ロシア語を専門とし、スラヴ言語の諸語も話す著者による、自身が公言する「初」エッセイ。 「この本はわたしにとって、はじめてのエッセイ集である、」 その一文で始まる。 この本の前には、『外国語の水曜日』が出版され、書評で、「著者の二冊目となるエッセイ…」とされる。 自身初の著書は『羊皮紙に眠る文字たち』が第一弾となるわけだ。 それは、外部からの判断であって、筆者は前二作の著書を「エッセイ」として書いたつもりはない、と。 筆者は、『羊皮紙に〜』は”スラヴ文献学”の、『外国語の〜』は”言語学”の入門書のつもりで書いたのに、である。 まあ、確かに軽妙な語り口で、外国語(特に東欧諸語)をエピソードに、簡潔明快な文章だったので、自分も、『羊皮紙に〜』も『外国語の〜』もエッセイだと思っていました。 さて。本書の内容。 筆者自ら「初のエッセイ」と言うだけ合って、先の本よりも比較的気楽に読めた。 自分は、『羊皮紙に眠る文字たち』『チェコ語の隙間』『外国語の水曜日』『外国語をはじめる前に』『ことばは変わる』と読んで、この本を読んだ。 そうなのである、『羊皮紙に〜』を読んでから、一気に黒田氏のユーモア(時に少しの皮肉)を込められた文章に見せられ、いや、言語(スラヴ語)の魅力に引き込まれたのである。 そして、多言語を学ぶ愉しさを教えてくれた。 メジャーな英仏独西を中心とする言語に対する、マイナーな「その他」の言語の魅力を語る。 英語一辺倒な日本の外国語学習にも疑問を呈し、持論を展開し、その意見にも肯ける。 この本を読んで、ますます「外国語=英語」ではないのだなと思いを深くする。 英語(学習)を否定するのではなく、英語も世界にある中の一つの言語として捉え、いかに言語を学ぶかということを書いている。 他のレビューにも書かれているが、まさに、「外国語を話せるとは、どこまで話せたら『話せる』ということになるのだろうか」という問いには、大きく頷いた。 この著作でも、筆者の言語に対する愛を感じられる、読みやすい黒田氏にとっての「初エッセイ」である。 「ことば」「言語学」、また「多言語学習者」に興味がある方は、ぜひ読んで欲しい。 (もちろん、それ以外の著作も、多くの人に読んでもらいたいです。)
Posted by 


