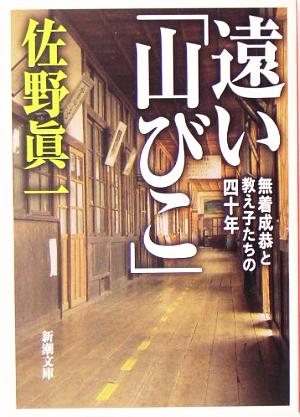
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-32-01
遠い「山びこ」 無着成恭と教え子たちの四十年 新潮文庫
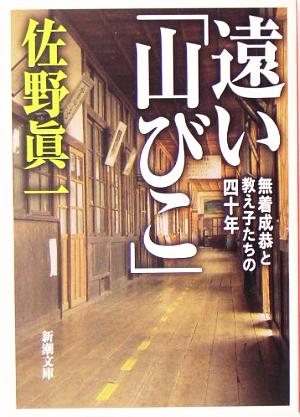
定価 ¥733
605円 定価より128円(17%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社 |
| 発売年月日 | 2005/04/25 |
| JAN | 9784101316376 |
- 書籍
- 文庫
遠い「山びこ」
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
遠い「山びこ」
¥605
在庫なし
商品レビュー
4.3
4件のお客様レビュー
1948年に刊行され、映画化もされるなど大ブームとなった『山びこ学校』は、養蚕と木炭生産に依存する秋田県の山村・山元村の中学生の作文集である。本書はこの『山びこ学校』を取り上げたルポルタージュ。ブームとなった背景やブームが指導者・無着成恭や生徒に及ぼした影響、その後の山元村の過疎...
1948年に刊行され、映画化もされるなど大ブームとなった『山びこ学校』は、養蚕と木炭生産に依存する秋田県の山村・山元村の中学生の作文集である。本書はこの『山びこ学校』を取り上げたルポルタージュ。ブームとなった背景やブームが指導者・無着成恭や生徒に及ぼした影響、その後の山元村の過疎化などが、丹念な取材によって明らかにされている。 とくに、中学生43名のその後を全員明らかにしていく過程は圧巻であり、佐野眞一の執念を感じさせる。戦後の経済成長や教育とは何だったのかを改めて考えさせてくれる作品。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2005年(底本1992年)刊行。 戦後、特異な綴方教育として名を馳せた「やまびこ学校」は、いかなる人物がいかにして生み出したのか。そして後世に向けて何を産み落としたのか。 本書は、無着成恭という青年教師の来歴から、教え子の生活や生き方に及ぼした影響、山形県山元村という地域属性と歴史性、社会や教育スタンスの戦後における変遷との関わり、教育ジャーナリズムに翻弄された有り様を通じ、先の問いに答えんとする試み。 戦後の農業生産性、農家の一人当たりの所得変遷やその要因、農村の過疎化や疲弊の要因など首を傾げたくなる指摘もある。が、個々の追跡の厚みは流石だ。 第一の読後感。つまり無着の生き様に関しては、ジャーナリズムや論壇に過度に取り上げられた結果、無着の教育実践の地域性・時代性を引き剥がし、見えなくしてしまったというもの。 そして、彼の限界という観点も本書は鋭く指摘している。 すなわち、無着の教え子が多くの場合、貧困層から抜け出し得ず、しかも地元から関東圏へ出て行かざるを得なかった。 戦前昭和から引き続く、次男三男坊の悲哀、口減しの圧力には何の抗いにもなっていなかったことが痛く刺さる。 結局、無着の一番の教え子をして、自身の娘には地元中学ではなく、附属中学を受験させ、息子には高校受験をさせ、二人に対し大学進学を促し実行させた事実が全てを物語っていよう。 そういう意味では、確かに所得の関係から高校進学が困難な時代相ではあったにせよ、進学に必要な英語の授業を三分の一にまでして綴方授業をなすべきだったのか。期せずして進学の芽を摘んだ印象も強く、無着の「山びこ学校」的な実践は、試行錯誤の「試」の段階に過ぎなかったのではないかという印象も強い。 そもそも公的教育は万能ではない。 教育資源で見れば、教師の能力的・時間的な限界、当該教育が付与される地域や時代による限界、さらには金銭面での限界が存するのは当然である。 一方、無着が理想とした教育像は、入学試験なし、おそらく留年・落第なし、点数序列の禁止というものであろう。 しかし、学問なり学習は、ただ座っていればできるものではない。 そして、もう一方の教育主体である学習者側にも意欲、資質、環境などの面で限界のあるのは否定できない。 野球を例に出せば、野球未経験者がプロ野球の練習生の門を叩こうとしても拒絶されるのが普通であり、それを奇異には感じないだろう。仮に門戸が開けられたとしても、力不足によるリタイアもまたさほど奇異ではないはずだ。 学習もまた然り。 留年許容、退学許容であることを前提にしなければ、入学試験の全くないシステムは機能しないだろう(もっとも、再挑戦の可能性を広く保障することが問題のないのは当然)。 無着について見るに、彼の綴方教育の個別具体的な教授術とその実践的意味は兎も角として、彼の理想とする教育全体の方向性は、時代を問わず無理があったのではないか。あるいは、無着は自覚的でないだろうが、全入時代のお客様大学生において発生する問題点を等閑視した考えではなかったか。 そんな疑問を生んだ本書の読後感である。
Posted by 
生活綴方教育の金字塔と言われる『やまびこ学校』。山形の貧しい村の中学生が、自らの生活を見つめて書いた作文集は、戦後を代表する大ベストセラーとなった。 指導者だった教師・無着成恭はまだ20代前半。いったい無着はどうしてそんな作文集を生み出すことができたのか。そして、その後、一躍ヒ...
生活綴方教育の金字塔と言われる『やまびこ学校』。山形の貧しい村の中学生が、自らの生活を見つめて書いた作文集は、戦後を代表する大ベストセラーとなった。 指導者だった教師・無着成恭はまだ20代前半。いったい無着はどうしてそんな作文集を生み出すことができたのか。そして、その後、一躍ヒーローとなった彼はなぜ村を去ったのか。その先東京で、生活綴方を捨てて科学的な作文指導法に傾倒したのはなぜなのか。そして何より、『山びこ学校』の主役であった生徒たちは、その後どんな人生を送っていったのか……。 まず何よりも、作文教育に関心のある僕には、無着成恭という傑出した教師の人生を追ったとても面白いノンフィクションだった。もちろん彼の作文指導(=生活指導)は興味深い。この本を傍らに改めて『山びこ学校』を読むと、あの文集が単に素朴に書かれたのではなく、「見る」技術の集積であることは、僕にとって大事な発見だった。特に、『山びこ学校』収録前のもともとの冊子「きかんしゃ」では、下半分が空欄となっていて丁寧な添削がほどこされていたことなど、その指導法が非常に興味深かった。 しかし、そういう国語教育的な文脈を抜きにしても、この本は戦後史の一断面として非常に優れた本だと思う。戦後の東北の貧しい村で、人々はどのような生活をしていたのか。都会が高度経済成長で沸き立つ中で取り残され、国から農業を見捨てられ、やがて自分も都会に行かざるを得なくなる村の人たち。そういう時代の流れの中で、貧しいながらも希望に燃えていた『山びこ学校』の生徒たちもまた、苦しい戦いを余儀なくされていく。 そうした教え子の人生の中で個人的に特に印象深いのは、『山びこ学校』の作品群の中でも文部大臣賞を受賞した作文「母の死とその後」を書いた江口江一と、卒業式での名高い「答辞」を書いた佐藤藤三郎の二人。無着の一番弟子のような二人が、その後ひとりは無着の辛辣な批判者となり、もうひとりは無着の教えそのままに働いて夭折する、その交錯は印象深い。 著者の佐野眞一は、丹念に取材を重ねて資料や証言を集め、『山びこ学校』を一つの糸にして歴史の一側面を描き出すことに成功している。わずか数十年ほど前のことなのに、もう消えてなくなりそうな「戦後」という時代の息遣いを、僕は読んでいて重苦しいほどに感じさせられた。
Posted by 



