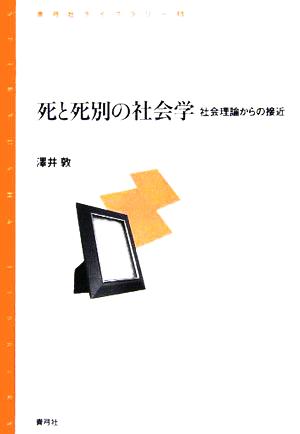
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-06-00
死と死別の社会学 社会理論からの接近 青弓社ライブラリー43
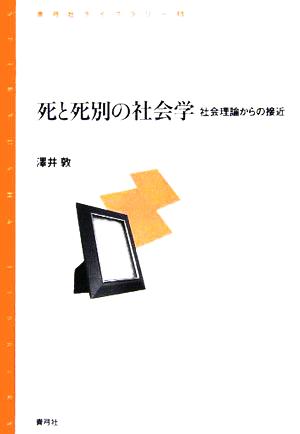
定価 ¥1,760
1,595円 定価より165円(9%)おトク
獲得ポイント14P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 青弓社 |
| 発売年月日 | 2005/11/18 |
| JAN | 9784787232502 |
- 書籍
- 書籍
死と死別の社会学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
死と死別の社会学
¥1,595
在庫なし
商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
著者はいわば「死別の作法」というべきことごと(看病の仕方、告知の仕方、臨終のまさにそのときの迎え方、葬送の仕方など)が宗教的なものにせよ非宗教的なものにせよ常に型にはめられたものへと回帰していってしまうことを執拗に指摘しています。これは「自由」に関するナイーブな態度と言えるでしょ...
著者はいわば「死別の作法」というべきことごと(看病の仕方、告知の仕方、臨終のまさにそのときの迎え方、葬送の仕方など)が宗教的なものにせよ非宗教的なものにせよ常に型にはめられたものへと回帰していってしまうことを執拗に指摘しています。これは「自由」に関するナイーブな態度と言えるでしょう。 死別に関することに限らず、ひとの行う差異化とは完全新規で独特のやり方を発明することではなく、所与のあるカテゴリと別のあるカテゴリとを対照させることで行われるものではないでしょうか。その差異化の過程で所与のカテゴリが解体されて複数に分けられたり、統合されたり、忘れ去られたりする。あるいは誤差が生じてふいに新たなカテゴリが創始される──話はそれますが、統廃合と誤差、その結果生まれるものを独自性・創造性の発露として評価するよう要求して、個人や個人の制作物に至上の価値を与えようとする運動が芸術ということになるのではないでしょうか──したがって真の問題というのはある選択が「自由」か否かということではなく、その選択がどのような条件のもとで行われるかということでしょう。あるひとがある作法を選ぶ。別のあるひとは別のある作法を選ぶ。その選択のちがいや、選択の機会のちがいが何に由来するかを論じることでしょう。「自由」そのものをうんぬんするのは政治的ないし法律的な議論です。「ひとが何を以て自由とするか」ということこそ社会学的な議論でしょう。 自分自身の体験として親との死別の経過を思い起こすときその選択肢の問題はまだ十分に客観化されていないようです。もしもあのときああしていたら・・・しかしああする以外にどうしたらよかったろうか・・・という思考はまだその選択の由来を云々するステップには進んでいません。
Posted by 
近年、「人生の終わりのための活動」の略である「終活」という言葉をよく目にするようになりました。この「終活」には、生前整理や自身の葬儀・墓の準備等、様々な活動が含まれますが、重要なのは、この活動がその人の人生の総括として捉えられているということです。「終活」は「自分らしい最期」を...
近年、「人生の終わりのための活動」の略である「終活」という言葉をよく目にするようになりました。この「終活」には、生前整理や自身の葬儀・墓の準備等、様々な活動が含まれますが、重要なのは、この活動がその人の人生の総括として捉えられているということです。「終活」は「自分らしい最期」を迎えるための準備なのです。 しかし、「自分らしい最期」とは一体何なのでしょうか。また、「自分らしい最期」に対して、残される/残された者はどうしたらよいのでしょうか。 本書では、以上のような「自分らしい最期」を自ら決定しようとする動き、つまり死や死別をめぐる「自己決定」の広がりと、それと並行して再考を迫られてきた「関係性」や「共同性」のあり方について、比較的抽象度の高い次元で議論されています。社会学あるいは社会理論の基盤をつくった19世紀後半の社会学者マックス・ウェーバーとエミール・デュルケムから始まり、アンソニー・ギデンズに至るまで、様々な社会理論から「死の社会学」をめぐる視線や知見を引き出し、それらを理論・理論家別もしくはテーマ別に再構成することで、死や死別という身近な出来事を、近・現代社会の全体的動向という文脈の中で問うための見取り図が描かれています。 全体を通して抽象度の高い議論が続くので、社会理論に触れたことがない方は難しく感じるかもしれません。しかし、ある議論の登場した背景や内容、また理論同士の関係等について丁寧に説明してくれているので、ゆっくり読み進めて理解ができれば、非常に勉強になる一冊です。さらに、注釈に参考文献とその簡単な説明が加えられているので、そこから死や死別について発展的に考えてみることも可能です。 死を考えるということは、生を考えるということでもあります。生きること、そして死ぬということについて、掘り下げて考えてみたい方はというぜひ一読してみてください。 (ラーニング・アドバイザー/国際公共政策 SATO) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1351416
Posted by 
大学の講義で扱った本。教授の著書であるが、自分の興味ある『死』という概念について、社会学的視点から考察している。
Posted by 



