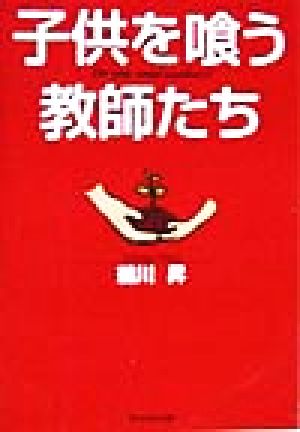
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1218-01-07
子供を喰う教師たち
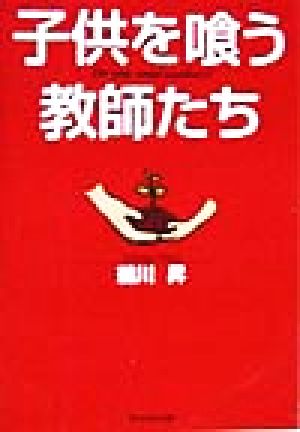
定価 ¥1,650
110円 定価より1,540円(93%)おトク
獲得ポイント1P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | プレジデント社/ |
| 発売年月日 | 1999/03/16 |
| JAN | 9784833490429 |
- 書籍
- 書籍
子供を喰う教師たち
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
子供を喰う教師たち
¥110
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
久しぶりに読んだ、骨太な教育の本でした。タイトルはちょっと大げさな気がしますが、1999年当時、業績評価とか生徒による授業評価に対して、これほど強く持論を展開できる人は、少なくとも現場にはそれほどいなかったように思います。おかげさまで、今では当たり前になった感があります。月日が...
久しぶりに読んだ、骨太な教育の本でした。タイトルはちょっと大げさな気がしますが、1999年当時、業績評価とか生徒による授業評価に対して、これほど強く持論を展開できる人は、少なくとも現場にはそれほどいなかったように思います。おかげさまで、今では当たり前になった感があります。月日が経つのは早くて恐ろしいですね。 p.93 教師の仕事は崇高な「裁量労働」である 最近流行の「裁量労働」という言葉、この本の中にもありました。崇高かどうかは別として、教師の仕事は、こういう意識がないとできない仕事であることは間違いありません。今はお休みの学校が多いようですが、こういう意識で頑張っている人、どれくらいいるのか、いないのか。 p.118 学校や社会のルールに反する行為があれば、当然、その責任は課せられる。 これは、原則その通りなのだと思います。でも、教師はそれで構いませんが、おかげで、今の子どもたちは失敗が許されなくなりました。何歳からこの原則を適用するのは、平時によく考えておく必要があります。このルール、我が子が被害者の時は当然と思えても、我が子が加害者の時も当然と思える親が、どれほどいるのでしょうか。みんな、自分の子は加害者にならないと勘違いしているように思います。 p.141 社会に出て行きていくうえで最も重要な「自立」と「自己責任」を曖昧にして当事者能力を養う教育をしてこなかったという点で、日本の教育は罪深い。 耳が痛い指摘です。こういう教育で育った大人が増えると、その子どもは…考えたくないですね。 余談。p162 というのも当時、都立高校の教師には週に1回、研究日があって、きちんと届け出をすればアルバイトができた。 確かに、私の学校の英語の先生も、予備校でバイトをしていると噂になっていました。時計とかアクセサリーが高価そうで、見るからにと思ったのを思い出しました。 p.170 東大生の質が落ちた理由 ぜひこれはお読みください。この本が書かれてから20年。今の東大生はどうでしょうか。
Posted by 
何ともドキリとするタイトルである。 そしてサブタイトルが「Do you trust teachers?」。 「教師を信用できるかい?」と、これまた扇情的なサブタイトルである。 これは横浜の桐蔭学園校長、鵜川昇氏による教育論である。 これが書かれたのが1999年ということだから、そ...
何ともドキリとするタイトルである。 そしてサブタイトルが「Do you trust teachers?」。 「教師を信用できるかい?」と、これまた扇情的なサブタイトルである。 これは横浜の桐蔭学園校長、鵜川昇氏による教育論である。 これが書かれたのが1999年ということだから、それから7年の年月が流れており、昨今の教育現場は、当時とは様相を変えている部分も多いだろう。 つい先だっても、「教師との馴れ合いから荒れる教室」などという記事をネットニュースで見たばかりである。 子どもとうまくやっていこうとするあまり、「友だち先生」にシフトして、逆に教師としての信頼感を欠き、教室の中で統制が取れなくなっていくというのだ。 この著書の中にも、同様のことは書かれており、当時からその兆しはあったのだろう。 この中に書かれていることには、賛同できることもあれば、「ちょっとそれは違うんじゃないかなあ」と思うこともあるが、次の件には大きく頷いた。 日本の教育はこれまで子供たちに当事者能力を求める教育を怠ってきた。別の見方をすれば、教育を放棄し、甘やかしてきた。ある年齢になれば、やっていい事と悪い事、つまり事の善悪を判断しなければならないし、自分の行為が悪ければ、その結果に対して責任を問われるということを子供たちに教えてこなかった。 どんなことでも学校で起きたことには、学校が責任を取ってきたからである、子供が将来、社会に出て生きていくうえで最も重要な「自立」と「自己責任」を曖昧にして当事者能力を養う教育をしてこなかったという点で、日本の教育は罪深い。 アメリカの教育現場で働いていて、日本の学校と最も異なる点がここなのである。 今、アメリカの教育現場も外側からの脅威にさらされている。 日本やアメリカに限らず、「学校」という場が大きく変わってきているのは確かである。
Posted by 



