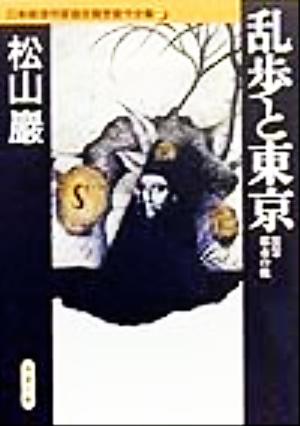
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1225-03-07
乱歩と東京 1920都市の貌 日本推理作家協会賞受賞作全集 49 双葉文庫
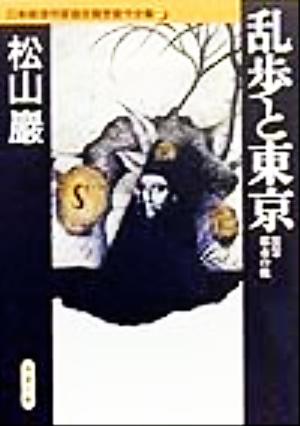
定価 ¥628
550円 定価より78円(12%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 双葉社/ |
| 発売年月日 | 1999/11/19 |
| JAN | 9784575658484 |
- 書籍
- 文庫
乱歩と東京 1920都市の貌
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
乱歩と東京 1920都市の貌
¥550
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
乱歩の作品を軸に、1…
乱歩の作品を軸に、1920年代の東京の風俗を考証しています。
文庫OFF
建築家であり作家でもある著者による、江戸川乱歩×都市論。 1920年代に東京を舞台にした探偵小説が生み出された背景を考察。 ノクタンビュリスム、高等遊民と不況、セリバテール、パノプティコンなど、 高山宏の推理小説論『殺す・集める・読む』でも言及されていたモチーフが出てくるので、 ...
建築家であり作家でもある著者による、江戸川乱歩×都市論。 1920年代に東京を舞台にした探偵小説が生み出された背景を考察。 ノクタンビュリスム、高等遊民と不況、セリバテール、パノプティコンなど、 高山宏の推理小説論『殺す・集める・読む』でも言及されていたモチーフが出てくるので、 頭の中で相互に補完すると理解が深まりそう。 著者が執筆期(1980年代前半)に撮影した東京の街角と建物の写真も豊富に収録されているが、 それら1920~1930年代の佇まい、すなわちアール・デコ様式の建築は、 ほとんど取り壊されて姿を消したと、あとがきに記されているのが寂しい。 ⅰ章「感覚の分化と変質」 ①「D坂の殺人事件」の舞台背景。 散歩という趣味と喫茶店文化、都会に蝟集した地方出身者たちの希薄な人間関係。 ②「人間椅子」に見る家屋の和洋折衷。 半パブリックな洋間と、無防備に裸足で床に座り込むことの出来る和室の共存。 ⅱ章「大衆社会の快楽と窮乏」 ①「屋根裏の散歩者」の成立条件=倦怠と密室。 恒常的なハレの空間となった都市へ地方から吸い寄せられた人々が、 より強い刺激を求めるようになったこと、 また、鍵を掛けてプライバシーを守れるアパートが、この頃に出現したこと。 ②「二銭銅貨」に見る恐慌と個人の不如意。 人間が金に翻弄されることを衝いたプラクティカル・ジョーク。 ⅲ章「性の解放、抑圧の性」 ①「お勢登場」に見る大家族制の解体と大都市における核家族化の進行。 家に縛られながらも戸主権を行使できない、都会の核家族の主(夫)は、 心理的には独身者と変わらず、ふとしたきっかけで単身者の心理に退行してしまう。 ②「覆面の舞踏者」「一人二役」に描かれた夫婦の性愛。 家という制度の枠を取り払ったとき、夫婦の性愛の自然な形が明るみに出るが、 そこに現れるのは不本意ながらのスワッピングや別人に成りすます演技であり、 彼らは性知識の氾濫の中で想像力を駆使して、生活の貧しさから目を逸らしていた。 ⅳ章「追跡する私、逃走する私」 ①「押絵と旅する男」に描写された浅草の十二階 =凌雲閣を設計したエジンバラ出身の技師バルトンは写真家でもあった。 高層建築と写真術の共犯関係が、 高さによる視界の変化と窃視性による疑似体験の感覚を人々にもたらした。 ②「鏡地獄」における自己の姿を映す鏡の魔力、 他者との関係を自身の領内で完結させようとした「虫」の主人公、 資金を使い果たして本来の自分に立ち帰った「パノラマ島奇談」…… それらの作品に描かれているのは、 外部から自己を隔絶したいという願望と共存する、なお外部と繋がりたいという欲求だった。 ⅴ章「路地から大道へ」 ①乱歩式・東京の地理学。 関東大震災後、復興のために発足した同潤会による鉄筋コンクリート造のアパート群の立地と 「陰獣」大江春泥の転居先との近接=都市スラムが盛り場を核として成り立っていたこと。 「吸血鬼」においては犯人と探偵の行動半径が拡大し、しかも、中心地が西漸したが、 この重心の移動は、東京の中心が国鉄駅を持たなかった浅草から新宿に移った点と重なる。 ②「闇に蠢く」「一寸法師」に描かれた浅草界隈の大道芸・見世物小屋の世界は、 そうした娯楽を嗜好する労働者が鶴見や大森といった新たな工場地帯へ移動したため、 衰退していった。 ⅵ章「老人と少年(30年代から60年代へ)」 ①火葬が一般化し、公園墓地が出現して「死」が帰る「家」を喪失。 葬儀の短縮と墓地の公園化によって、死後の世界との関わりが薄れていった。 死へ近づきながら、唯一自由が利く眼で彼岸を見つめる「芋虫」の夫と、 現実が無意味だと悟ることを避ける妻。 ②少年誘拐 「少年探偵団シリーズ」の隆盛と最後の輝き。 時代の流れや街の様相の変化によって、少年たちを拐かし恐怖させるのは、謎の怪人ではなく、 彼らを取り込もうとする戦争、延いては受験戦争へと移り変わっていった。
Posted by 



