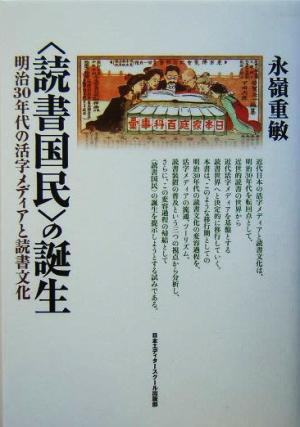
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1206-02-05
“読書国民"の誕生 明治30年代の活字メディアと読書文化
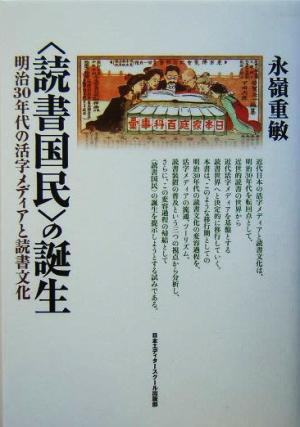
定価 ¥3,080
770円 定価より2,310円(75%)おトク
獲得ポイント7P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:12/13(土)~12/18(木)
店舗到着予定:12/13(土)~12/18(木)
店舗受取目安:12/13(土)~12/18(木)
店舗到着予定
12/13(土)~12/18

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
12/13(土)~12/18(木)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本エディタースクール出版部 |
| 発売年月日 | 2004/03/30 |
| JAN | 9784888883405 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
12/13(土)~12/18(木)
- 書籍
- 書籍
“読書国民"の誕生
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
“読書国民"の誕生
¥770
在庫あり
商品レビュー
3.8
4件のお客様レビュー
図書館より 前近代的な集団や共同体の音読から、個人的な黙読へどのように移っていったのか、明治30年代を中心に流通面、交通網、図書館サービスなどの視点から分析されています。 自分はちょうど読書文化の歴史を調べようと思い、この本を手にとったわけですが、近代的な読書の移り変わ...
図書館より 前近代的な集団や共同体の音読から、個人的な黙読へどのように移っていったのか、明治30年代を中心に流通面、交通網、図書館サービスなどの視点から分析されています。 自分はちょうど読書文化の歴史を調べようと思い、この本を手にとったわけですが、近代的な読書の移り変わりを知れるという点では、良書だったと思います。 今でこそ交通網が発達して、全国ほとんど同じ時間帯に同じものを読むことが可能になったわけですが、当時はなかなかそういうわけにもいかず、地方の読書人のために出版社などが通信図書館など、いろいろな取り組みをやっていたというのが面白かったです。 流通の発達した時代に生まれた読書好きの自分は幸せ者だったんだな、としみじみと思いました。
Posted by 
読書という視点に絞った日本近代史。明治30年代が大きな変換点になったことはやはり鉄道の普及が大きく、新聞・書籍の出版が全国規模、東京大阪に集約されていったということは理解しやすい。それと共に車中読者の誕生ということも確かに大きい。それまでは読書は音読が中心だったが、黙読に慣れない...
読書という視点に絞った日本近代史。明治30年代が大きな変換点になったことはやはり鉄道の普及が大きく、新聞・書籍の出版が全国規模、東京大阪に集約されていったということは理解しやすい。それと共に車中読者の誕生ということも確かに大きい。それまでは読書は音読が中心だったが、黙読に慣れないためのトラブル頻発というのも今から考えれば微笑ましい。そして新聞縦覧所、図書館、駅中新聞販売などが30年代をはさんで大転換をしていた時代とのこと。ある意味で今はそれに匹敵するネット化の変遷の時代かも知れない。三四郎が車中で新聞を借りて読むというのも時代を考えると面白い。
Posted by 
2012 2/5パワー・ブラウジング。筑波大学図書館情報学図書館で借りた。 読書史・メディア史関係の本でしばしば言及されていたので手にとって見た本。著者は先に『雑誌と読者の近代』も出している、図書館短大OB/図書館員。 第1部:活字メディアの全国流通網の形成、第2部:移動中・旅行...
2012 2/5パワー・ブラウジング。筑波大学図書館情報学図書館で借りた。 読書史・メディア史関係の本でしばしば言及されていたので手にとって見た本。著者は先に『雑誌と読者の近代』も出している、図書館短大OB/図書館員。 第1部:活字メディアの全国流通網の形成、第2部:移動中・旅行中の読書習慣・環境の形成とその影響、第3部:読書装置としての図書館の発見・普及と「図書館利用者公衆」の誕生について扱い、以上の帰結として生まれた<読書国民>について論じる。 図書館は「官」からの読書週間形成の試みとして位置づけられる。 アンダーソンの『想像の共同体』もしばしばひかれていて、いかに全国一斉の活字メディアの流通環境が全国的な問題を共有する「国民」を形作ることに貢献したか/その中での図書館、ということを考える上で非常に面白かった。最近関連するテーマを扱う本をしばしば読むが他にも手を出して行きたい。 以下、気になった部分のメモ。 ・第1章: ・新聞小説の存在・・・東京・大阪の新聞が地方読者を獲得する大きな武器に ・鉄道網の確立・・・全国紙・全国的流通へ ⇒・加えて新聞社間の市場競争の存在・・・地方読者が中央にダイレクトに接続される環境へ ⇒・地方共同体を超え、同レベルの問題関心を共有する<読書国民>に ←・そこから漏れる過疎地域/読書能力の低い人へのアプローチ・・・前者はいわゆるアウトリーチ、後者は図書館 ・第3章:移動中読書 ・黙読の普及につながる ・読者のイメージの再生産・・・他人の読書する姿を見ること ・国民の読書指標(本を読むための場所ではないところの読書状況の調査から国民水準を測る) ・第5章:国家はいかに「読書」の有用性を発見していくか ・明治初期における新聞読者創出の試みの失敗 ⇒・明治30年代・・・図書館へ ⇔・間の10-20年代は図書館は不振・・・公立図書館の廃館など ⇒・自由民権運動とも結びつく読書は政府にとって不都合? ・小学校卒業後、教育制度の枠外に置かれ読み書き能力を低下させていった人びとの発見 ⇒・いかにして知的水準を向上させるか? ⇒・「読書」の浮上へ ・「地方改良運動」 ⇒・無数の小図書館の設置 ⇒・結果として・・・「国民の統合」における読書の意義の発見
Posted by 
