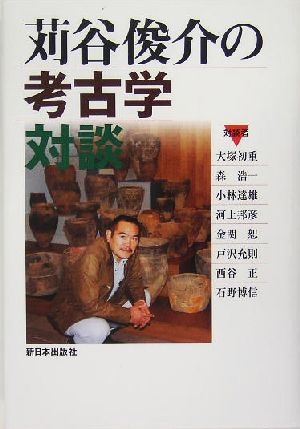
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-03-02
苅谷俊介の考古学対談
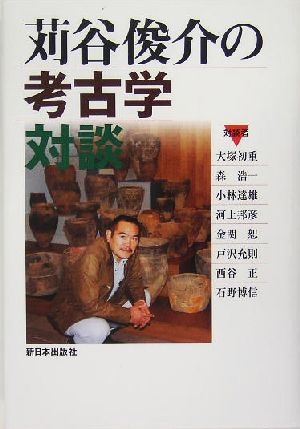
定価 ¥1,760
825円 定価より935円(53%)おトク
獲得ポイント7P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新日本出版社/ |
| 発売年月日 | 2005/05/25 |
| JAN | 9784406031622 |
- 書籍
- 書籍
苅谷俊介の考古学対談
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
苅谷俊介の考古学対談
¥825
在庫なし
商品レビュー
4
1件のお客様レビュー
俳優(悪役が比較的多い)苅谷俊介が、玄人はだしの考古学ファンだということは知っていたが、その実力は良く知らなかった。この本を読んでみて、玄人はだしではないと思った。アマチュアの顔をした専門家である。専門的知識は学位論文もものにしているだけあって、充分学者になれる。しかし、立場はあ...
俳優(悪役が比較的多い)苅谷俊介が、玄人はだしの考古学ファンだということは知っていたが、その実力は良く知らなかった。この本を読んでみて、玄人はだしではないと思った。アマチュアの顔をした専門家である。専門的知識は学位論文もものにしているだけあって、充分学者になれる。しかし、立場はあくまでもアマチュアだから、「箸墓は卑弥呼の墓だ」と断定してはばからない。 この本の凄いところは、1999年から2005年まで考古学者との対談を載せているのだが、所謂この時期の代表的な考古学者は網羅しているということである。成果を挙げ、名を上げた学者を此処までそろえる対談はこの本だけだろう。すこし、考古学をかじった人が見たならば、みんな肯くとおもう。大塚初重、森浩一、小林達雄、河上邦彦、金関恕、戸沢充則、西谷正、石野博信である。あと五年、いや二年企画が早ければ佐原真がこの列に加わっていたのは間違いない。対談の前半時期にはまだ存命だったのだが、佐原真はすい臓癌と闘っていたため、苅谷さんも対談は遠慮したのだろう。 以下、防備禄である。 ●(苅谷)まきむく石塚古墳は、もともとは陸橋部つきの円丘で、馬蹄形の周溝があって陸橋部を前方部として区画した。箸墓も方形壇付円丘であったものを前方後円形に作り変えたのではないか。箸墓の後円部から出てくる特殊器台型埴輪と前方部の二重口縁壺の年代差はお祭の時期の差である。したがって、二回目のお祭に前方部をつけたのだろう。 ●(苅谷)考古学の定義を変えて欲しい。過去の遺物から過去の人間の生活・文化様相を探る、というだけでなく、それを未来の人間の指針になる、未来にどう提言するのかが、考古学本来の目的であるということを新たに定義してくれると、遺物の見方も変わってくると思う。 ●(小林達雄)一万年以上続いた草創期から晩期まで全縄文時代を通じて、各地に約75の土器様式の盛行と消滅および変遷があります。その分布圏の境界を見ると、大枠で今日の東日本、西日本の区分や方言などの言葉遣いのまとまりと重なります。 ●(河上邦彦)昔は前期古墳の始まりを四世紀中ごろあるいは初めと考えていた。しかし、ここ二十年前くらいから三世紀末と考えるようになってきた。前期が百年以上続いたことになる。そのなかで「石囲い木槨」や変化にとんだ埋葬施設があった。ホノケ山が三世紀前半から中ごろまで、中山大塚が三世紀後半から末、黒塚が四世紀初頭に造られ、そのあとに下池山が築造されたらしい。 (苅谷)前期古墳の共通性は、長い木棺を使い、粘土床を使い、副葬品を大量に入れる。その前段階のホノケ山の木槨(石室の代わりに木で部屋を作り木棺をいれる)から石室に移るときになにか政治的なことがあったのですか。 (河上)その変化はどのような理由かは分かりませんが……。 (苅谷)そこに最古級の前方後円墳の箸墓古墳が卑弥呼の墓がらみで注目される(笑)。 (石上)全長280mの箸墓が最初の巨大古墳として現れます。それが三世紀中ごろから後半です。ホノケ山が80m。ですから箸墓を契機に埋葬施設が変わったとも考えられます。 (苅谷)その変化には、ヤマト政権の確立という大きな政治の動きが背景にあったのでしょう。 (石上)政権を「芽生えー発展ー確立」期があると考えると、箸墓段階は発展期に当る。ホノケ山はその前の段階に当る。 (苅谷)古墳時代は年代としてホノケ山の段階から始まったと考えていい。それがヤマト政権につなかっており、その墳墓の形式が全国に広がって統一されていくということですね。 ●(苅谷)邪馬台国が九州にあったとすると。 (石上)三世紀前半の九州には大きな墓がありません。ただ、福岡県糸島の平原遺跡から40枚の鏡が出ている。(略)鏡を持つ財力はあったが、墓を造るために人を動かす力がなかった。国としてのまとまりは、財力が高いところか、権力が大きいところか、どちらが国のまとまる要素があったか、私はハッキリしていると思いますが。 ●(西谷)共通する社会発展段階にあったものの、朝鮮半島まで来て倭国には入っていないものがあります。筆、青銅の容器、最近では光州の遺跡から木製品ー車輪が出て、注目されています。
Posted by 

