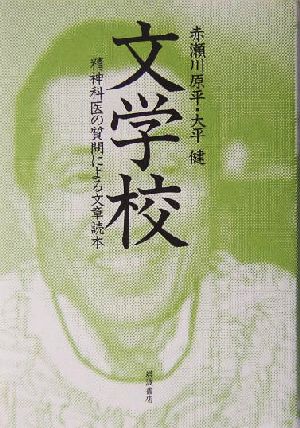
- 中古
- 書籍
- 書籍
文学校 精神科医の質問による文章読本
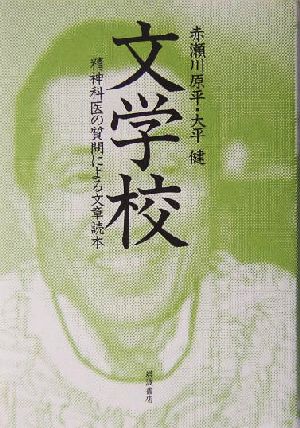
定価 ¥1,760
110円 定価より1,650円(93%)おトク
獲得ポイント1P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店/ |
| 発売年月日 | 2004/05/20 |
| JAN | 9784000246248 |
- 書籍
- 書籍
文学校
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
文学校
¥110
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
赤瀬川原平と精神科医大平健による対談形式の文章読本。 つるつるした文章だけでは読み進められない、という意見に賛成。読ませる側も読ませるために、読者の側に立ったりしながらも、自分のリズムも崩さない。迎合し過ぎない、そのさじ加減。 赤瀬川さんの作品を次から次へと読みたくなる本。
Posted by 
副題が「精神科医の質問による文章読本」。早い話が文章読本である。谷崎にも三島にも「文章読本」があるが、正直どれもつまらない。文章の好き嫌いは人それぞれ。その評価も時代や読者によって変わってくる。赤瀬川原平ともあろう人が、そんなありきたりな本をどうしてまた書こうと思ったのかと不思議...
副題が「精神科医の質問による文章読本」。早い話が文章読本である。谷崎にも三島にも「文章読本」があるが、正直どれもつまらない。文章の好き嫌いは人それぞれ。その評価も時代や読者によって変わってくる。赤瀬川原平ともあろう人が、そんなありきたりな本をどうしてまた書こうと思ったのかと不思議に思ったくらいだ。ところが、読んでみると、これはなかなかよくできている。文章の書き方はこうだと大上段に構えるのでなく、赤瀬川の書いた四冊の本を教材にして、精神科医でもある大平健が、著者である赤瀬川氏にお教えを乞うという私塾形式になっている。「文学校」というタイトルのつく所以だ。 上手下手を別にして、こうして書いている拙文もまた文章である。書いてみれば分かることだが、書きたいことと、書かれたこととの間にはずいぶん距離がある。ものを書こうと思う人なら誰もが皆その間を縮めようと努力するのだが、そこがいちばん難しい。言葉でものをとらえるということは、はたで見ているほど簡単なことではないのだ。どう書けば達意の名文になるのか。名文と言えるほどの文章でなくてもいい。少なくとも読んで面白い文章を書く秘訣はあるのか、もしあればめっけ物くらいの思いで読み始めた。 知ってのとおり、赤瀬川氏はただの物書きではない。千円札事件で世間を騒がせた前衛芸術家でもあり、「トマソン」で有名な路上観察学界の創始者のひとりでもある。最近ではライカ同盟という集団を立ち上げ、展覧会を開く写真家でもある。小説家としては尾辻克彦の筆名で、芥川賞も受賞している。一筋縄ではいかない曲者である。ところが、その曲者が書く文章はどれも読みやすくて面白い。しかも、面白いだけでなく筋が通っているというか発想が非凡で、こちらが見落としている勘所をきちっと押さえて教えてくれる。編集者というのはさすがにプロである。こういう人を先生にして文章術を語らせるというのは考えたものだ。 では、赤瀬川流の文章術とはいかなるものか。まずは自分が面白くなくてはならない。しかし、面白いだけでは駄目、栄養がないといけない。笑いに走らず、ほんとうの面白さを追求する。お得意の比喩ひとつとっても同じだ。表面的な類似に頼らず構造の本質に達するものを選ぶ。そういうとなんだか難しそうだが、読者に最短距離で伝わるものを選ぶから、実際に書かれたものは、なあんだというくらい腑に落ちるものになっている。 利休について語るところに真骨頂がある。利休は前衛である。ところが、茶道というものになるとそこに型ができ誰もが同じようにできるために言語化される必要がある。弟子の山上宗二が必要になる所以である。厳密に言語で説明できる部分と、言うに言えない沈黙でしか表すことのできない二つの焦点を持った楕円という構造がそこに生まれる。 かつて前衛であった赤瀬川は、マラソンでいえば先頭を切って走っていたトップランナーである。そのトップランナーが、次の集団の位置に身を置けるようになったことで、見えてきたのが楕円の構造だ。ものには型がある。文章でも視覚芸術でもそれは同じである。型をマスターした上でそれを毀して新しいものを生むことが大事なのだ。かつての前衛が危機感を持つのは、オウム事件のように市民社会に現れる突発的な事件が、前衛のコピーのように思われるからだ。 流行語大賞を受賞した「老人力」という一語からも分かるように、洒脱な脱力感のある文章が特徴的な赤瀬川氏に、前衛的な意識がいまだに濃厚であることが新鮮だった。利休でいながら山上宗二でもあるという二つの焦点を持つ存在。トップランナーとして走る前衛の意識と、その背中を次走者の集団の中からしっかり把握する批評的な視点とが複眼的なバランス感覚をもたらしているのである。 新聞小説として連載された『ゼロ発信』を、生徒の大平氏が読み取ってゆく「実実皮膜という虚構」の章は、エッセイ風の文章を書きながら、いつか小説を書きたいと思っている人には、うってつけの指南書になっている。構想メモをもとにしながら小説を書くことなんかできないという人にも、こんな小説なら書けるかもしれないという気にさせてくれるからだ。名づけて「非線形小説」。理科系で文章好きの人にもおすすめしたい。
Posted by 



