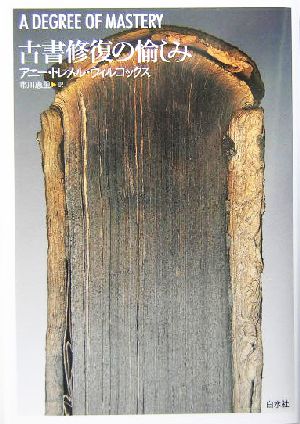
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
古書修復の愉しみ
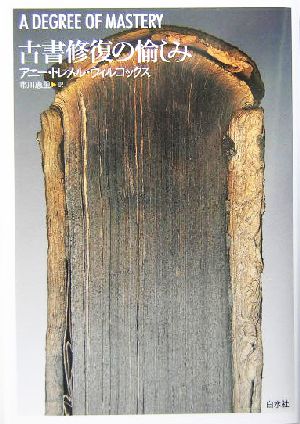
定価 ¥2,640
¥1,650 定価より990円(37%)おトク
獲得ポイント15P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
6/28(金)~7/3(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 白水社 |
| 発売年月日 | 2004/09/10 |
| JAN | 9784560047873 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
6/28(金)~7/3(水)
- 書籍
- 書籍
古書修復の愉しみ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
古書修復の愉しみ
¥1,650
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.5
4件のお客様レビュー
保存科学を専攻していた大学時代でさえ、本の保存修復について何か学ぶことはほとんどなく、その技術や処理方法はあるのはあるが、どのようなものかはわかりませんでした。 本書の訳者あとがきでも書籍修復が珍しい仕事であることが書かれていましたが、この本は修復技術のノウハウや、専門知識を深...
保存科学を専攻していた大学時代でさえ、本の保存修復について何か学ぶことはほとんどなく、その技術や処理方法はあるのはあるが、どのようなものかはわかりませんでした。 本書の訳者あとがきでも書籍修復が珍しい仕事であることが書かれていましたが、この本は修復技術のノウハウや、専門知識を深めるというような内容ではなく、書籍修復家の著者が日々の修復活動の中で感じたことや、どのような本をどう処理したのかというような日記的な内容になってします。 修復は今では大学などで専門的に学ぶことが主流みたいですが、著者の時代は修復家の元で弟子として学ぶことが多かったようで、師匠からは技術や知識だけなく修復に対する姿勢も学んだとあり、その姿勢を知る本として日本人が書いた本を紹介され、熟読したとあるのは興味深かったです。 文化財の保存修復の原則は現状をほとんど改変しない方法を選ぶと学んだ人は、一部、その修復でいいのか疑問に思うところがあるとおもいます。それは当時の考え方によって行われたもので、考え方の違いを知る上での関心も湧いてきます。
Posted by 
本好きと呼ばれる人には二種類ある。一つはいわゆる読書家。本を読むことが好きな人たちで、読むことさえできれば、文庫であろうが、借りた本であろうが関係ない。もう一方は、愛書家と呼ばれる人たち。無論読むのも好きだが、それだけにとどまらず本という物自体が気になってならない人々である。当然...
本好きと呼ばれる人には二種類ある。一つはいわゆる読書家。本を読むことが好きな人たちで、読むことさえできれば、文庫であろうが、借りた本であろうが関係ない。もう一方は、愛書家と呼ばれる人たち。無論読むのも好きだが、それだけにとどまらず本という物自体が気になってならない人々である。当然、装幀、造本に煩い。本好きの多くは、この二極のどこかに位置しているはずだ。私自身は、どちらかと言えば、後者よりか。本という物の成り立ちや作りに興味がある。 京極夏彦の本でお馴染みの中禅寺秋彦は古書店主だが、扱うのは主に和綴じ本。衒学趣味を満足させるには古書店主の探偵というのはいい設定だが、資料的価値はともかく、本としての堅牢さ、美観という点では、洋書に一歩譲るのではないだろうか。しかし、その洋書も時の浸食には勝てない。洋の東西を問わず古書は傷みやすい。そこで、古書の修復を専門に担当するブックアーティストと呼ばれる人が登場してくる。 著者は大学の出版局で製本を学んでいるときに、古書修復の第一人者であるウィリアム・アンソニーに出会う。「一冊ずつ違う本を作る方が、そっくり同じ本を二百五十冊をつくるよりはるかにいい」と、考えた著者はビルに弟子入りし、古書修復のノウハウを直接伝授されるという幸運にめぐりあう。敬愛する師との出会いから別れまでを、実際に担当した古書修復の現場報告を交えながら綴ったのが、本書である。優れた仕事でありながら、あまり世間の注目を浴びない世界に読者を導いてくれる貴重な一冊といえるだろう。 実際、古書の修復というものがどのようにして行われているのか、著者は自分の担当した『ロシア遠征詳述』を例に、初心者にも理解できるように、丁寧に解説してくれている。道具や用紙の準備から薬剤の製法まで、これを読めば、そのおおよそは分かるのではないか。何よりも大切なことは、無味乾燥になりがちな解説書めいたところがなく、はじめて出会った古書修復にかける著者の意気込みや、失敗したときの落胆ぶり、師の支えによって見事成功したときの喜びが、ある時は初々しく、またある日には自信に満ちて、こちらに伝わってくるその筆致である。 仕事の上でも人間的にも尊敬できる師と過ごす毎日。気心許せる仲間とのふれあい。時には、講師として出かけたワークショップで、騒ぐ児童に疲労困憊したりもするが、適切な助言と見本を与えてくれる師のおかげで、次第に独り立ちしてゆく著者の姿はまぶしいくらいだ。現代にあっては、存在すら危ぶまれる職人の徒弟制度というものに対するちょっと面はゆいほどの傾倒ぶりは、日本人職人オーダテ(大館年男)の著書の引用から熱く伝わってくる。 楮(こうぞ)紙や寒冷紗といった紙だけでなく、他の用途で作られた道具を借用して製本用の道具にしている古書修復の世界では、鉋や砥石その他、日本の道具が多く使われている。国連やオリンピックで騒がれるより、こういうところで頼りにされる日本という存在に心惹かれるものがある。手仕事の世界では、まだまだ貢献できることがあるのがうれしい。 本を全部ばらして、紙を薬品につけて水洗いをし、中和させることで酸性化を止めたり、ポリエステルフィルムの袋で挟み込んで再び製本したり、と古書修復の現場でとられている作業の実態には、驚かされることも多い。同じ出版社から先に出ている『本棚の歴史』と併せ読まれると一段と興趣が増すことだろう。読書の秋にお薦めしたい一冊。
Posted by 
物語に出てくる古書修復家の皆さんの、本と向き合う姿勢に強く感銘を受けます。 絶版のようです。なんとしても手元に置いておきたい一冊。
Posted by 
