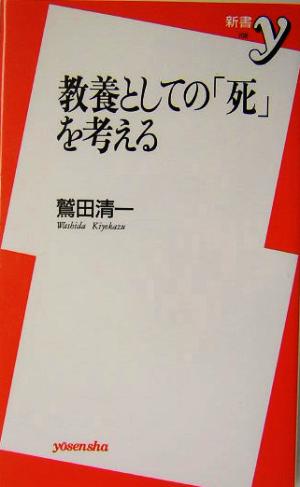
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-30-01
教養としての「死」を考える 新書y
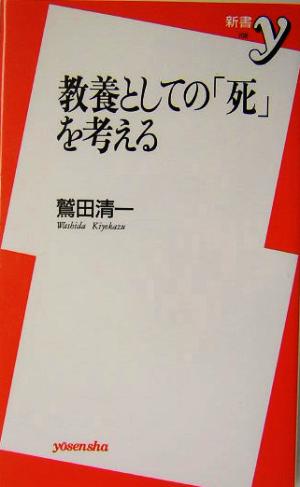
定価 ¥792
220円 定価より572円(72%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 洋泉社 |
| 発売年月日 | 2004/04/21 |
| JAN | 9784896918083 |
- 書籍
- 新書
教養としての「死」を考える
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
教養としての「死」を考える
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.2
6件のお客様レビュー
哲学的な意味を見つける 死と対極にあるもの 生・性 死の過程に立ち会うことがなくなった 湯灌など専門の業者に任されることが多い 死が おぞましいのは 名前がないから 死の事実があるだけ 死は隠されている 現実感覚が変わり始めている 生命のリレーの持つ軽薄さ 生...
哲学的な意味を見つける 死と対極にあるもの 生・性 死の過程に立ち会うことがなくなった 湯灌など専門の業者に任されることが多い 死が おぞましいのは 名前がないから 死の事実があるだけ 死は隠されている 現実感覚が変わり始めている 生命のリレーの持つ軽薄さ 生命倫理の胡散臭さ
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
久々に鷲田清一さんの本を。本書は何度も目にしていて、気になってはいたけど、読めずにいた本。 内容をおおざっぱに要約してみる。うまくまとめられていないのは力不足。 近代以降、死が自分たちのものではなくなっている。死を確認するのは畳の上ではなく病院のベッドの上で、器械を見た医師の言葉からである。そもそも死のみに限った話ではない。死に化粧が施された遺体と対面したり、胎脂が取り除かれた赤ん坊と対面するのが例として挙げられる。現在の我々は生死に触れ合う機会が少なくなっている。 また、若い世代の死に対する捉え方は変化してきている。死は個人のもの、と考えられているのだ。その原因は、条件付きでしか自分を認めてもらえず、他者から許されている感覚というものが感じられないからである。元来、自分は他者からの眼差しによって「宛名」として存在しうる、他者との関係の中のものであり、完全に独立したものであるわけではない。死とは、そういった他者の眼差しがなくなることである。死というものを意識するときこそ、他者の存在が浮き上がってくるのである。 そういった感覚が薄れてしまってきた今、堕胎や人工授精などがテクノロジーの手により認められている。そう考える背景には自分の身体を自分が所有しているという感覚があり、また身体をパーツに分けられると考えていることがある。そういった認識が蔓延る今唱えられる生命倫理は、倫理ではなくガイドラインや法律といった約束事に過ぎず、そもそも治療していいのかだとかを考える必要がある。 今の若者は、頑固に自分を保つことよりも場に応じてキャラを変えることができることのほうを好むという。しかし、古いものが壊れるのは必然というバブル崩壊のなか育ったことを考えると、一概に非難するわけにもいかない。このように、いることといないことの紙一重で成り立っている現代においては、人称の死では語りえない死がリアルになっているのかもしれない。 我々は身体を所有できるものと考えるのではなく、身体は自分と密着して切り離せないものであることを自覚し 、隠されている生と死は人と人との間で起こる出来事だと再確認しなければならない。 …やはり、鷲田さん。身体論だな、と思った。 自分を他者の「宛名」としてとらえること、眼差す対象がいなくなることを死ととらえることなど、独特な考え方に感銘を受けた。 中でも、文体について述べている部分が印象にのこった。年を経るにつれ宛先となる他者の影が変わるのだから、文体が変わるのも自然、という考え方にははっとさせられた。しかし、コミュニケーションツールが多様化する現代においては書き手自信も誰を「宛名」としているのかが分からなくなってきてはいないだろうか。SNSの普及などで、関わりを持つ相手は匿名の他者にまで広がっていることを考えると、自己の文体を形成する要素は複雑化してきていると感じた。 一点だけわからない点があった。門案について述べているところだが、「問うものと問いかける内容は一体化しています。同じように、問われるものと問いかけられた内容も一体化しています。」の部分のみ、どうも一読しただけでは理解ができない。 私の理解不足なだけかもしれないが。
Posted by 
むー、わかったようでわからなかった本。 新書の体裁やけど、かなり硬質な文章でした。 鷲田さんの臨床哲学の本業はこういう話なんやろうな、と思いました。 生と死が日常生活から遠ざけられている、という本書の主題、そして人格をいろんな場によって変えていくというのは当然だ、という話が印象的...
むー、わかったようでわからなかった本。 新書の体裁やけど、かなり硬質な文章でした。 鷲田さんの臨床哲学の本業はこういう話なんやろうな、と思いました。 生と死が日常生活から遠ざけられている、という本書の主題、そして人格をいろんな場によって変えていくというのは当然だ、という話が印象的でした。 鷲田さんの著書をもっと読んで感覚をつかんでから、またチャレンジしたい本です。
Posted by 



