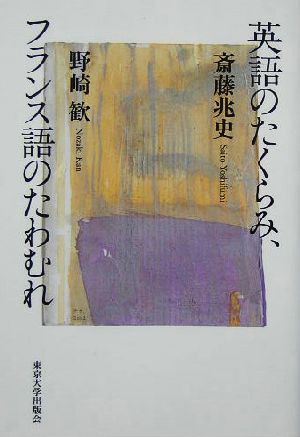
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
英語のたくらみ、フランス語のたわむれ
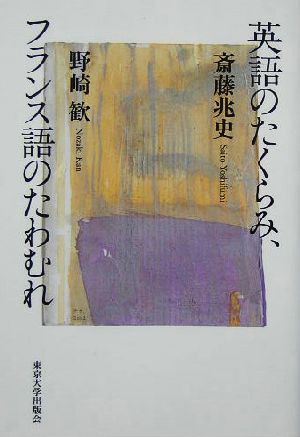
定価 ¥2,090
220円 定価より1,870円(89%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
7/2(火)~7/7(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東京大学出版会/ |
| 発売年月日 | 2004/07/20 |
| JAN | 9784130830393 |
- 書籍
- 書籍
英語のたくらみ、フランス語のたわむれ
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
英語のたくらみ、フランス語のたわむれ
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.7
8件のお客様レビュー
英文学者と仏文学者の、語学学習から文学研究や翻訳までを扱った対談集。仏文専攻で英米文学好きな私は、楽しめないわけがない本です。 文学論は専門的だったので、なかなか理解はしづらかったのですが、大学の授業を思い出すようなトピック(バタイユ、ロラン・バルト、サイード、デリダなんか)が...
英文学者と仏文学者の、語学学習から文学研究や翻訳までを扱った対談集。仏文専攻で英米文学好きな私は、楽しめないわけがない本です。 文学論は専門的だったので、なかなか理解はしづらかったのですが、大学の授業を思い出すようなトピック(バタイユ、ロラン・バルト、サイード、デリダなんか)が多く、今と当時の思想の乖離を甘酸っぱく受け止めました。高尚なお話がたくさんあって、こういうことを日々考えている人がいるんだなあ、と思い出させてくれたことも、読んでよかったと思う理由の一つです。また、私が文学、中でも仏文学を専攻した理由はこれまでうまく説明できなかったのですが、仏文学研究の第一人者である野崎先生の言葉の中に見つけることができました。 「医者は目の前の患者を直せるけど、文学は万人を癒せるんだ!」と斎藤先生が医者である奥様におっしゃったそうですが、その心意気はまぶしい限りです。いや、これ本当に。 ただ、お二人が若いせいか、ちょっと議論に深みが足りないような、許容度が小さいような。。『アカデミズム is NO.1、No 実利主義』という枠組みの中で、似た環境に生きるお二人が気持ちよくオタク話を喋っているような印象も受けました。 少ないながらも同意できなかったのは、一応以下の点。 ・翻訳は研究者がすべき(強く断言はしていなかったのですが) ・翻訳者は黒子に徹するべき(一方で翻案も支持していて、境界が明示されなかった) ・外国語は文法をちゃんと理解した上で、良質な文学を精読して身につけるべき(たしかにそれは理想。でも実際、それができないけど外国語を使う必要に迫られた人には簡便メソッドが流行るんでしょう。語学にそこまで心血注げるビジネスマンは少ないと思う) ちょっと保守的な感じはありましたが、東大の文学講座(濃縮版)を受けた気分になれるので、とてもお得で勉強になる本です。これが理解できるくらいに文学的教養をつけるのが目標です。
Posted by 
翻訳論、語学論、比較文学論として面白く、役に立つ小ネタ満載の対談書。仏文と英文の違いとして「英文学は語学の延長として読めるが、フランス語はそうはいかない」というのはなるほどと思った。ただ、「翻訳が翻訳されることはないというパラドックス」については、重訳や別言語訳の参照といういまだ...
翻訳論、語学論、比較文学論として面白く、役に立つ小ネタ満載の対談書。仏文と英文の違いとして「英文学は語学の延長として読めるが、フランス語はそうはいかない」というのはなるほどと思った。ただ、「翻訳が翻訳されることはないというパラドックス」については、重訳や別言語訳の参照といういまだにさかんな(!)事象を見て見ぬふりしている。 「文学は何のためにあるか」というお決まりの問いに対する対処の仕方を随所で講じている。東大の先生はさすが頭がいい。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
語学、翻訳、文学の3つの主題を軸とした対談。 3つ全てに興味津々の私のような人間にはぴったりの本だった。 さて、本書では「実用英語」「コミュニケーション英語」偏重の教育を目指す動きに警鐘が鳴らされている。(確かに大学に在学する身としてそうした潮流は強く感じる。実際に科学論文とプレゼンのための英語の講義などもあるわけだし。) でも個人的には、この傾向はある程度仕方ないことなのかなと思った。勿論、本当に外国語が好きで習得したいという熱意がすべての学生にあるのなら、著者らが言うような教育のあり方が望ましいのは頷ける。しかし、実際はそうではないのだから。 彼らのうち相当数は英語なんて嫌いだし、必要最小限のこと(著者らの目からすれば不十分だろうが)しか勉強したくないと思っているだろう。大抵の者は文学に興味はないわけで、訳読なんて真面目にやるとは思えない(というか実際に皆真面目にやっていない)。在学中からやれ就職だ資格だと慌ただしい中で、「実用的」でないものは多くの学生には訴えかけないのが現状だ。 そんな中で現行のような教育システムになってしまうのは当然の成り行きなのではないか。これは教育界というよりは社会全体の風潮の問題だという気がする。 ・・・でもね、やっぱり理想はお二人の主張なんだよなぁ。そういう授業じゃなけりゃ、語学・文学・翻訳の本当の面白さ、奥深さというものは伝えられないよね。難しい。 全体を通して印象に残ったのは、フランス語に魅せられた数学科の学生のエピソード。私自身理系に属しながら語学・文学にはまりこんでしまい、周囲の友達も理数にしか興味のない人が多く寂しい生活を送っている中で、こういう学生さんの存在を知って訳もなく嬉しいという(笑)彼の発言にはことごとく共感してしまった。ぜひお近づきになりたいくらい。
Posted by 

