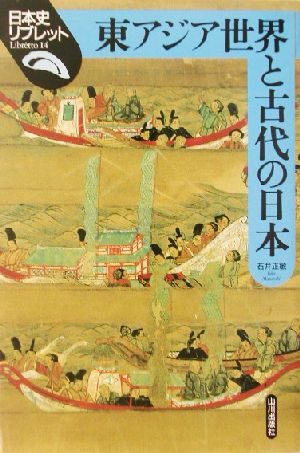
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-04
東アジア世界と古代の日本 日本史リブレット14
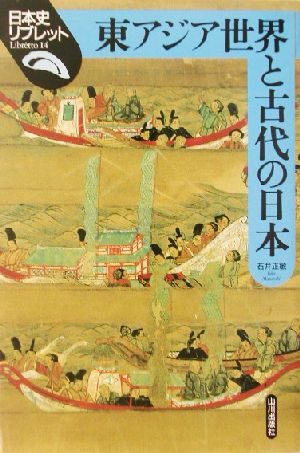
定価 ¥880
605円 定価より275円(31%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 山川出版社/ |
| 発売年月日 | 2003/05/30 |
| JAN | 9784634541405 |
- 書籍
- 書籍
東アジア世界と古代の日本
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
東アジア世界と古代の日本
¥605
在庫なし
商品レビュー
4.5
2件のお客様レビュー
中華思想は中原にはじまり、アジア各地に広がっていったイメージで、中国が力を落とせば周辺の小国たちが中華思想の後継者として振る舞い出すというイメージだったけれども、日本も例外ではなかったか。 中華思想というものは本当に、どの国が持っていてもろくでもない。 こういう本は、読み始める...
中華思想は中原にはじまり、アジア各地に広がっていったイメージで、中国が力を落とせば周辺の小国たちが中華思想の後継者として振る舞い出すというイメージだったけれども、日本も例外ではなかったか。 中華思想というものは本当に、どの国が持っていてもろくでもない。 こういう本は、読み始めるまでが長いけれど、読み始めてからは面白くってあっという間だ。 日本の歴史は中国や朝鮮半島を中心とする地域の動静と深くかかわりながら推移してきた。 「日本の王権が古代国家の形成に向けた歩み始めたころ(5世紀)からもっともエネルギーをそそいだのは朝鮮諸国との政治的位置関係であった。日本外交の政治的関心はつねに朝鮮諸国にあり、親羅・百済・高句麗よりも上位にありたいとの認識が根本にあった。倭の五王以来およそ一世紀の空白をへて、隋の時代にふたたび中国外交を再開すると、たちまち問題となったのが、607(推古15)年に遣隋使小野妹子が進めた「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙なきや」云々という国書である(『隋書』倭国伝)。 隋は別格と認識しながらも天子を称して対等を求める外交を展開しようとしたのは、すでに隋に冊封されている朝鮮諸国よりも上位にありたいとする目的からである。これは隋を倒して興った唐に対しても同様で、630(舒明2)年の日本の最初の遣唐使犬上御田鍬(いぬがみのみたすき)を送って来日した唐使高表仁(こうひょうじん)が、「日本の王子(もしくは王)と礼を争い」使命を果たせずに帰国したという(『旧唐書』倭国伝、『新唐書』日本国伝)、第一次日唐交渉決裂の原因は、冊封を行おうとする唐使と、それを拒否する日本側とのトラブルによるものとみられている。」p.005-006 「もちろん古代の日本・日本人が中国・朝鮮以外の地域とまったく交流がなかったわけではない。日本の人びとは限られた場面ではあるが、より広い世界にもふれる機会はあった。すでに本文において、天平勝宝度遣唐使が唐の朝廷で席次を争った場には新羅使だけでなく、吐蕃使や大食使も列席していたことを紹介し、また三河の国に天竺人が漂着し、綿種をもたらしたことにもふれた。このほか、天平度の遣唐使にともなわれて「ペルシア人」が来日し、鑑真一行のなかには「如宝」という僧がいた。のち還俗して安如宝と名乗っている。その姓からみて中央アジアのオアシス国家の一つでシルクロードの要衝を占めた安国(ブハラ)の出身とみられる。ペルシア人・ソグド人が日本にやってきているのである。またインド出身の僧や東南アジア林邑国出身の僧も渡来している。遣唐使は長安・揚州など各地で碧眼・紅毛の人々を実際に目にしていたであろうが、733(天平5)年入唐の遣唐使の一員で、唐からの帰途遭難して今日のベトナム方面に漂着し、ふたたび唐に戻って渤海経由で帰国した平郡広成(へぐりのひろなり)のような人物もいた。こうした異国人の渡来や遣唐使らの体験談は、古代日本人の地理的・文化的世界観を広げ、書物だけの知識を疑似体験する機会として重要な意味を持ったものと思われる。外交といった直接の交流はないものの、古代の日本人は確実に「東アジア世界」を認識していたにちがいない。十世紀末~十一世紀初めごろの成立とされる『宇津保物語』では主人公俊蔭(としかげ)が遣唐使の一員として入党の途中遭難して「波斯国(ペルシア)」に漂着する一説が語られるまでになるのである。」p.90-91
Posted by 
古代東アジアと日本の間でやりくりされたヒト、モノの概観。 奈良から平安がメイン。 遣唐使はもちろん、渤海使、古代の国家の情報管理や外国使節への対処の仕方など。
Posted by 



