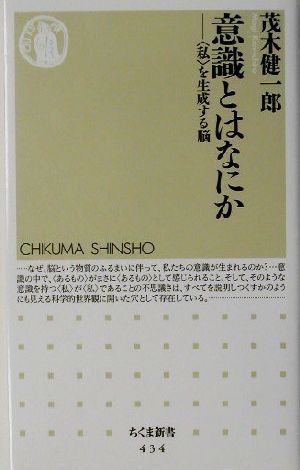
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
意識とはなにか 「私」を生成する脳 ちくま新書
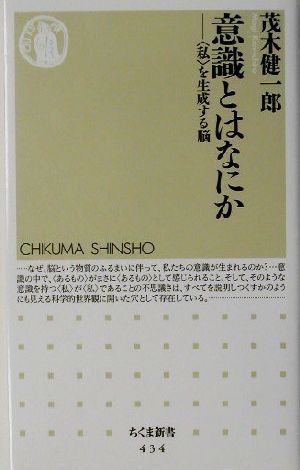
定価 ¥880
110円 定価より770円(87%)おトク
獲得ポイント1P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
11/25(月)~11/30(土)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房/ |
| 発売年月日 | 2003/10/10 |
| JAN | 9784480061348 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
11/25(月)~11/30(土)
- 書籍
- 新書
意識とはなにか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
意識とはなにか
¥110
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.2
21件のお客様レビュー
主に認知に関する議論が多い。例えば、小鳥のさえずりや鮮やかな赤を、いかにして脳でユニークなもの(クオリア)として認識しているかという問いについて議論している。脳の解明はやはり難しく、1か0かではないところに科学らしくない科学といった印象を受ける。学問もヒトに近づけば近づくほど白黒...
主に認知に関する議論が多い。例えば、小鳥のさえずりや鮮やかな赤を、いかにして脳でユニークなもの(クオリア)として認識しているかという問いについて議論している。脳の解明はやはり難しく、1か0かではないところに科学らしくない科学といった印象を受ける。学問もヒトに近づけば近づくほど白黒はっきりできないものが多いように思う。もちろん共通言語として論理的に考えることはツールとして必要だが、世の中すべてを単純化して見てしまうことは、あらゆる弊害を生む気がする。もしかするとICTの限界はその辺りにあるのかも?
Posted by 
最初のうちは、分かっていながらもなかなか言葉に出来ないことが、”クオリア”として表現されることで、スッキリした気分を味わえた。読み進むにつれて、同意反復が気になってくるというか、”クオリア”に関する解釈を、ひたすら言葉を変えて繰り返しているだけに思えて、だんだん辛くなってきました...
最初のうちは、分かっていながらもなかなか言葉に出来ないことが、”クオリア”として表現されることで、スッキリした気分を味わえた。読み進むにつれて、同意反復が気になってくるというか、”クオリア”に関する解釈を、ひたすら言葉を変えて繰り返しているだけに思えて、だんだん辛くなってきました。もう少し厚みが欲しいというか、一冊の書として纏めるには薄いというか。正直、学術論文くらいの長さで纏まっていた方が、インパクトも高まると思うし、ニュアンスもより良く伝わったんじゃないか、と思えてしまいました。
Posted by 
「クオリア」ということばが何度も登場する。本書のテーマになっていることばだ。しかし、どうもこの言葉の意味をうまく人に説明することができない。自分で使うこともできない。本書によると、クオリアとはもともとは「質」を表すラテン語で、心の中で感じるさまざまな質感を表すことばとして定着して...
「クオリア」ということばが何度も登場する。本書のテーマになっていることばだ。しかし、どうもこの言葉の意味をうまく人に説明することができない。自分で使うこともできない。本書によると、クオリアとはもともとは「質」を表すラテン語で、心の中で感じるさまざまな質感を表すことばとして定着してきた。では「質感」とは何か。いろいろな具体例で説明がなされているが、私なりに解釈をすると、「苦い」ということば1つを取ってみても、コーヒーは苦くて好きになれないという人もいるだろうし、その苦さが好きだという人もいるだろう。同じことばでもそれぞれの人にとっての感じ方は違う。もっと言うと、赤いリンゴを見たとき、私とあなたで本当に同じ赤色を感じているのだろうか。それまでに生活してきた文化的な背景によっても感じ方は違ってくるのではないか。そういったそれぞれの意識の持ち方が「クオリア」となるのだろう。しかしそんなことを一々考えていたのでは話が進まない。だから皆が同じように感じているとして話を進めてしまう。ちょっと立ち止まって考えると、それは突然「難しい問題」として目の前に現れてしまう。それは哲学の問題だ。そんなことは科学としては扱えない。科学は客観的に数値で扱えるものしか扱わない。ところが、それが最近少し変わりつつあるのだそうだ。脳の研究者の中で「意識」ということを扱うのはタブー視(良いことではないと)されてきた。技術の進歩で、何かをしているとき、何かを感じているとき、脳の中のどこがはたらいているかを突きとめることが出きるようになってきた。人間の「意識」を科学として扱うことが出きるようになってきたというのだ。20世紀は物理学の時代だと言われた。21世紀は生物学の時代、特に脳研究の時代と考えられる。本書のテーマはしばらく大きく発展していくに違いない。しかし、今のところ私には、本書の内容はボヤーとしか感じることができない。ちょうど養老先生と本書の著者との対談が出版された。それも読みながらさらに考えてみたい。
Posted by 


