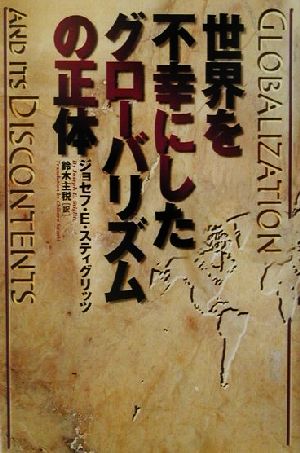
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-01-05
世界を不幸にしたグローバリズムの正体
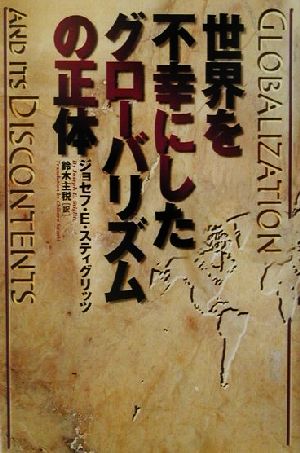
定価 ¥1,980
385円 定価より1,595円(80%)おトク
獲得ポイント3P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 徳間書店/ |
| 発売年月日 | 2002/05/31 |
| JAN | 9784198615192 |
- 書籍
- 書籍
世界を不幸にしたグローバリズムの正体
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
世界を不幸にしたグローバリズムの正体
¥385
在庫なし
商品レビュー
4
30件のお客様レビュー
世界中に貧困を作り出したIMFの罪を公開する本。 著者が高名な経済学者。 2章まで読んで挫折。 似たような内容の繰り返しであり、訳が非常に読みづらかった。 2000年頃に書かれた本で、現在ではIMFも変わっているかも知れないが、当時は相当酷いものだったらしい。 最後まで読んでいな...
世界中に貧困を作り出したIMFの罪を公開する本。 著者が高名な経済学者。 2章まで読んで挫折。 似たような内容の繰り返しであり、訳が非常に読みづらかった。 2000年頃に書かれた本で、現在ではIMFも変わっているかも知れないが、当時は相当酷いものだったらしい。 最後まで読んでいないが恐れずに要約すると、IMFは時代遅れの政策を貧困国に押し付けて悲劇を作り出している、ということ。 世界の貧困問題について知りたい方におすすめです。
Posted by 
ノーベル経済学賞受賞者による国際経済機関(主にIMF)の批判。世界銀行の要職にあったこともある著者から見たIMFの問題について多く書かれている。 骨子としては、 ・戦後復興のために作られた世界銀行(開発)とIMF(国際金融の安定)が時代の変遷とともに拠出国への責任をほとんど負わ...
ノーベル経済学賞受賞者による国際経済機関(主にIMF)の批判。世界銀行の要職にあったこともある著者から見たIMFの問題について多く書かれている。 骨子としては、 ・戦後復興のために作られた世界銀行(開発)とIMF(国際金融の安定)が時代の変遷とともに拠出国への責任をほとんど負わない官僚機構、唯一拒否権を持つ米国の政治意図の擁護者になってしまった。 ・IMFは融資国に「融資条件」として、融資返済のための緊縮財政、為替レートの維持など、経済学的な理論とはかけ離れた対応を迫る。 緊縮財政は危機にある経済の活力を失わせ、通貨防衛は輸出競争力の改善による景気後退からのリカバリーを邪魔する。 ・急速な市場開放は現地企業の成長機会を奪う。中国のような工業化がスムーズに進展した国はおろか、19世紀の欧米ですら他国の産品からの保護を与えながら自国産業を成長させて来たのだ。「市場開放」は然るべきフェーズで行われるてこそ消費者の利益になる。 ・ガバナンス、説明責任、現地主義の徹底により国際機関の失墜した信用を取り戻す必要がある。 というもの。 2002年に出版された古い本だが、80年代、90年代に国際社会が新興国にどういう対応をしたのかをしる上では今でも有用な本だ。(学生時代に講義の副読本になっていて読んでいた友人も多かった。) 特に「IMFにより独裁政権に貸し出された融資を返済するために多くの新興国が苦しみ成長機会を失っている」という文脈は、近年の著書にも多く取り上げられている。信用と貨幣の歴史を紐解いたデヴィッド・グレーバーの「負債論」や、デフォルトした国会債務を安価に取得し裁判で履行を求めるファンドをモデルにした黒木亮「国家とハイエナ」などがそうだ。
Posted by 
「傲慢な援助」を読んだのをきっかけに、中途で放り出していたのを読み直す。 イースタリーがIMF含む援助機関の主に官僚主義の側面を批判していたのに対し、スティグリッツはIMFのイデオロギーを批判の中心にしている。しかし両者の議論はかなりの部分で重なり合うように思う。乱暴に要約する...
「傲慢な援助」を読んだのをきっかけに、中途で放り出していたのを読み直す。 イースタリーがIMF含む援助機関の主に官僚主義の側面を批判していたのに対し、スティグリッツはIMFのイデオロギーを批判の中心にしている。しかし両者の議論はかなりの部分で重なり合うように思う。乱暴に要約すると、イデオロギーから入らずに複雑な現場の状況を直視しろよ、ということではないか。改革の速度や順序が肝腎であること、法制度などの社会資本の不可欠さが説かれている。 題名や帯を見ていると反グローバリズムの本みたいだが、スティグリッツは原則的にはグローバリゼーションに賛成、もちろん市場経済を重視している。批判しているのは、あくまでIMF・米財務省の自由主義を唱えながらもイデオロギーに凝り固まった方法論だ。 IMF・米財務省は金融危機により景気後退に見舞われた東南アジア諸国に対して金融引き締めを主張した。昨今の欧州やアメリカの風景と重なるところがあるか?他国に向かって吐き出していた毒が身中に回ったとも見えるが。。。米国金融界と行政の回転ドアに対する批判もほのめかす程度だがされている。 IMFの融資が、危機に陥った国よりも債権者への救済として働いており、それがモラルハザードを引き起こした側面があったと。いわゆる新自由主義や財政引き締め主義は、金貸し資本主義なのか。縁故資本主義よりそっちが問題であろうと読める。 意味の取りにくいところが結構あった。訳語の選択が微妙だったり(「少数の株主を保護する」?「の」は要らない)。
Posted by 



