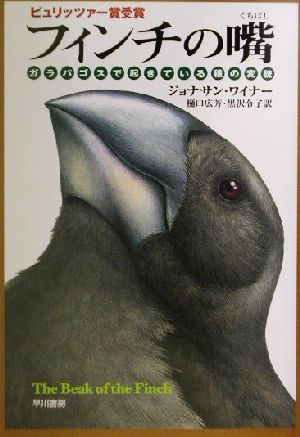
- 中古
- 書籍
- 文庫
フィンチの嘴 ガラパゴスで起きている種の変貌 ハヤカワ文庫NF
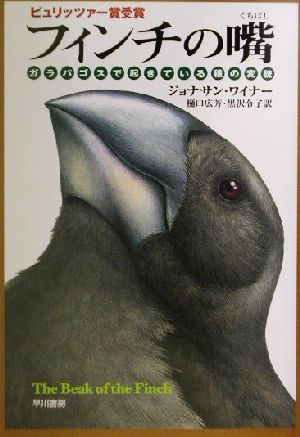
定価 ¥1,034
220円 定価より814円(78%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 早川書房/ |
| 発売年月日 | 2001/11/30 |
| JAN | 9784150502607 |
- 書籍
- 文庫
フィンチの嘴
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
フィンチの嘴
¥220
在庫なし
商品レビュー
4.1
16件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・ダーウィンの唱えた進化論とは、自然選択の必然的結果であって、その過程を想定するのは難しい=進化過程の観察は不可能とされていた。 ・ガラパゴス島のフィンチという鳥を研究するグラント夫婦は、フィンチは嘴の大きさによって好んで食べる種子の大きさが異なる事を観察。 ・ガラパゴス島の気候変動の際に、フィンチの採食する種子に偏りが発生し、それに伴って種子の大きさに嘴の大きさが合わないフィンチは個体数を減らしていった。 ・世代を経ると、上記の現象の結果、フィンチの嘴サイズに偏りが生じ、それは進化の過程に他ならないと言う。 ・フィンチの他にも農薬に耐性を獲得した虫や、ワクチンへの耐性の付いたウイルスも例に挙げられる。我々の身の回りでも目を凝らせば進化は観察出来るのである。
Posted by 
ガラパゴス諸島で20年の長きにわたりガラパゴスフィンチの体のサイズとその生存率を丹念に追った研究者夫妻のノンフィクション。非常に興味を惹かれる書き方で、スイスイと読み進められる。 ガラパゴス諸島は独自に進化を遂げた野生動物の楽園としてよく知られているが、その夫妻は孤立して人も近づ...
ガラパゴス諸島で20年の長きにわたりガラパゴスフィンチの体のサイズとその生存率を丹念に追った研究者夫妻のノンフィクション。非常に興味を惹かれる書き方で、スイスイと読み進められる。 ガラパゴス諸島は独自に進化を遂げた野生動物の楽園としてよく知られているが、その夫妻は孤立して人も近づかない離島の鳥に注目した。そこでは餌となるサボテンやハマビシなどの植物とフィンチたちだけのほぼ孤立した環境で、生態学の研究を行うには理想的環境であったからだ。彼らはそこで、ほんの0.5ミリ程度の嘴のサイズの違いがフィンチの生存率に大きく関係していることを見出した。旱魃で、食べられずに残されたのはサボテンの固い種子だけという時期は、長い嘴が生存に圧倒的に有利にはたらく。ただ長ければよいというものではなく、雨量が多く、柔らかい種子が大量に利用できるときは逆に短めの嘴が有利になるなど、環境変化に応じて、生き残るフィンチの体の特徴は敏感に変動する。 その差が大きくなったときに、さらに別の環境要因の変化が進化の「山」を引き離す方向に働けば、まさに我々が別種として認識する種が誕生するのだろう。 ただ、ここで上げられるフィンチの例は、まだ種として確立できないレベルの中での変動であり、そこから飛び出して種として独立するところを観察で見出すのはやはり難しいと感じる。極端な話をすると、チンパンジーを数世代飼育しても人間にはならないし、逆もしかり。 また、本書では、フィンチの嘴の長さの変化をもって進化が見られるとしているが、これは実際のところDNAの配列の変化まで伴うものなのだろうか? また、ほかの例として挙げられている、捕食者の存在による魚の模様、色の変化についても、数世代で起こる変動は我々が通常抱く「進化」という概念と本当に適合するのか、そしてDNAの配列変化があるのかそのあたりは疑問が残った。 夫妻が研究を行った70-80年代はまだまだ分子生物学は限られた人たちのものであり、また現代のように各種の遺伝子配列が簡単に同定、報告されている時代ではなかったため、その疑問に答えるだけの内容はかかれていない。本書ではミバエにおける酵素の組み合わせの違いを取り上げているが、あまり説得力がないように思える。 ただ、これらの疑問は本書がかかれた以降のこの20年の間に確実に解決されているはずだ。 また、一部分子生物学の話が出てくるが、一般の読者にもわかるよう細部を省略しているのがかえって解りにくくなっている点は否めない。
Posted by 
通常は観察するのは難しい生物の進化を、ガラパゴス諸島の中でも特に周囲の環境から隔絶されたダフネ島にて観察した内容を元にした本。ガラパゴス諸島では一般的であるダーリンフィンチという鳥についての観察の話が中心である。俺の一世代ぐらいの期間で、ダーウィンの言う自然淘汰を観察できるとは非...
通常は観察するのは難しい生物の進化を、ガラパゴス諸島の中でも特に周囲の環境から隔絶されたダフネ島にて観察した内容を元にした本。ガラパゴス諸島では一般的であるダーリンフィンチという鳥についての観察の話が中心である。俺の一世代ぐらいの期間で、ダーウィンの言う自然淘汰を観察できるとは非常な驚きであった。
Posted by 



