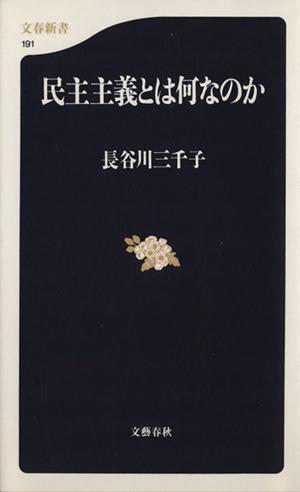
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
民主主義とは何なのか 文春新書
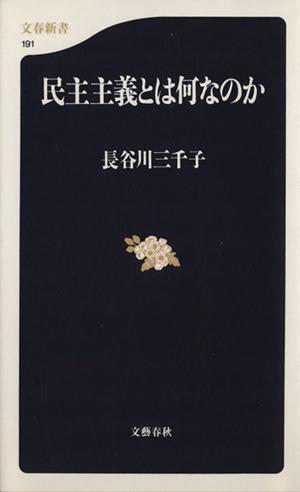
定価 ¥880
550円 定価より330円(37%)おトク
獲得ポイント5P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/3(月)~2/8(土)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋 |
| 発売年月日 | 2001/09/20 |
| JAN | 9784166601912 |
- 書籍
- 新書
民主主義とは何なのか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
民主主義とは何なのか
¥550
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.7
15件のお客様レビュー
とても面白かったです。本書の最大の特徴は、錦の御旗を与えられている「民主主義」「人権」という概念を疑えという問いかけです。以下私なりの理解を書きます。民主主義(デモクラーティア)は、古代ギリシャ時代においても、実は(最初は)邪道な統治方法だと考えられていた。その語源から言えば、民...
とても面白かったです。本書の最大の特徴は、錦の御旗を与えられている「民主主義」「人権」という概念を疑えという問いかけです。以下私なりの理解を書きます。民主主義(デモクラーティア)は、古代ギリシャ時代においても、実は(最初は)邪道な統治方法だと考えられていた。その語源から言えば、民衆(デーモス)が力(クラティア)を獲得して政治を行う、ということだが、この背景には、フランス革命に象徴されるように、絶対的統治者、あるいは国家に対する闘争を通じて民衆が権利を獲得する、というニュアンスが込められている。しかしいざ国民が革命を通じて統治権を得ると、その統治者への怒り、憎しみが高まり、再び闘争を通じて(あるいは弾劾裁判などの手段を通じて)、国民が鉄槌を下す、という「われがわれに敵対する」病的なイデオロギーであるというわけです。 これは日本人なら意外に納得できる説明ではないでしょうか。欧米人が権利を主張してばかりいるのを見ると嫌気がさす、という感覚を日本人はまだ持っているのではないかと思いますが、複数の人々が根拠(グラウンド)のない権利主張をしあっている場面ほど虫酸が走るものはありません。お互いが聞く耳を持っているわけではなく、理性的でもありません。 そして本書の最後では、民主主義を克服するということで、聖徳太子の十七条憲法を参照します。そこに書かれていることは、いかに各人が理性および知的謙虚さをもって相手の話を聞き、自分の視点を広げていくか、そして当初は考えもつかなかったより良い結論をみんなで探索するか(衆議衆論するか)、ということが重要なわけです。闘争を通じて自分の権利を獲得せよ、という無理性の行為ではないのです。そして主張するよりも聞くことの大事さ、これはまさに10人の主張を同時に聞いた?と言われる聖徳太子が示す、人間にとっても最も大事なスキルだということでしょう。
Posted by 
埼玉大学で名誉教授を務める著者が「民主主義」を根っこから紐解くことを試みた本。その構成要素と成り立ち、歴史といった角度から民主主義の正体を明らかにしていく。 我々は民主主義というものを一体どれだけ知っているのか、という著者の問いかけから始まる。確かに民主主義というイデオロギーを...
埼玉大学で名誉教授を務める著者が「民主主義」を根っこから紐解くことを試みた本。その構成要素と成り立ち、歴史といった角度から民主主義の正体を明らかにしていく。 我々は民主主義というものを一体どれだけ知っているのか、という著者の問いかけから始まる。確かに民主主義というイデオロギーを知ってはいるが、それがどんな根拠や論理によって支えられているかを理解しているとは言えない。 著者によれば、近代民主主義が社会で陽の目を浴び始めたのは18世紀のアメリカ革命とフランス革命以降である。どちらも既存の体制(絶対専制君主制)に対する革命であり、これによって「民衆が力を持って支配権を得る体制」(民主主義)を築き上げた。つまり、民主主義はその生い立ちからして「反体制」的、暴力的性質を持つものなのである。 また民主主義の主要な構成要素である「人権」も、欺瞞に満ちたインチキなものであるとする。現代社会で広く受けいれられている自然権の概念は、ロックによってもたらされたもので、「神によって与えられた」権利であるという、キリスト教的世界観の延長線上にあるものだ。しかしロックは権利に対応する義務を説明することはなく、故に不十分なロジックとして世に出てしまった。 著者が言うのは、自然権の本来の意味はホッブスが『リヴァイアサン』で唱えたように「各人が生存すること自体を根拠とする、各人の自由」だと言うことだ。つまりそれは誰から与えられたものでもなくて、ただ自らが生存することで持ち得る自由であり、ここでは「それをどのように放棄するか」が問われている。 この問いを克服するのが人間の「理性」である。今起こっている権利をめぐる様々な「矛盾」(「知る権利」と「プライバシーの権利」、「生存権」と「環境権」の真正面からの対立)は、この理性を回復することで解消に向かうことができるとする。 上記が本書の要約であるが、内容としては非常に興味深いものだった。著者の分析も一つ一つの事柄は丁寧で分かりやすい。 しかし、それを統合する段階がかなりなおざりになっている。故に繋がりがわかりにくい。 大筋を掴んだ後に再読すると理解できた。難解で読みにくい本だが、理解できれば教養は深まるとおもう。
Posted by 
「民主主義」の光の側面のみに目をうばわれている現代の知的状況を批判し、その闇の側面を明らかにしている本です。 著者は、政治的には対立する立場に立つであろう福田歓一の『近代民主主義とその展望』(岩波新書)を参照し、そこで福田が「民主主義」ということばのいかがわしさに目を向けている...
「民主主義」の光の側面のみに目をうばわれている現代の知的状況を批判し、その闇の側面を明らかにしている本です。 著者は、政治的には対立する立場に立つであろう福田歓一の『近代民主主義とその展望』(岩波新書)を参照し、そこで福田が「民主主義」ということばのいかがわしさに目を向けていることに注目します。そのうえで、「ヴァンデ事件」という、フランス革命のさなかに起こった血なまぐさい事件をとりあげて、「民主主義」の裏面を明らかにします。 その後著者は、ギリシアにおける僭主制と民主制の概念にまでさかのぼり、民衆のなかから生まれる僭主を排除しようとする民主制のありかたを、「われとわれが戦う」病ということばで表現し、民主制の起源にひそむ問題にせまろうとしています。さらに著者は、ホッブズとロックの議論の差異に着目し、「人権」という概念がどのような経緯で仏蘭西人権宣言やアメリカ独立宣言のうちに取り入れられるようになったのかということを明らかにします。 「民主主義」の輝かしい理念ではなくその現実について、歴史的な解説をおこなっているところは興味深く読みました。
Posted by 



