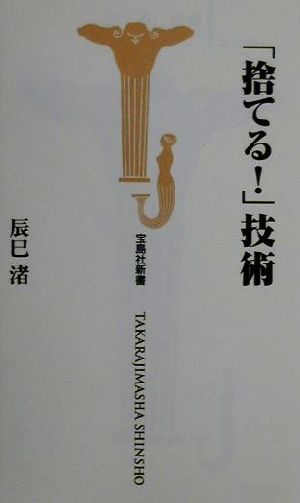
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
「捨てる!」技術 宝島社新書
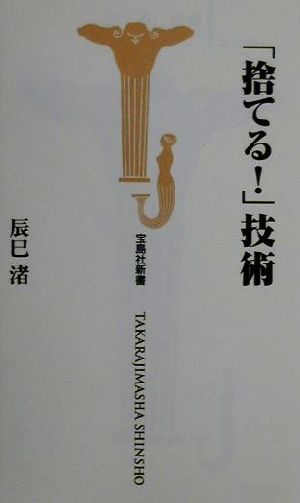
定価 ¥748
110円 定価より638円(85%)おトク
獲得ポイント1P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/8(土)~2/13(木)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 宝島社 |
| 発売年月日 | 2000/04/24 |
| JAN | 9784796617918 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/8(土)~2/13(木)
- 書籍
- 新書
「捨てる!」技術
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
「捨てる!」技術
¥110
在庫あり
商品レビュー
3.2
58件のお客様レビュー
先日読んだ著作が良かったので、BOOKOFFオンラインにて辰巳渚さんの著作をまとめ買いした。 今私は「整理収納アドバイザー」の資格の勉強中なので、タイムリーだったし。 ベストセラーになったという本書、2000年4月が初版でもう24年も前の本だ。著者が35歳の時の本ということにな...
先日読んだ著作が良かったので、BOOKOFFオンラインにて辰巳渚さんの著作をまとめ買いした。 今私は「整理収納アドバイザー」の資格の勉強中なので、タイムリーだったし。 ベストセラーになったという本書、2000年4月が初版でもう24年も前の本だ。著者が35歳の時の本ということになる。 ものごとの本質を突いているからなのか、今でも充分読める。リサイクルの方法などについては情報が古いが、それは仕方ないとして、モノとの付き合い方、捨てる際の考え方などは今でも充分通用する。 それというのも著者はマーケティングの仕事をしていてモノの本質や売らんかなの商売のあり方などにも通暁しており、データ分析の裏打ちがあっての論考およびメソッドだからということらしい。 現代の家庭の現状分析にも優れていて、耳の痛いトピックもちらほら。 目から鱗、というような劇的な読書体験とはいかなかったが、現代の住まいの問題の本質をついていたように思う。
Posted by 
2000年の本、110万部。今となってはコンセンサスを得られている内容だが、当時はコペルニクス的転回だったのだろう。
Posted by 
捨てるテクニック、というより、捨てる気構え(?)について説いた本。いつか使うかも、と思ってものが捨てられないひとのための本であって、そうではないひと、例えばぼくみたいに、邪魔なものがあるけど単に捨てる手間が面倒なだけ、というタイプにはあまり役に立たない。 2000年に出版された本...
捨てるテクニック、というより、捨てる気構え(?)について説いた本。いつか使うかも、と思ってものが捨てられないひとのための本であって、そうではないひと、例えばぼくみたいに、邪魔なものがあるけど単に捨てる手間が面倒なだけ、というタイプにはあまり役に立たない。 2000年に出版された本なので、内容はだいぶ古い。新聞雑誌やパンフレット、仕事の資料などのドキュメントは、いまどきクラウドなどのITを利用すればほぼ無尽蔵にとっておける。捨てなければならないのは、とっておく場所やコストと、再利用の回数が見合わないからで、場所もコストも不要なら、捨てる必要もないわけだ。そういう意味ではいい時代になったな、と思う。もしパソコンやクラウドを使っていなかったら、ぼくはドキュメントの山に埋もれていただろう。
Posted by 


