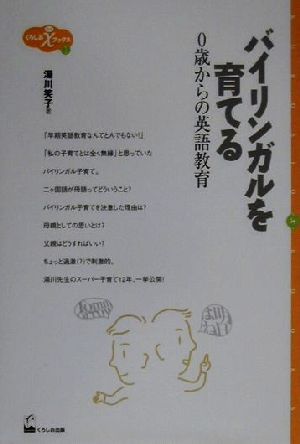
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1201-02-07
バイリンガルを育てる 0歳からの英語教育 くろしおΧブックス1
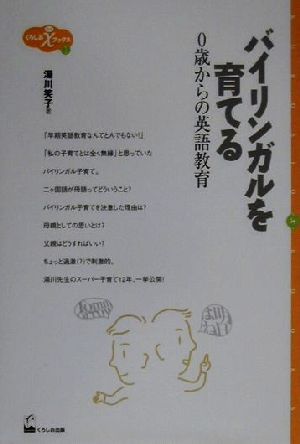
定価 ¥1,760
220円 定価より1,540円(87%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
3/23(日)~3/28(金)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | くろしお出版/ |
| 発売年月日 | 2000/04/25 |
| JAN | 9784874241929 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
3/23(日)~3/28(金)
- 書籍
- 書籍
バイリンガルを育てる
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
バイリンガルを育てる
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3
4件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
これまでの英語教育を受けて、「臨界期」を過ぎてしまった研究者でもある著者とその夫。自分たちが到達できる英語運用能力の限界を感じ、自らの子どもには、ネイティブによるチェックなしで、英語で論文を書けるようになってほしいと、自らの子どもたちをバイリンガルに育てようとする。 家の中では夫婦ともに英語で話し、毎日英語で読み聞かせを子どもが求めるだけしてあげ、自分の留学に夫と下の子を日本に残して、上の子だけ一緒に連れてでたり、外国人に家に滞在してもらったりと、ここまでするかと思うほど労力を厭わない、また、ラディカル取り組みをする。 そういえば、自分が勤めていたイマージョンの小学校にも、担任はしなかったが、いつもお父さんが子どもに英語で話している家庭があった。みな不思議に思っていたが、同じような考え方だったのだろうか。先日、中高生のインター校間のスペリングコンテストに出ていた。 私も自分の娘の小学校として、インターナショナルスクールに通うという選択を一方的にした。しかし、著者の取り組みを知った今、自分が娘の英語学習を学校任せにして、努力不足と言われても仕方が無い程度のことしかしていないことに気づかされた。読み聞かせはもちろんのこと、著者が言う通り、目にするもの耳にするものの全てが英語である環境に身を置くことは極めて重要なことであるが、一度も海外に連れて行ったことはない。来年こそ実施したい。 一方、著者の主張に疑問を感ずる点が二つある。 一つは、著者自身も主張が別れるとしている「臨界期」である。果たして、本当に成人してからでは、ネイティブのように文法チェックをしてもらわずに論文をかけるようにはならないのだろうか。私も日常的に英語を使って仕事をしている。もちろん、ダブルの同僚の英語での発言や書き物に自分のものが及ばないことをしばしば痛感させられ、ネイティブ向けの英語でのワークショップに出ると、理解の低さやスピードについて行けずに、もっと英語ができるようになりたいと願う。しかし、もうどうしようもないこととはあきらめておらず、いずれ英語圏に出る機会を待っている。また、成人してからではないが 弟子入りして相撲部屋に入る外国人力士の自然な日本語、歌でに自然な日本語を聞くと、少なくとも音声面での臨界期を疑う根拠はゼロではないと思う。 もう一つは夫婦で言語研究者のようであり仕方がないのだろうが、言語への意識が強く、その内容の習得への視点がかけていないだろうかという点である。著者自身が、良いと思ったEnglish supportの例として、ハワイの小学校での合科的なセマティックユニットの「海」の実践を紹介していたが、言語はその内容習得、思考と理解からは切り離せないのではないのだろうか。 いずれにせよ、選択は異なるものの同じような状況を共有している著者の問題意識には興味が尽きない。
Posted by 
わが子がそのまま博士号の実験台になったようだ。バイリンガル教育は確かに面白い。親の都合で海外生活を余儀なくされ、その多大なメリットと代償を子供が受ける。筆者の日記を元に書いたこの本。実は読むのに4年もかかった。あまりに細かいことが多過ぎて、興味を続かせるのが大変だった。印象に残っ...
わが子がそのまま博士号の実験台になったようだ。バイリンガル教育は確かに面白い。親の都合で海外生活を余儀なくされ、その多大なメリットと代償を子供が受ける。筆者の日記を元に書いたこの本。実は読むのに4年もかかった。あまりに細かいことが多過ぎて、興味を続かせるのが大変だった。印象に残ったのは、筆者の子供2人を「日英両方のネイティブのレールにしかっりのっている」と自負しているところ。立派なものだ。英語と日本語の言語格差を考えると、おそらくこの2人は今後英語の環境に強制的におかれない限り、日本語が主流になっていくであろう。私の子供たちも同じような立場に現在いる。英日もかなりできると親として自負しているが、ある流暢さの頂点までくれば「通訳技術」を学ばせ、更に深い言語知的能力を付けさせてあげたい思っている。私も日英ほぼネイティブ(少なくとも発話に関しては)であるが、通訳の言語変換能力のよな力は、人格形成にとってもよいと思う。しかし、あまりこれをし過ぎると、日英の発話における「流暢さ」を失う恐れもある。私の知っている1流の通訳者の中で「自分の思い」をネイティブと対等に話し続ける「連続的流暢さ」を備えた人はほとんどいない。言語変換をしすぎると常に変換をしないと話せない職業病に陥ることもある。まず「流暢さ」それから「通訳能力」である。その反対ではない。しかし、日本ではこれがどうしても反対になる傾向だ。難しい問題だが、専門家の責任は大きい。
Posted by 


