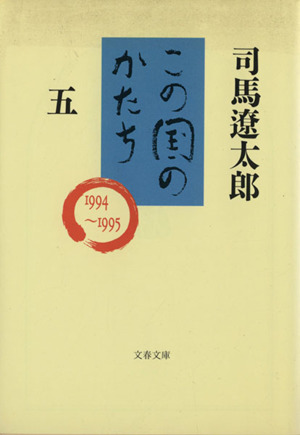
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 文庫
- 1225-02-03
この国のかたち(5) 文春文庫
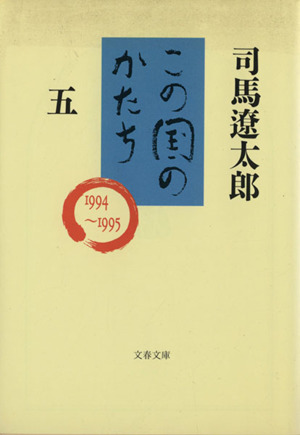
定価 ¥737
385円 定価より352円(47%)おトク
獲得ポイント3P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗到着予定:2/27(金)~3/4(水)

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/27(金)~3/4(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋 |
| 発売年月日 | 1999/01/07 |
| JAN | 9784167105846 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/27(金)~3/4(水)
- 書籍
- 文庫
この国のかたち(5)
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
この国のかたち(5)
¥385
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.6
20件のお客様レビュー
この国のかたちも5巻目。今回は宗教と学問のお話が中心で少しとっつきにくかった。 これとは対象的におまけとして司馬遼太郎氏の口述をもとに編集された文書が掲載されておりこれが面白い。氏が過去に小説にした人物たちを取り上げており、龍馬や大村益次郎、高杉晋作と河井継之助との違いなど、こぼ...
この国のかたちも5巻目。今回は宗教と学問のお話が中心で少しとっつきにくかった。 これとは対象的におまけとして司馬遼太郎氏の口述をもとに編集された文書が掲載されておりこれが面白い。氏が過去に小説にした人物たちを取り上げており、龍馬や大村益次郎、高杉晋作と河井継之助との違いなど、こぼれ話的なもので興味深かった。
Posted by 
https://opac.lib.hiroshima-u.ac.jp/webopac/BB01853884
Posted by 
・儒教の危険性 ・明治人が持っていた職人的合理主義 ・室町時代の特異性 ・連歌の魅力 ・大村益次郎、高田屋嘉兵衛の魅力
Posted by 


