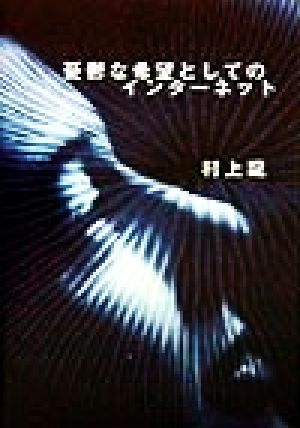
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1211-04-01
憂鬱な希望としてのインターネット ダ・ヴィンチ・ブックス
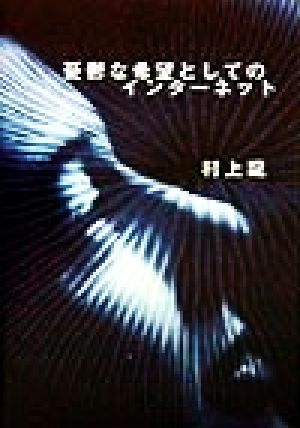
定価 ¥1,540
110円 定価より1,430円(92%)おトク
獲得ポイント1P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | メディアファクトリー/ |
| 発売年月日 | 1998/09/24 |
| JAN | 9784889916157 |
- 書籍
- 書籍
憂鬱な希望としてのインターネット
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
憂鬱な希望としてのインターネット
¥110
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
「分子とDNAだけをもっている原始的な細菌が 発生して光合成を始めた結果、 地球に酸素が増えていきました。 メタンや硫黄や水素で満ちていた地球の環境を、 彼らは20億年ぐらいかかって変えちゃったわけです。 新しい生命はものすごい頻度で細胞融合するんです。」 →いままでの理解では...
「分子とDNAだけをもっている原始的な細菌が 発生して光合成を始めた結果、 地球に酸素が増えていきました。 メタンや硫黄や水素で満ちていた地球の環境を、 彼らは20億年ぐらいかかって変えちゃったわけです。 新しい生命はものすごい頻度で細胞融合するんです。」 →いままでの理解では、細胞分裂の歴史と そこでの変異であったが、 「細胞融合」するという考え方がおもしろい。 「日本のような均一的な共同体の中ではという 前提つきですが、ネットでは本当に 奇妙な自浄作用が働くんですよ。 こういうことをやることは人間として恥ずかしいことだとか、 他人の意見をもっと公平に聞くべきだとか、 人から批判されることに馴致すべきだとか、 フェアな論理が存在しているんですね。」 「一人が他を裏切って自分だけ生き延びていくような 行動をとると全体がサバイバルする 確率は低くなることがわかりました。 これは細胞融合でも同じで、 自己保存力が強い細胞型の細胞を殺して テリトリーを広げていった場合のサバイバルの確率と、 細胞が相互に協力し合って生存していく場合の 種の生存確立は、後者の方が断然高いことがわかっています。」 「相手が生きていくことを助ける、 そして感謝されることに喜びを感じる人が 絶対的に多数であることは事実です。 あいまいな性善説ではなくて、 人間がサバイバルしていくうえでの 純粋な生物学的な論理として、 感謝される喜びをモチベーションとする 行動様式というモノがあるわけです。」 「不特定多数の人の言葉が入り乱れる 掲示板のような場で一番大切なのは、 表象能力なんです。 ある書き込みに対して意見を述べるときに、 その人が相手の言葉の核心を読みとって、 そのメッセージにむけて自分の考え方を表象化し、 自分の言葉で正確に言説化することが大切なんです。 きちんと表現できてさえいれば、 どんな厳しい批判でも人間は受けとめられるんです。」 「作者が読者に情報を与えるのみならず、 読者によって作品の本質を教示される、 そういうインタラクティヴィティの形を 発見できたことがうれしかった。」 インタラクティブ 情報の相互交流、相互作用、双方向性 「日本人は歴史的に藩や地域社会に所属していて、 近代になってからも国家に、戦後は企業という風に、 共同体へ依存してきた歴史があるから、 日本人が個として生きるのは困難だと いうようなことをいう人がいます。」 「テクノロジーとエコロジーを両立させる。」 「井上光晴は『限りなく透明に近いブルー』について、 『現代における青春の、もっともビランした部分を、 悔恨も悲哀もなく」描いた作品と評価してくれましたが、 それは葛藤がなかったということだと思うんですね。 じゃあ葛藤ではなく何を描いてきたかというと、 それはコミュニケーションなんです。」 「僕にとって小説というのは、 自分の中の情報を消費していく作業です。」 「いま日本は黒船の来航に匹敵するような 歴史の端境期だと思います。 ・・現代は、物語の力をかりなければ 捕捉できないぐらいの大きな変動なんですね。 そういう意味では、現在ほどフィクションを書くことの意味が 問われる時代はないといってもいいかもしれません。」 「現実を正確に表象化しようとするフィクションが ドキュメントになるという不思議な逆転現象が 起こっていると思います。」
Posted by 
7年前に書かれたとは思えないくらいネットの本質に迫っていると思う。7年経った今を見て著者がどう思っているか知りたいところ。新しいメディアに対して常に実践的な著者の言葉から、ネットに関わる者の心構えを知りました。
Posted by 



