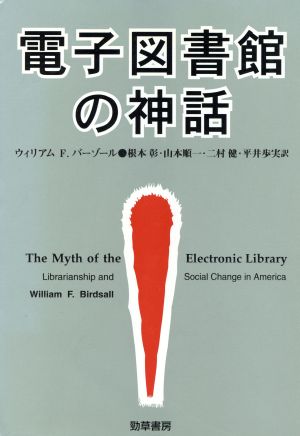
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-01-00
電子図書館の神話
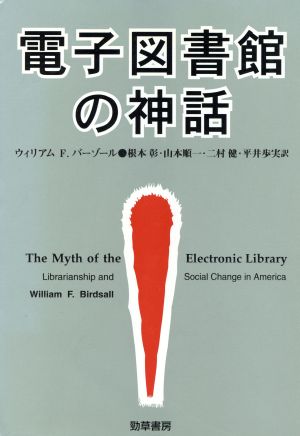
定価 ¥3,740
220円 定価より3,520円(94%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 勁草書房/ |
| 発売年月日 | 1996/04/10 |
| JAN | 9784326000173 |
- 書籍
- 書籍
電子図書館の神話
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
電子図書館の神話
¥220
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
IoTやコンピュータ等デバイスの普及が途上の20世紀において、技術革新によるアメリカでの図書館電子化について真剣に述べられている専門書。 まだアナログな手法が強かった時代、未来を見据えて新技術を取り入れる業種が増える中で図書館は保守的でした。 図書館が扱う資料は紙媒体が多く、デジ...
IoTやコンピュータ等デバイスの普及が途上の20世紀において、技術革新によるアメリカでの図書館電子化について真剣に述べられている専門書。 まだアナログな手法が強かった時代、未来を見据えて新技術を取り入れる業種が増える中で図書館は保守的でした。 図書館が扱う資料は紙媒体が多く、デジタル資料は少なかったために当然そうなります。 しかし日本の現在の図書館を見てみると、オンライン蔵書目録“OPAC”によってPCやスマートフォン等から検索と予約が行える時代になっています。 アメリカの現代の図書館においては電子書籍の貸出も行い、北欧等の図書館ではPC・TVゲームの利用も可能になりました。 少しずつデジタル化に対応してきている現在の図書館ですが、本書はそれを構想の段階から図書館員の処遇も含めて考察しています。 図書館員・司書がデジタル化の行きつく先でどうなるのか、本書では開業医と同等の専門性を持つ“情報ブローカー”のような存在になるだろうと予測しています。 デジタル化が促すのは情報の量産と氾濫で、そこから信用できるものを選択するには司書のスキルが役立ちます。 しかしそれ故に、現在日本の図書館法に定められている図書館業務で稼いではいけない点から逸脱した司書、“開業司書”や“闇司書”と言える生き方が待っているのかもしれません。 私自身はどのような形態であれ司書として生きていく所存ですが、技術の進捗状況を見ているとそんなサイバーパンクな世界が存命中に到来するかもしれませんね。 司書としても個人としても、色々と考えさせられる一冊でした。
Posted by 
2009 12/31読了。筑波大学図書館情報学図書館で借りて読んだ。 1990年代までの図書館あるいは図書館員の在り方を巡る言説を、公共図書館を基盤とし、図書館員を人間志向的専門職と位置づける「場としての図書館の神話」とドキュメンテーション・専門図書館を基盤とし図書館員を非人間...
2009 12/31読了。筑波大学図書館情報学図書館で借りて読んだ。 1990年代までの図書館あるいは図書館員の在り方を巡る言説を、公共図書館を基盤とし、図書館員を人間志向的専門職と位置づける「場としての図書館の神話」とドキュメンテーション・専門図書館を基盤とし図書館員を非人間志向的(あるいは伝統的)専門職として位置づけようとする「電子図書館の神話」という2つの神話を用いて整理・検討した著作。 既に原著発表から15年が経ち、情報化や電子図書館については状況が激変しているところも多いが、基本的な2つの神話の併存構造は現在も変わっていないと言え、今なお電子図書館、あるいは場としての図書館を考える上で重要な文献であると考えられる。 一方でなぜドキュメンテーション・専門図書館を基盤とする「電子図書館の神話」の信徒が図書館員全体に対しメッセージを発しようとするのか、言いかえれば館種を超えて、あるいは機能を超えて神話を普遍化しようとする者が(中庸的な立場で満足できない者が)あらわれるのかと言う点についての考察が少ない部分が物足りなく感じる。 「電子図書館の神話」と「場としての図書館の神話」を信じる人ではそもそも違うものを見ているのではないか、「図書館」という枠に捉われて本来の自分の興味の範疇にないものまで一緒くたに語ろうとしていないか・・・と言う点に興味が湧いた。
Posted by 



