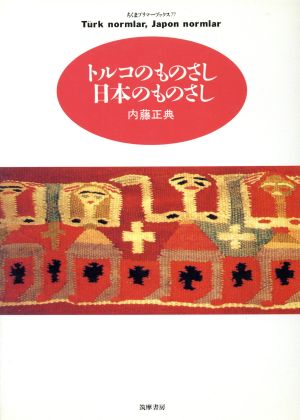
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-05-03
トルコのものさし日本のものさし ちくまプリマーブックス77
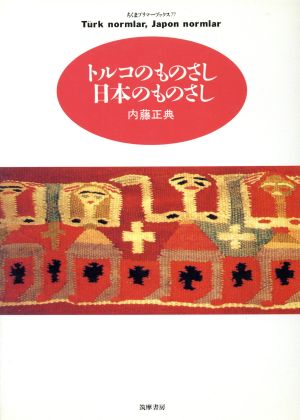
定価 ¥1,174
220円 定価より954円(81%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房/ |
| 発売年月日 | 1994/02/10 |
| JAN | 9784480041777 |
- 書籍
- 書籍
トルコのものさし日本のものさし
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
トルコのものさし日本のものさし
¥220
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
トルコのイメージは、浦沢直樹の『モンスター』で最初に描かれるドイツのトルコ人街、ここ数年自動車産業の集積などで喧伝される「勤勉な国民性」、でもやっぱりちょっといい加減なトルコ人男性などなど。 本書は清水義範さん『大人がいない』で知って手に取った。 夫婦の絆、親子の絆は完全に独...
トルコのイメージは、浦沢直樹の『モンスター』で最初に描かれるドイツのトルコ人街、ここ数年自動車産業の集積などで喧伝される「勤勉な国民性」、でもやっぱりちょっといい加減なトルコ人男性などなど。 本書は清水義範さん『大人がいない』で知って手に取った。 夫婦の絆、親子の絆は完全に独立していて、親子が友達のようになったりすることはありえない。子供に対しては「惜しみなく愛情を注ぐ半面、子として親に従うべきことを徹底的に教え込んでいる」「おまえのために働いているんだぞなんて恩着せがましいことはいわない」「トルコの父親は仕事によって得たものを、すべて家族に還元しようとする」「決して容易ではない生活を送りながら、子供を守り、子供を他人に対して誇りにしながら育てていくトルコの親の姿」 本書は、家族像だけでなく、そして「トルコ礼賛・ニッポン軽視」ではなく、バランスよくトルコ事情が描かれており(若干、今からすると一昔前のトルコになるが)、行ったことないけどちょっと身近に感じられる良書だった。
Posted by 
◆日本のものさしを見直してみよう p.6-8 日本の産業界には「外国人労働者は受け入れてもいいが、来るなら単身赴任にしてくれ」という虫のいい主張がある。この点について、外国から労働者を受け入れてきたほとんどのヨーロッパ諸国は、まったくちがう立場をとっている。今でこそ、かなりきび...
◆日本のものさしを見直してみよう p.6-8 日本の産業界には「外国人労働者は受け入れてもいいが、来るなら単身赴任にしてくれ」という虫のいい主張がある。この点について、外国から労働者を受け入れてきたほとんどのヨーロッパ諸国は、まったくちがう立場をとっている。今でこそ、かなりきびしく制限しているが、原則的には家族が同居するのは基本的人権の一部で、それを帰省することはできないという立場である。トルコ人をはじめとする外国人労働者が大量に定住して大きな負担になっているドイツでさえ、この原則だけは今も崩していない。(略) 自分のものさしで相手をはかるときにはなんの痛みも感じないが、相手のものさしを自分に押しつけられるとどういう思いがするか、そのことを知らないと、日本人は国際社会で自分の意見を相手に理解させることはできない。 ◆トルコ人のものさし、日本人のものさし p.10-11 それまで黙って聞いていた別のトルコ人の友人がさとすように口を開いた。 「だからいっただろう。日本がここまで発展したのは、おれたちには想像もつかない働き方をしてきたからなんだ。おまえが働き者であることはおれも認めるよ。だが、今だって、おまえの息子が急病になったと電話があれば、おまえはここからすっ飛んで家に帰るだろう。おれはトルコ人だから、それを止めようとは思わないよ。でも、日本では、それをしちゃいけないんだ。今はおまえは日本のことを好きだ、ぜったい行きたい国だっていってるけど、そういう国に住んでもずっと好きでいられるかな?」 「おれには無理だな。そんなところで働くのは……」 ◆民主化のジレンマ p.52-4 トルコをのぞくと、中東で成文憲法をもち、議会制民主主義が機能している国はほとんでない。トルコは建国と同時に議会制民主主義の基礎をつくっている。もちろん、何度も軍事クーデターによって、政党の活動が禁じられたり、言論の自由が制限された経験はある。しかし、1983年に軍事政権から民政移管が行われて以来、議会制民主主義はしだいに根をおろしつつある。 むずかしいのは、民主主義のもとで複数政党制が実現されると、前にふれたように、イスラム原理主義勢力も政党をつくって合法的に政治に加わってくることである。憲法の規定があるから、イスラム政党であることを看板にかかげはしない。 民主主義をとる以上、特定の政党の活動を禁止することはできない。それをすれば、民主主義は死んでしまう。しかし、その政党が、将来政権をとったとき、民主主義を否定する可能性をもっていたら、どうしたらよいのだろう。 「神の命ずるところ」にしたがう宗教政党に、人間が「神の意向」にもさからうことを認める寛容の精神があるだろうか。そこにトルコが建国以来かかえる政教分離のむずかしい問題がある。
Posted by 



