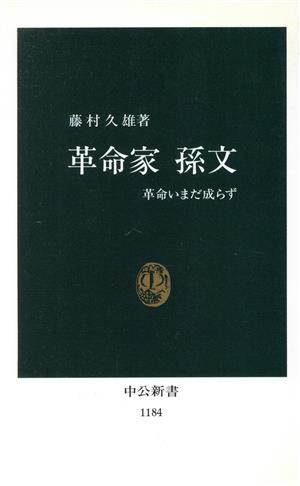
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-26-02
革命家 孫文 革命いまだ成らず 中公新書1184
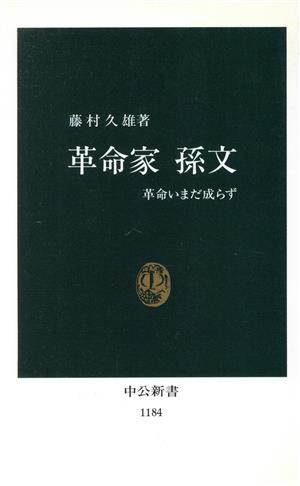
定価 ¥748
220円 定価より528円(70%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論社/ |
| 発売年月日 | 1994/04/25 |
| JAN | 9784121011848 |
- 書籍
- 新書
革命家 孫文
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
革命家 孫文
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.5
2件のお客様レビュー
孫文は、中国に適した理想的な共和国の建設を目指した。彼の言う「三民主義と五権憲法の国家」である。最も完美な国家であった。欧米における議会制民主主義の欠陥を克服したものであり、またソ連型の社会主義国家をも超えるものであった。 孫文の目指したものは、主権在民の大原則下、五権分立...
孫文は、中国に適した理想的な共和国の建設を目指した。彼の言う「三民主義と五権憲法の国家」である。最も完美な国家であった。欧米における議会制民主主義の欠陥を克服したものであり、またソ連型の社会主義国家をも超えるものであった。 孫文の目指したものは、主権在民の大原則下、五権分立の憲法と民権の直接的行使による地方自治の徹底。五権分立とは立法、司法、行政、考試、監察の五権により、三権分立の不備を補うもの。五権による政府の治権を、人民のもつ選挙権、罷免権、創制権、複決権の四権で管理する体制。 欧米先進諸国の制度には不備があるから、新生中華民国では、それを補いより完全なものにしなければならないと考えた。議会制民主主義国にみられる三権分立の、立法、司法、行政の三権の他に、それらと同じ重みをもつものとして、考試権と監察権を加えて五権分立とした。 孫文の五権憲法は、一見、欧米型の三権分立に、中国の古くからの考試(科挙)、監察(御史)の二権をもってきて、継ぎ足したかのような感じを与える。寄せ集めのようにも思われそうだが、人民の四権による政府の五権の管理など、民主国家中国を基礎から固めて築き上げようとする、孫文の強い意欲と苦心の理論構築とによるものであったといえる。 二千年を越す専制王朝を瓦解させ、中華民国を建国した革命家、孫中山。 あの世から現在の中華人民共和国をどう見るか。
Posted by 
孫文や辛亥革命について著した著作は数多あるが、本書は孫文の身にスポットを当て生涯を忠実に辿った伝記であるといえるだろう。死を前にして「革命いまだ成らず」と遺訓し、後の革命の完成を民衆に託したといわれるが果たしてどうだろうか。眉唾ものだと私は思う。後世の人たちの創作ではないのか。...
孫文や辛亥革命について著した著作は数多あるが、本書は孫文の身にスポットを当て生涯を忠実に辿った伝記であるといえるだろう。死を前にして「革命いまだ成らず」と遺訓し、後の革命の完成を民衆に託したといわれるが果たしてどうだろうか。眉唾ものだと私は思う。後世の人たちの創作ではないのか。 孫文は理想主義者であったと思う。「建国方略」や「国家建設」などを著して世界中で最も理想的な民主国家を目指している。孫文は建国半ばで亡くなったが、いまだその理想国家は実現していない。現在の政権もその理想には程遠いにもかかわらず孫文を「革命の父」と崇めているのは面白い現象だ。孫文が建設しようとした「世界で最も新しい、最も進歩した国家」の骨幹を要約すると、 ① 独特な政治体制 ② 豊かな国家経済 ③ 漸進的な土地改革 の3点になるという。なんとなく現在の中国で実現されつつあるように見えるが、それぞれ意味合いが違っているようだ。 また孫文はたびたび来日し日本人からも少なからず支援を受けたことはつとに知られているが、逆に日本政府は冷たかったこともあってか本書では日本との関係についてはほとんど触れていない。これについては別に詳細な本が各種出版されているのでそちらを参照することとしたい。 孫文が亡くなるところで本書もきっちりと筆を止め、その後については語っていない所が潔く好感が持てる。大まかに孫文の一生を知るには良書と思った。
Posted by 



