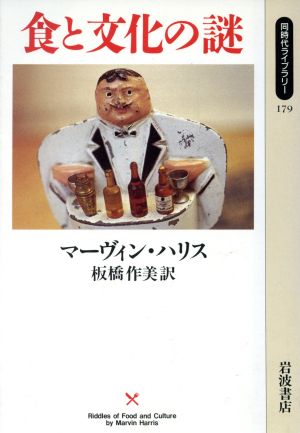
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-27-00
食と文化の謎 同時代ライブラリー179
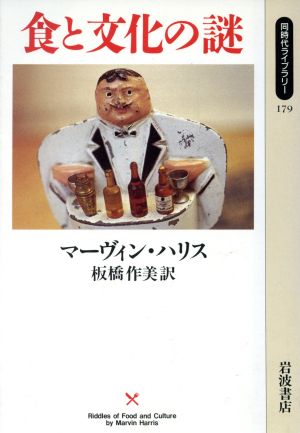
定価 ¥1,282
550円 定価より732円(57%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店/ |
| 発売年月日 | 1994/03/15 |
| JAN | 9784002601793 |
- 書籍
- 新書
食と文化の謎
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
食と文化の謎
¥550
在庫なし
商品レビュー
4
1件のお客様レビュー
地域によって食される食物やタブーとされる食物が異なるのは、エネルギーや栄養素の摂取や、獲得に要する時間や労力と得られる利益との差、環境への影響、人口密度などが異なるからであるという立場が貫かれている。説得力もあり、食文化とその背景の全体像をつかむことができる。 インドで牛肉が食...
地域によって食される食物やタブーとされる食物が異なるのは、エネルギーや栄養素の摂取や、獲得に要する時間や労力と得られる利益との差、環境への影響、人口密度などが異なるからであるという立場が貫かれている。説得力もあり、食文化とその背景の全体像をつかむことができる。 インドで牛肉が食べられなくなったのは、人口増加と森林の縮小のためで、乳牛は牛肉よりもカロリーや蛋白質が得られる効率が高く、雄牛は鋤を引く農作業に欠かせないことから大切にされるようになった。 反芻してセルロースを消化できる動物を飼育することによって、人間消費用の作物をわけあわずに肉とミルクを得られた。 元来、水の豊かな谷間や川岸の木陰をすみかとしていたため汗腺がなく、暑く乾燥した気候と生態環境にはあっていない豚は、肉以外ほとんど役に立たないため、森林破壊と人口増加とともに中東から姿を消した。 馬肉のタブーが始まったのは、中東に古代帝国がおこったときで、BC900年頃、騎兵の乗り物として使われ始めた。 ミルクに含まれるラクトーゼは、ラクターゼという酵素によって単糖類に分解されて吸収される。成人になってもラクターゼを持つ人々は世界的には少数派であり、保有率が高い集団は濃緑色の葉野菜を作ることができない地域で、カルシウムを摂るために必要だった。南インドや中国では、濃緑色の葉野菜と豆類からカルシウムを得ることができたため、ミルクから摂る必要がなかった。 大部分の昆虫は、一定の収穫量に対する時間的、またエネルギー上のコストの点で非常に劣る。食べられる昆虫は、体が大きく、一度に大量に捕まえることができるものに限られている。 アステカ人が家畜とすることができたのは、シチメンチョウと犬だけで、動物性たんぱく質が不足していた。ただし、戦争カニバリズムは副産物に過ぎない。
Posted by 



