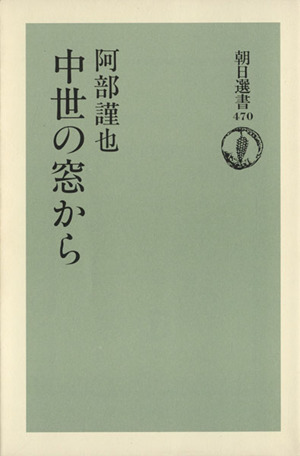
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
中世の窓から 朝日選書470
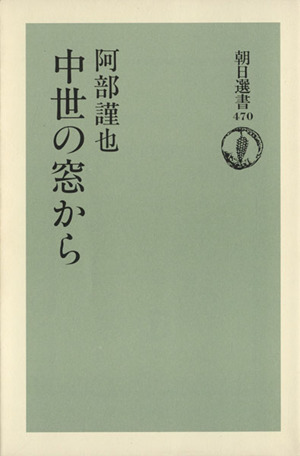
定価 ¥1,442
660円 定価より782円(54%)おトク
獲得ポイント6P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
12/5(木)~12/10(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞/ |
| 発売年月日 | 1993/03/25 |
| JAN | 9784022595706 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
12/5(木)~12/10(火)
- 書籍
- 書籍
中世の窓から
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
中世の窓から
¥660
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.5
2件のお客様レビュー
日本人がヨーロッパを理解しようとする時に欠ける何かを、中世の人と人との関係から得ようとする本。新聞の連載だったものなので一般向けに分かりやすく語りかけるような文章。 市民の暮らし、貨幣の価値、つきあいの形、十二人兄弟の館、靴職人の世界、衣服のタブー、石と鉄、仮面の祭り、飛脚、子供...
日本人がヨーロッパを理解しようとする時に欠ける何かを、中世の人と人との関係から得ようとする本。新聞の連載だったものなので一般向けに分かりやすく語りかけるような文章。 市民の暮らし、貨幣の価値、つきあいの形、十二人兄弟の館、靴職人の世界、衣服のタブー、石と鉄、仮面の祭り、飛脚、子供の遊び、十一世紀の大転換、贈物で結ばれた世界、女性と異端、時代のはざまで―ユダヤ人―、聖性の喪失、音で結ばれた世界という章立て。 以下、面白かったエピソード。 聖母マリアは昇天したとされているので聖遺物がない、中世の家は「平和の場(アジール)」、逃亡者が畑の中におかれた馬鍬のところにたどりついた時は、1ペニヒ相当の小麦パンを食べる間そこにとどまることができる、帽子や石、靴をアジールに投げ入れれば安全圏に入ったことになる、多くの場合6週間と3日が期限、金属貨幣に呪術的な力、魔女に金貨を投げつければ魔女を傷つけ殺すことができる、鐘を鋳造するときに銀貨を混ぜる、かけっこはもっとも好まれた競技、ユダヤ人は帝国内のどこでも移動でき、結婚も離婚も商売も自由にできた。5歳になると学問所に通い、貧富の差なく文字や戒律、ユダヤ教の倫理や道徳を学んだ、手紙で権威ある大学者のレスポンサ(回答)を得るネットワークができた、15世紀初めのニュルンベルグの娼婦宿に関する市参事会の規則「管理人を置き、意志に反して仕事を強要されない、いつでも勝手に宿を出ることができる、少なくとも週1回は無料で入浴できる、個人営業は不可、宿での飲食物や衣類の代金を定め、結婚する時管理人は妨害してはならず、手工業職人が結婚する場合は職人に市民権が与えられる」、しかし15世紀末には市内での営業が禁止され、職人組合が娼婦との交渉を仲間に禁止し、宴会や舞踏会の出席も禁止、死んだ後は墓地に埋葬されず、皮はぎの処理場に埋められた、都市では市門の開閉のたびに笛が吹かれ、三時間おきに時刻を告げる教会の鐘の音が響き、物売りの声や歌が聞かれた、嵐は悪霊のしわざとされ、鐘をならして嵐を鎮めようとした、家畜につける鈴も悪霊や病から守るため、鐘の鋳造は遍歴する専門の職人、湖や地中に沈んだ鐘のモチーフは古伝説のなかに数多く残る、水面に上がった鐘にはすぐ上に布をひろげなければならない
Posted by 
●構成 Ⅰ 聖と俗の間 Ⅱ 職人絵の世界 Ⅲ 人と人を結ぶもの Ⅳ 原点への旅 Ⅴ ふたたび町へ -- かつてヨーロッパ中世は「暗黒時代」といわれ、文化への弾圧や停滞がその特徴とされてきた。しかし、現在では多くの研究者が、例えば「12世紀ルネサンス」といわれる古代復興もなされ、...
●構成 Ⅰ 聖と俗の間 Ⅱ 職人絵の世界 Ⅲ 人と人を結ぶもの Ⅳ 原点への旅 Ⅴ ふたたび町へ -- かつてヨーロッパ中世は「暗黒時代」といわれ、文化への弾圧や停滞がその特徴とされてきた。しかし、現在では多くの研究者が、例えば「12世紀ルネサンス」といわれる古代復興もなされ、また決して弾圧や停滞ばかりでないことを示している。 本書は、11世紀から12世紀にかけての、ハンブルグ及びニュルンベルグの町を中心として、市民社会の有り様を多面的に観察する。著者は人と人の関係を軸に、都市社会での民衆同士の係わり合いやそれによる規制・制限、あるいは集団関係の中での自由を描く。そして、人同士の関係性の変化や貨幣経済の導入、聖性の変容など様々なトピックを11~12世紀の大きな社会的転換の中に位置づけることで、読者は中世ヨーロッパの人々の暮らしを著者という窓ごしに観察するのである。 中世の社会史・民衆史を、モースの「贈与論」を理論的枠組みとして意識しながら、人と人、人とモノの関係性の中から読み解く労作である。 -- 【図書館】
Posted by 


