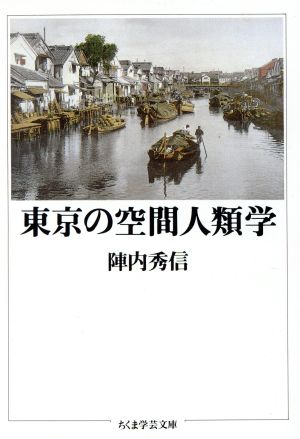
- 中古
- 書籍
- 文庫
東京の空間人類学 ちくま学芸文庫
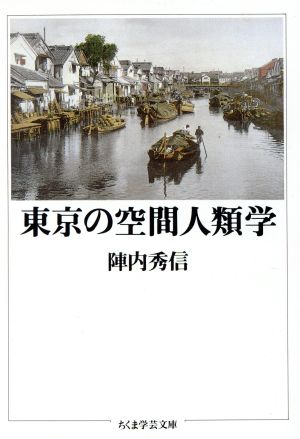
定価 ¥1,056
605円 定価より451円(42%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 1992/11/07 |
| JAN | 9784480080257 |
- 書籍
- 文庫
東京の空間人類学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
東京の空間人類学
¥605
在庫なし
商品レビュー
4
19件のお客様レビュー
東京の各地で再開発が行われていたり、計画中のところもあり、景色が変わっていく。 古本まつりで偶然見つけて買った今回の本は、1985年に発行されたものだが、2023年に読んでも面白い。 東京のベースは、江戸時代に作られたと言ってもいい。 著者は次のように表現し...
東京の各地で再開発が行われていたり、計画中のところもあり、景色が変わっていく。 古本まつりで偶然見つけて買った今回の本は、1985年に発行されたものだが、2023年に読んでも面白い。 東京のベースは、江戸時代に作られたと言ってもいい。 著者は次のように表現している。 まず、初期の江戸は、城下町の明快な理念に基づき、〈計画された空間〉としての為政者の意図通りに形成された。だが、明暦大火後、とりわけ中期以降の江戸は、城下町としての枠組みを超え、豊かな自然をとりこんで周辺部に大きく発展し、山の手では「田園都市」(川添登『東京の原風景』NHKブックス)、下町では「水の都」という、いずれも〈生きられた空間〉としての都市の魅力を大いに高めたのである。 明治以降、西欧を見本にしたが、江戸時代の枠を活用しながら、建物も西洋風でありながらどこか日本風という個性的なものができた。 所々に古い地図や写真を引用している。 浅草、東京、新橋、渋谷、新宿、池袋と浮かぶだけで、様々な顔を持つ東京。 読んでいくといろいろなことが頭の中をよぎる。
Posted by 
東京という都市の空間・街並み・建物を読み解くために、その地形や江戸のまちづくりを丁寧に掘り下げて分析・考察した読み応えのある本。江戸という都市が原型となり明治から現代にいたる東京の空間形成を解き明かしている。街歩きや東京の案内に興味深い視点を与えてくれる一冊。
Posted by 
1980年代の本だが、それだけに現代における都市景観の見直し論の基本書となっていると予想。名著。 「かつて大名屋敷が軒を連ねた一等地に住まう」みたいなマンション広告。まず、大名屋敷は軒を連ねない。 「屋敷を構える」「店を構える」はそれぞれ景観に対して違うアプローチ。前者は周囲...
1980年代の本だが、それだけに現代における都市景観の見直し論の基本書となっていると予想。名著。 「かつて大名屋敷が軒を連ねた一等地に住まう」みたいなマンション広告。まず、大名屋敷は軒を連ねない。 「屋敷を構える」「店を構える」はそれぞれ景観に対して違うアプローチ。前者は周囲を塀で囲い、緑に覆われ、屋敷を見せない。前者は通りに面し、生活空間を路地側に寄せる。 軒を連ねていたとしたら下級武士のエリア。その作りは現代の戸建の基本となっている。 そのそれぞれが江戸の独特の情緒を形作っている。 そして、あまたある坂を上り切れば、江戸のどこからでも富士を臨めるよう街が設計されていた・・・(感動)。 ちなみにヨーロッパは目抜き通りに面して高級住宅の玄関が立ち並ぶ。その頂点が通りの終点の広場に面した王宮。 「緑の都市」としての山の手、「水の都」としての下町。 これらの多くは震災、そして戦争から復興を通じて失われた。が、それでも江戸期の街づくりの姿勢は受け継がれている。著者は決して近代化否定論者ではなく、西洋の文物を何とか江戸の町の中に位置づけようとした先人たちの努力にも敬意を払っている。そこが素晴らしい。 しかしつくづく問答無用によくなかったのは、川の上に高速道路をかけたこと。 オリンピックに向けて仕方なかったとはいえ、本書を読むとなおさら無念極まりない。観光立国日本として、「水の都」の復活に期待(ただし気候変動の今、それを望むことがただしいのかはわからないが・・・)
Posted by 



