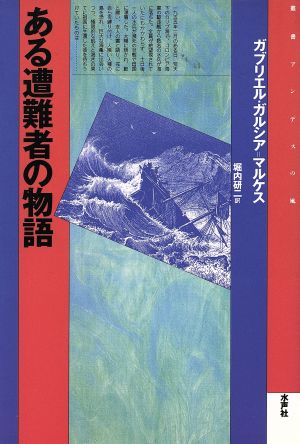
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1222-01-07
ある遭難者の物語 叢書 アンデスの風
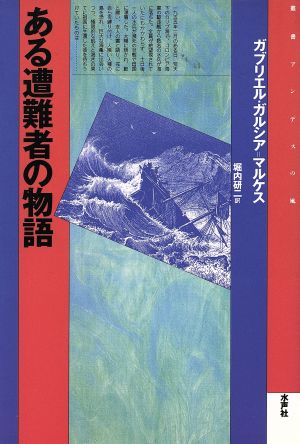
定価 ¥1,650
1,155円 定価より495円(30%)おトク
獲得ポイント10P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 水声社 |
| 発売年月日 | 1992/07/30 |
| JAN | 9784891762735 |
- 書籍
- 書籍
ある遭難者の物語
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ある遭難者の物語
¥1,155
在庫なし
商品レビュー
3.8
5件のお客様レビュー
嵐の海に放り出され10日間の漂流のうちに母国コロンビアに流れ着いた水兵の手記(ということになっているおそらくはフィクション)。これまでに読んだいくつかの「奇跡の生還」ものとの一番の違いは、読者が期待している「不屈の闘志」に必ずしも光を当てていないことだ。 例えば遭難した南極探検...
嵐の海に放り出され10日間の漂流のうちに母国コロンビアに流れ着いた水兵の手記(ということになっているおそらくはフィクション)。これまでに読んだいくつかの「奇跡の生還」ものとの一番の違いは、読者が期待している「不屈の闘志」に必ずしも光を当てていないことだ。 例えば遭難した南極探検隊を描いた「エンデュアランス号漂流」は、隊長シャックルトンの類まれなるリーダーシップが読んだ人を奮い立たせる。サン・テグジュペリの「人間の土地」は飛行機の黎明期、郵便航空会社に勤務するパイロットたちの遭難物語(アンデスの雪山に激突、サハラ砂漠に不時着)だが、人間の意志の強さを感動的に歌い上げる。 「救いは一歩踏み出すことだ。さてもう一歩。そしてこの同じ一歩を繰返すことだ・・・」(「人間の土地」、新潮文庫P.48) マルケスの作品は、もちろん根源に人間への賛歌を含んではいるが、淡々とした記述が重苦しい恐怖を掻き立てる。「私は一分毎に時計を見た。・・・時計が自分の気を狂わすのではないかと思われた。苦悶にとらわれた私はポケットにしまおうと時計を手首からはずしたが、それを手にした時、一番いいのはそれを海に投げ込むことだと思った。一瞬ためらった。やがて恐ろしくなった。時計がなくなったら今以上にひとりぼっちな思いにとらわれると思ったからだ。」(P.37) 猛烈な渇き、飢え。絶望しつつも一縷の望みを捨てきれない焦燥。戦争中、沈没した船の乗員でこれと同じ思いで、尚救われず死んでいった将兵がどれだけいたことだろう。それを強く意識させられたのは以下の描写。 「・・・まだ希望は失ってはいない。まだ・・・筏(いかだ)に体を縛りつけるという最後の手段が残っている。戦時中、数多くの死体がそのようにして発見された。・・・まだ夜までは、つなぎ止めないでいられるだけの体力があるように思われた。」(P.56) シャックルトンやテグジュペリと異なるのは、主人公に「なすすべがない」ということだ。 僕たちは人生を強い意志で切り開くことに、あるいはそうすべきであるという思想に慣れ過ぎている。が、舵を失った筏にのって大海原をただ漂流する、ひとりひとりの人生などむしろこっちに近いのではとふと気づかされる。 それでも人間は希望を持つことを止められない。食べ物を探す努力を止められない。生きる「本能」と生きる「意志」とは極限状況ではそう簡単に分けられるものではない。流されながらでも生きるのを止めることだけはしない、そういう感動もあるのだ、と思った。
Posted by 
1955年2月、荒波のカリブ海でコロンビア海軍の駆逐艦から海上に放り出された数名の水兵たち。ひとりは偶然にも一緒に放り出された筏に乗り込む。しかし、他の水兵たちは、大波に翻弄され、わずか数メートル先の筏にたどり着くことができず、海に沈んでいく。 そこから10日間のたったひとり...
1955年2月、荒波のカリブ海でコロンビア海軍の駆逐艦から海上に放り出された数名の水兵たち。ひとりは偶然にも一緒に放り出された筏に乗り込む。しかし、他の水兵たちは、大波に翻弄され、わずか数メートル先の筏にたどり着くことができず、海に沈んでいく。 そこから10日間のたったひとりでの漂流。太陽に焼かれ、そして極限的な餓え、渇き。幻覚。鮫との毎日の戦い。飛行機や船を見れば発見されたはずと喜び、鴎を見つけたり、海の色が変われば陸が近いと確信したり、しかしそのたびに裏切られて追い詰められていく。絶望の中彼はこう思う。「生き続けるよりも死ぬことの方がずっと難しい」。 そして10日目、祖国の海岸に漂着。英雄になる。そして、忘れ去られる。 マルケスが新聞記者だった時代、本人から取材して書いた「新聞記事」がこの物語。
Posted by 
海兵の遭難漂流物語、これは事実のルポルタージュなのか、作者による創作(事実+創意)なのか。後者説を取ると見えてくる本作の魅力を解説した訳者あとがきが、非常に良かった。勿論本編の読み応えは文句なし。
Posted by 



