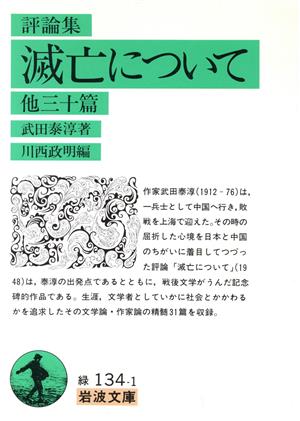
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-36-01
評論集 滅亡について 他三十篇 岩波文庫
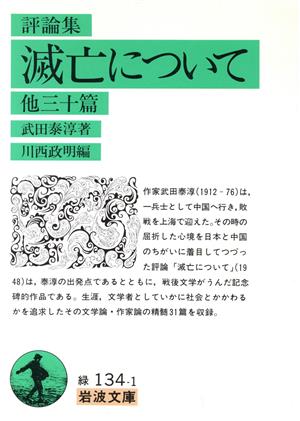
定価 ¥935
550円 定価より385円(41%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店/ |
| 発売年月日 | 1998/08/19 |
| JAN | 9784003113417 |
- 書籍
- 文庫
評論集 滅亡について 他三十篇
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
評論集 滅亡について 他三十篇
¥550
在庫なし
商品レビュー
4.5
3件のお客様レビュー
『武田泰淳対談集ー精神の共和国は可能か』(この本が検索できないので標記本を仮措定)が実際に読んだ本であり、それについての書評である。 武田泰淳の11人の文学者との対談集。 椎名麟三・中村真一郎・三島由紀夫・遠藤周作・西脇順三郎・寺田透・大岡昇平・いいだ もも・辻邦夫・玉城康四郎・...
『武田泰淳対談集ー精神の共和国は可能か』(この本が検索できないので標記本を仮措定)が実際に読んだ本であり、それについての書評である。 武田泰淳の11人の文学者との対談集。 椎名麟三・中村真一郎・三島由紀夫・遠藤周作・西脇順三郎・寺田透・大岡昇平・いいだ もも・辻邦夫・玉城康四郎・佐古純一郎との対面での論談集である。それぞれ作家の問題意識や執筆上の悩みついて忌憚のない真剣な会話がされている。武田泰淳の「蝮のすえ」「富士」などの作品も俎上に上げて、キリスト教や仏教における宗教との関わりについて、文学・小説・詩のことでもかなり深い遣り取りがされている。終戦直後の文学界における武田の立ち位置もよくわかる、同時に各人の作品やそれを描いた時の状況や思惑が滲み出ていて興味深い。
Posted by 
泰淳の小説に描かれていることがより良くわかるエッセイ集だ。仏教や、中国文学や、上海で敗戦を迎えた経験など。泰淳は諸行無常という言葉を、滅びゆくものへの哀愁というような固定化したイメージから解き放ち、全てのものは変わっていくがだからこそ何かが生まれる可能性がある、そこにこそ希望があ...
泰淳の小説に描かれていることがより良くわかるエッセイ集だ。仏教や、中国文学や、上海で敗戦を迎えた経験など。泰淳は諸行無常という言葉を、滅びゆくものへの哀愁というような固定化したイメージから解き放ち、全てのものは変わっていくがだからこそ何かが生まれる可能性がある、そこにこそ希望がある、というふうに積極的に捉え直している。泰淳の滅亡のイメージとはおそらくそういうものだろう。 そのことから未来を見据える視線が出てくる。「無感覚なボタン」が中でも特徴的である。時代が下るにつれてあらゆるものが無感覚になりつつある。例えば最近は合衆国の無人戦闘機が中東の辺りに飛んでゆき、操縦者は安全地帯でボタンを押すだけで人を殺せる。同じ人殺しでも昔は死に物狂いの取っ組み合いである。ここには行為するものの感覚に大きな差がある。何の苦労も感じないなら、人はそれをしてしまう危険が高い。こうした状況はなお進行するだろうことを泰淳は見通している。現代において、伊藤計劃や阿部和重はそういう状況を文学の問題として扱っているが、どこまで対抗出来るだろうか。
Posted by 
大学図書館で借りる 明治初年に、日本政府は僧侶の所帯を、法律的に許可した。また法然や親鸞、浄土真宗の先輩は、自己の苦悩の中からこの問題を早くから解決していた。 かぶきのセリフに「坊主ッけえり」という言葉がある。 坊主からひっくりかえって、俗人にもどった人間のこと。 正宗白鳥...
大学図書館で借りる 明治初年に、日本政府は僧侶の所帯を、法律的に許可した。また法然や親鸞、浄土真宗の先輩は、自己の苦悩の中からこの問題を早くから解決していた。 かぶきのセリフに「坊主ッけえり」という言葉がある。 坊主からひっくりかえって、俗人にもどった人間のこと。 正宗白鳥、志賀直哉の諸先生も若き日は、キリスト教の説教に感激し、のちにそれから離れたのだから、「坊主ッけえり」的気分を味わわれたことがあるに違いない。 僧侶にも寺院にも、一定不変の形式などあるはずがない。だからこそ、諸業無常なのだ。それだのに、所行無常を説く人自身が、無限の変化のありがたさをこばんで、へんに意地を張るのは、それこそ反仏教的というものであろう。 宗教の歴史は、分裂へ向かっているのか、それとも統一へ向かっているのか。難問である。 どうしても私には、宗教と宗教とが相争うことが不満である。
Posted by 



